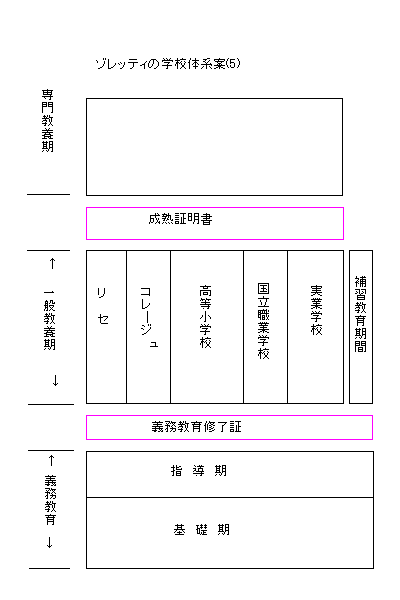R.H.卜ーニーの中等教育論
── 調和的統一学校論
(1)はじめに
イギリスの第一次大戦以後の教育の発展にとって、R.H.トーニーが執筆し、労働党の政策として出された『中等教育をすべての者に(Secondary Education for all)』(1922)が、極めて大きな意義をもっていることは、周知のとおりである。しかし、その評価となると、その意義を認める者の中でもいくつかの対立する論点が依然として残されている。そして、その対立点は単なる評価の相違ということに留まらず、中等教育、ひいては教育制度全体の構想についての論の対立を背景に持っている。
ではトーニー評価の論点とは何か。それは究極的には、トーニーの論は労働者階級の教育論の一典型であるのか、今日の「人的能力開発政策」の嚆矢なのかということに収斂される。
前者の立場に立つ成田はトーニーの『中等教育をすべての者に』について、三点で高く評価する。(1) この点は既に第三章で述べた。
一方、後者の立場に立つ竹内真一はトーニーに対して次のように批判している。
トーニーの社会批判は、前期資本主義的自由土地保有者の社会秩序に基づく倫理的なものであって、階級強調の立場にあった。そしてその中等教育論は「ウェッブとホブスンを接ぎ木したもの」で、生得的能力論に依拠しており、人文的教養論を軸としたエリート教育論であり、それ故統一中等学校に背を向けた人的能力論である。(2)
こうした対立からは次のような課題が提起されるだろう。
第一に、トーニーの中等教育論の土台となっている彼の「平等論」及び「社会観」の質的吟味である。1920年代、30年代は資本主義の変質の時代であるとともに、「自由・平等論」の転換期でもあった。
第二に、中等教育の「多様性」の検討である。言いかえれば、ハドーレポートの論理との関連を明確にすることである。両者は相反するとする成田説は、トーニーがハドーレポート作成の中心であったということの意味を説明しきれないし、両者を同一視する竹内説は明確に存在する相違点(例えば、トーニーが断固拒否した「安価な代替物」をハドーレポートは採用している)を事実上無視している。今日、後期中等教育については、「多様性」を全く否定する論は見当たらないのであって、その在り方が問題になっているとすれば、トーニーとハドーレポートの関係は避けて通ることのできない問題をなげかけている。
第三に、「試験制度」「能力論」が、トーニーの構想の中で、どのように位置付いていたかを明らかにすることである。教育史上(とりわけイギリスでは)試験制度の大きな改革は第二次大戦以後のことであるが、大戦間はそれを準備した点で大きな意義をもっており、トーニーの構想にも微妙に影響している。
<註>
- なお中等教育の発展を公正な制度への道と捉えるマスクレイブも同様な評価である。P.W.Musgrave "Society and Education" p263~264
- 竹内真一「R.H.トーニーと中等教育改革」『明治学院論叢』240号所収 竹内はこの主張をB.Simon "The Common Secondary School" に依拠して述べている。
(2)トーニーの平等論
<古典的平等論の変質>
トーニーが『中等教育をすべての者に』(1922)、『獲得社会 (Acquisitive Society) 』(1921)を出した時期は、フィッシャー法が可決され、その具体法である1921年の教育法が実施された時期であった。ところで、フィッシャー法の規定が義務教育年限の延長や、継続学校の義務化であったとしても、法の主要な意図が教育の拡大にあったわけではない。支配階級が教育に要求していたことは、第一次大戦によって国力が教育によって大きく影響されることを認識したとはいえ、主要には、まだ「政治教育」という側面から捉えられていた。
フィッシャーが強調したことも「市民精神 Citizenship 」の涵養であった。フィッシャーは法案が通過したとき、義務化はできなかったとはいえ「継続学校は、労働者の市民精神においても必ず好ましい影響を生むだろう。」と述べている。(1) 更に自由党の有力なイデオローグだったプライスは、1920年に次のように書いていた。
1868年、英国が普通選挙への幅広き第一歩を踏み出そうとしておった際に、これに対する有力なる反対者たるロバート・ローは社会において『諸君の学校教師を教育すべし』と叫んだ。二年後、公立小学校設置に関する英国最初の法律案が通過した。以来投票者はその権利の行使に適するように教育を受けなければならぬという法則は平凡化した。而して、民主政治の弁護者は無意識的に、又、自然な経路を迫り、教育は市民的機能を果たすのに必要な準備であるという命題から、教育は充分なる準備であるという命題に推移するに到った。(2)
こうした認識には3つの契機があった。第一に、教育を極端に国家主義的に利用して国力を急激に増大したドイツ帝国及びその敗北。(3) 第二に、ロシア革命による新しいイデオロギーの登場。(4) そして、第三に、1918年の普通選挙法の実施である。(5) したがって、これらに対応する以上、市民精神(Citizenship)の教育を重視することは当然のことであったといえよう。重要なことは、こうした中ですでに「平等思想」は、従属的な意味しかもっていなかったことである。ブライスは「市民的自由、宗教的自由、個人的自由、そして市民的平等(私法上の平等)、政治的平等(参政権)、社会的平等(階級的特権の除去)、自然的平等(ヒトであること)」と自由平等について整理するのであるが、最も重要である社会的平等については、階級的敵悔心を除去することに第一の対応策を見出し、「個人の自由な人権の発展が最も重要であり」、しかも、「政治的自由は財産上の平等がなくてもありうる」としたのである。 (6)
こうした自由党の考え方から、中等教育を平等に与えるという政策が出てこないのは当然なことであろう。
古典近代の「自由・平等」論が、社会的不平等の増大によって崩壊する。国家独占資本主義への移行は平等論に即してみれば、「形式的平等」は維持しながらも、実質的不平等を社会的事実として認知し、実質的平等を実現するためではなく、それを固定するべく階級的に異質な(不平等な)救済等を行うのであり、その意味で「不平等」を原則化するといえる。ハドーレポートが、それまで多様に展開してきた学校を、中等学校という名目で統合しながらも、明確に水準の異なる三つの学校に分割したのは、こうした論理に符合している。
<註>
- T.E.S.1918.8.8
- ブライス『近代民主政治』第一巻 1920 岩波文庫杉山武訳 p90
- 同上 p97
- 同上 第四巻 p281-294 いうまでもなくブライスはロシア革命に賛成ではないが、単純に反共的な反発を示しているのではなく、ロシア革命の中に抑圧された民衆を解放する要素を認めつつ、その「独裁的」な部分に反対しているのである。いかにして近代民主主義政治は共産主義よりも、民主的でありうるか、と自問しているのである。
- 河合秀和氏によれば、1918年の普通選挙法は、1867年選挙法改正の平坦な延長にあるが、はじめての普通選挙はやはり大きな政治的意味をもった。それは保守・自由二党制から保守・自由・労働の三党制への移行に端的に現れた。河合秀和『現代イギリス政治史研究』1974
- ブライス前掲第一巻 p72-88
<トーニーの平等論>
トーニーが『平等論』を復権させようとしたことは、それ故、時代批判として大きな意味を持っている。
では、トーニーの『平等論』は、ジグムント・ノイマンの言うように「課税と再分配」に帰着するものなのだろうか。(1) 確かに、『平等論』は、最終的には条件の平等に帰着する。『平等論』の地平に立つ限り、問題は平等にすべき条件内容の拡大に限定され、古典近代の「自由・平等論」に留まるといえるだろう。
まずトーニーは手がかりとして次のように書いている。
富の再分配や収入の平等が単純に平等をもたらすわけではない。生まれ、職業、知能、経済、性格等多面的に考察されなければならない。(2)
第一に、彼は社会構造を問題にするが、階級の存在、富の偏在が社会的不平等の現れである。(3) しかし、トーニーは階級的特権の廃止のみに留まっており、経済的不平等が決定的ではない、というように回避している。(4)
第二に、文化の不平等の問題である。このことは教育の課題である。
第三に、政治権力の不平等である。そして、トーニーの不平等論はここに焦点がある。
今日の社会の分化をもたらしているのは権力(Power)の不平等である。それが、富や健康や教育の不平等につながっているのである。(5)
そこでトーニーのたてる平等への戦略は、第一に、社会的に存在する権力の主体を公的な統制におくこと、(6) そして、権力の偏在によって生ずる不平等をそれ独自に社会的に是正することである。富に対しては税による再配分、教育の平等、教育の実際の拡大、労働者組織の発展の中にみていた。(7)
つまり、トーニーの平等論には二つの契機があった。一つは、市民社会における私的組織が、公的な性格をもちうる程に発展してきたこと。他の一つは、ロシア革命であった。そこで形成されたのは、ラスキを代表とする多元的社会主義論である。(8)
ラスキは国家について次のように言っている。
いかなる国家といえども、完全な意味における、つまり単に一時的であるにとどまらない最高権力を持たないことは、明らかだからである。(9)
民主政治においては、究極的原則は要するに自治なのである。(10)
これは諸団体、諸地域の自治を土台とする考えであって、基本的にはトーニーも同じ基盤にある。すなわち、J.リースが述べているように、トーニーやラスキは、社会における多様性と社会的経済的平等は両立する、という立場に立っていた。(11)
ラスキによれば、平等とは第一に、特権の存在しないこと、第二に、適当な機会が万人に開かれていること、第三に、人の第一義的必要に対して、充分の限界まで同一に応じてやることである。(12)そして、この平等と多元論の両立は、教育への期待を高める。(13)
自治を基盤として成り立っている社会には、自治の主体を形成するために、教育が求められ、現実に存在する不平等の再分配、調整機能が公的権力に期待されている。
では、「階級」はトーニーにどのように捉えられているだろうか。
彼によれば、階級は「経済的利益を同じくする社会的グループ」のことである。(14)そして、生産制度における位置と、社会的グループという二つの側面からみることができる。前者においては、雇用主、資本家と賃金労働者、地主と自作農などであり、後者は指揮し、組織する者と、多くの賃金労働者である。(15)
「経済的利害」が異なる集団(二階級)の間のめざすべき関係は、階級間の平等、同等の権利、一方が他を抑圧しないことになるであろう。だからトーニーにとって重大なことは、「資本の集中によって、大量生産がおこり、労働者を支配するに到っている。そうした少数者が統制していること」なのであった。(16)
そこで解決策は「大企業が公的支配に服すればよい」ということになる。そのための役割が「労働組合」に期待され、「工場委員会」とか「全国評議会」がつくられるべきであるとされた。そして、パートナーシップをトーニーは主張するのである。(17)そして、先述したように、その客観的基盤を、「所有」と「経営」の分離、教育の拡大、組合の発展などに見出していた。(18)こうした考えが具体的に顕著に現れたのが、彼の石炭産業国有化に対する先駆的、かつ強力な支持であったといえよう。(19)そこでは、「産業民主主義」が実施され、価格が上昇せず、労働者は充分保護され、生産が計画的になされると考えられていた。
以上のような階級観にたつトーニーにとって、共産主義は受け入れられるはずのないものであり、ソビエトは自由と民主主義のない全体主義と考えられた。(20)
では、卜一二一の社会論は、単純に竹内氏の言うように、前資本主義的なものであろうか。
なるほど、トーニーの平等論はロック的な「労働による平等」を思わせる。しかし、竹内氏が「私有財産制(もちろん生産手段の)存在そのものを全面的に否定せず、とくにその寄生的独占的形態の制限と排除を主要内容とする社会論」と指摘する論は、ロック的労働の復権というより、むしろケインズ的階級論に近いものを持っていると考えるべきであろう。(21)
さて、以上の階級観にたって、教育の階級性は、どのように捉えられていたろうか。
それは、彼の次の言葉によって端的に示されている。
イギリスの教育は、違う階級の子がそれぞれ違う学校に行くようになっている。全ての階級の子が同じ学校に行くようになるまでは、イギリスの教育制度は、文明社会の中で価値あるものとは言えない。(22)
これは明確に統一学校の主張であった。
全ての階級の子が同じ学校に行ったとしても、その学校の内容が支配階級に都合良いことが教えられているという意味での階級性は、トーニーには問題にされなかった。堀尾が指摘しているように、トーニーは、資本主義の下での機会の平等が「不平等になる機会の平等」に過ぎないことを認識していた。しかし、それを克服する為に考えるのは、「出発点の平等(equal start)」「開かれた道(openroad)」一そして、「環境の平等(equal environment)」であり、(23)それが、教育においては、全ての者が通う中等学校である。
もちろんここで、トーニーの階級認識、平等認識が階級の廃止に到っていないと批判することは、容易であり、誤りではない。しかし、具体的教育構想のレベルでは、階級の廃止が問題とされないことは当然であり、トーニーの場合、こうした社会論上の限界をもっていたとはいえ、教育制度構想はそれを前進させていたことが見過ごされるべきではない。
<註>
- ジグムント=ノイマン『現代史下』 p26 フェビアン協会では、むしろ、経済面よりも、教育と健康の重視が特徴と見られた。"Fabian News" 1931.7
- R.H.Tawney "Equality" 1931 p35,106
- ibid. p62-63
- ibid. p64
- ibid. p117
- ibid. p187
- ibid. p200
- ラスキが多元的社会主義という語を使ったわけではないが、社会主義の立場から国家支配の強化に反対しながら、ボルシェビズムを批判するという意識であったので、こう呼ぶのが適切であろう。
- ハロルド=ラスキ「主権の基礎」1918 『世界の名著60』中央公論 p37
- ラスキ『政治学大綱上』日高明三・横越英一訳 p127
- J.リース『平等 ── 真の原理はなにか』半沢孝麿 p129
- ラスキ前掲 p226-235
- ラスキは次のように述べている。「市民の教育は近代国家の中心問題である ── 民主政治の欠陥は主として民主政治への無知に基づいている。」(同上 p120)「一般大衆が目標の意味をよく理解し、したがってそれを実現するように教育されていないならば、またその社会に殆ど完全に近いような経済力の平等がなければ、こうした目標は達成されないであろう。」(同上 p201)
- R.H.Tawney op.cit. p52
- ibid. p56-58
- ibid. p178
- ibid. p178-194
- ibid. p200
- トーニー「石炭産業の国有化」1918 『急進主義の伝統』所収
- 同上 p223-226
- ケインズは、投資家階級・企業家階級・労働者階級の三つに分け、投資家階級を否定した。伊東光晴『ケインズ』岩波新書 p18
- R.H.Tawney op.cit. p157
- ibid. p109-111
(3)トーニーの中等教育拡大論
トーニーが「中等教育をすべての者に」という政策を具体化するとき、まず問題にしなければならなかったことは、中等教育に進学することに対する障害は何であるのか、ということであった。
そして、彼は第一に、経済的要因をあげている。
現在のところ、きわめて多くの子供たちが彼等の両親の貧困のために、中等学校に入ることをまったく阻まれている。(1)
当時、補助金を政府から受けている中等学校は、全て定員の25%以上を無償としていたから、形式的にはテストに合格すれば、中等学校に入学できるしくみになっていた。しかし、それは実質的には機能していなかった。なによりも学校が少なく、充分な学力をもった者でも定員が足りなくて入学できなかった。(2) そして、受ければ合格する者でも、すぐ働かなければならないために、受験しない者がいる一方、合格の水準に達しない者でも授業料を払うことのできる者は、進学できるという実態であった。(3) それ故、トーニーは1905年に開かれた会議においても中等学校の無償を強く主張している。(4) 公立の中等学校は、その財政的基盤から明らかなように、人民の費用で支配階級を養成する機関であった。(5)
従って、「中等教育」への入学を制限するのは、支配層にとって当然のことであった。「教育経費に関する特別委員会」は授業料を値上げすることによって、中等学校への接近を制限しようという提案を行ったのである。(6) このような経済的障壁は、中等教育が支配層養成機関であることの具体的現れであったが、それにもかかわらず、20世紀に入って、純然たる支配階級の自己教育機関からは徐々に性格が変わってきていたといえる。(7)
しかし、中等学校はやはり依然として特権学校であり、労働者階級の子が入学することは困難であった。(8) マスクレイブによれば、1899年から1910年に生まれた子の中で、中産階級の子は27%が中等学校に進学したが、労働者の子は4%が進学したに過ぎない。(9)
全ての者に中等教育を受けさせるということを構想する場合、このような支配階級の学校という性格を変える必要があった。単に労働者の子どもが入ることができるということではすまない。トーニーはそれを「青年期の教育」を行う学校という性格を与えることで解決しようとした。
では、それはいかなるものか。
特定の階級や職業にとって固有のものではない諸能力を発達させ、また、社会における合理的で責任ある生活の条件であるが故に、後になっての特殊化にとって基礎となりうるものであるが、特定の職業にとってだけ役立つということを越えて拡大する価値を持つ諸関心を作りあげること(10)
当時フィッシャー法による18歳までの継続教育は、産業界の反対によって実質化できない状態になり、14歳までの義務就学が1921年教育法によってやっと実施された。1921年教育法は次のように規定した。
42条 子供に対し、読・書・算の有効な基礎的教育(efficient elementary instruction)をうけさせることは、5歳から14歳までの、あるいは、本法律の下に条例で定めた場合には、6歳から14歳までの全ての子供の親の義務である。
しかし、1921年法は15歳以上の継続教育については、義務的な規定を設けなかったし、雇用の制限についても年齢及び罰則を明記した禁止をしなかった。(11)事実、児童の雇用については、工場や商店はそれなしにはやっていけない状態であったと言われている。(12)また、1922年当時、7万名の学齢児童が半労半学であった。(13)
さて、このような1918年法、1921年法に対して、労働党は、1918年社会主義政党としての性格を明確にして以来、大部分の労働者には粗末な基礎教育を与えるだけの内容に対し、批判的姿勢を強めていた。(14)だから当然トーニーも複線型学校体系を批判する上で、フィッシャー法を前提として批判したのではなく、フィッシャー法も批判の対象であった。
1918年法は、そのあらゆる長所と共に一つの欠点をもっていたからである。それは、ほんとうにはその問題に正面から向かわなかったからである。つまり初等教育と中等教育の役割は何か、両者の関係はいかにあるべきか、という問題にである。(15)
フィッシャー法は就学義務のみを決めたのであって、その部分的実施を決めた1921年法は更に、その内容として「読・書・算」ということを表現していた。それ故、多くの者は14歳まで「基礎学校」に在学し、そこから就職するという形態になっていた。トーニ一はこれを「能力の無駄」と考える。
第一に、基礎学校の内容に関してである。それは、彼によれば、「『彼等とは別個の貧乏人たち』のために、宗教的、経済的、及び人道的な理由から設立されたもの」であった。(16)このような基礎教育に対する考えは一般的であった。(17)
第二に、発達段階に適合していない、ということである。当時の心理学に基づいて、彼は、11歳で発達段階を区分し、それ以後を「青年期」として設定する。青年期の者に、基礎教育を行うことを無駄と呼んだのである。
そこで、トーニーは、これを発達段階に即した教育として、次のような構想をたてる。
Ⅰ.初等(Primary) 11歳ないし12歳までの全ての子供たちのための学校 x
これを更に次のように分ける。
a.7歳までの全ての子供たちのための保育学校・幼児学校
b.7歳から12歳までの全ての子供たちのための予備学校
Ⅱ.中等(Secondary)12歳から16歳乃至18歳までの男女生徒のための学校
Ⅲ.高専、大学の形態を提供する学校(18)
そして、16歳までの全ての者が教育を受けることができるように、というものであった。(ただし、この本では、国家の力で義務として課すのか否か、という問題と、中等学校の「16歳から18歳まで」という表現は、一種の学校で、卒業が自由なのか、二種の学校をつくるのかどうか明瞭でない。)
従ってトーニーは、「個人のレベル」での利点と共に、社会にとっての利益という視点を提供していた。
は次のように言っている。
青年期の教育が枯渇することで、民族それ自体が不毛化する。(19)
それは、二つの点において考えられている。
第一に、義務就学を終えて、働きに出る者が、まだ十分に成熟していない産業界に投げ込まれている、という点である。その結果多くの青隼が、身体的道徳的な歪みにさらされている。
第二に、それ以上に重要なことは、優秀な者が「巨大な産業界の渦巻きの中に失われる」ということ、言い換えれば、社会を指導する力を持つ者を、中等教育を狭めることによって、人口の小部分から引き出さなければならないということである。(20)
つまり、中等教育を社会の指導層を選びだす機会として、彼は考えていた訳である。トーニーによれば、「社会組織には、明敏な指導者が必要であるが、その機会の平等が大切である。」(21)
ここで、トーニーは、国家社会の立場から、いかに有効に指導者を選ぶという発想にたっている。しかし、だからといって彼がケルシェンシュタイナーのように、社会認識の中から「階級」概念を排除して「指導者」と「被指導者」という概念でそれを置き換えたりしているのではない。又、竹内氏のようにエリート選抜論である、と規定することはできないと思われる。学校が引き受けるかどうかは別として、社会組織の理論として、「エリート選抜」の位置づけがない理論は、十分なものではない。
G.H.D.コールによると第一次大戦前の社会主義の中で、次のような論争があったとされている。
高いレベルの教育を全ての(少なくともついて行ける全ての)者に保障すべきか、特に才能のある者に保障するのか、という論争である。(22)確かに、後者に立つといわれているウェッブは、統一学校(Common School)に反対していた。ウェッブは「統一学校は、狂信としては良いだろうが、民主主義的な理念ではない」といって、多様な学校形態を主張している。(23)しかし、ウェッブが、このように主張したとき、「統一学校」とは、ドイツの第一次大戦前の統一学校の主張を意味していたのであり、「民主主義的な理念ではない」というウェッブの評価は必ずしも的外れではない。そして、当時の労働者の教育に対する技術教育の要求は「高いレベルの教育」によって意味するものに直結するものではなかった。中等学校が公立学校として組織されていなかったり、存在していたとしても極めて僅かであったりするとき、まず優秀な者を進学させよ、(24)という主張から始まることは自然なことであり、機会の拡大とともに「全ての者に」という主張に発展するのが要求の筋道である。「多様な形態」をウェッブが主張するとき、機会を優秀な者に限定する意図は見られない。この点でウェッブの主張は発展してきたとみることができる。(25)
むしろ、ナショナル・ミニマムの主張にみられるように、多元論を超える可能性をもっていたと考えられる。
<註>
- 卜一二一『全ての者に中等教育を』成田克矢訳 p10 R.H.Tawney "Secondary Education for all" p8
- Kandel "Educational Yearbook" 1924 サイモンは、フィッシャー法以前ロンドンではグラマースクールとセントラルスクールの定員が子供の20%しかなかったと指摘している。B.Simon "Intelligence, Psychology and Education" 1971 p212
- トーニー前掲 p75 R.H.Tawney op.cit. p71
- "Secondary Education for all ── North of England Conference" T.E.S.1925.1.17
- 1912-1913年において、イングランドの補助金支給中等学校の全収入の41%は授業料である。トーニー前掲 p84-85 R.H.Tawney op.cit p80
- 同上 p66 ibid. p63
- 同上 p64-65 ibid. p60-61 但しパブリックスクールは貴族に対しては、授業料を払えない場合免除にすることがあり、これは明瞭に身分制学校の残存といえよう。五十嵐は次のように書いている。「社会的に組織された教育費とは個別的な教育費の組織から発展した。私立学校の教育費は、個別的な教育費として納められる授業料を収入として組織されたものである。イギリスのパブリックスクールは典型的な社会的に組織された教育費である。社会的に組織された教育費はまだ個別的教育費を廃止するものではない、イギリスの名門パブリックスクールは高額の授業料によって階級的排他性を達成している。しかし、その反面ファンデショナー(foundationer 給費生)制度によって同階層の貧困者を共済することにおいて組織性を発揮している。」五十嵐顕『教育財政学講義』1978 p31
- トーニー前掲 p67 R.H.Tawney op.cit p64
- P.W.Musgrave "Society and Education in England since 1800" 1968 p97
- トーニー前掲 p32-33 R.H.Tawney op.cit p29
- Board of Education "Education Act 1921"
- "Labour Yearbook" 1925 p334
- P.Musgrave op.cit p98
- Simon "Education and the Labour Movement 1870-1920" p356-357
- トーニー前掲 p19
- R.H.Tawney "The British Labour Movement" p123
- Kandel "Comparative Education" p361
- トーニー前掲 p13-14 R.H.Tawney "Secondary Education for all" p10
- 同上 p73 ibid. p70
- 同上 p72-76
- R.H.Tawney "Equality" p106
- G.D.H.Cole 'Education and Politics: A Socialist View' in "Labour Yerabook" 1955 p50
- Sidney Webb "The neccessary Basis of Society" 1911 Fabian Tract No.159 これは1923年に再版されたものを使用した。
- J.W.Martin "The Worker's School Board Programm" 1894 Fabian Tract No.55 p18
- Barbara Drake "Some Problem of Education" 1922 Lilian A. Dawson "Co-operative Education" 等
- S.Webb op.cit p9 "The Difficulties of Individalisme" 1896 p5 しかし、その実現のために労働者、教師が政治的主体として活動することに積極的でなかったことはウェッブの弱点であった。Webb "The Teacher in Politics" 1918
(4)トーニーの中等教育多様性論
多元的社会主義に立つトーニーは、中等教育も多様なものとして構想する。そして、先述したように、多様性が直ちに不ヰ等に結びつくとは考えられなかった。
この点を更に検討するには、彼が中等学校は多様でなければならない、と主張したときの教育内容に対する考えを検討する必要がある。というのは、フイッシャー法では、初等中等の二元体系はそのまま残されたのであるが、教育庁自体は「中等教育」という言葉によって「12歳から16歳までの教育」という理解に近づいており、焦点はそこに求められる教育内容になっていたからである。(1)
トーニーは、現存する「中等学校」以外の学校として「初等技術学校(Junior technical school)」「昼間継続学校(Day continuation school)」「中央学校(Central school)」を検討しているが、基本はこれらの学校を中等学校に近づけていくことで、多様な中等学校を創り、16歳までを義務就学とする、ということである。(2) その際、トーニー自身は中等学校の直接的定義を与えておらず、教育庁の「中等学校規則」による教師・設備・学級と運動場の基準に合うことをあげているに過ぎない。(3) しかし、中央学校、初等技術学校を中間学校に変革しようとするケントの教育委員会の計画者の述べた「あらゆる場合にカリキュラムの基底は、英語・歴史・地理・数学・科学・工作(女子には家庭科)及び体育をもって構成されるであろう。」という表現に対し、外国語がないことをを除いて「その全ての本質的な点において中等カリキュラムである」と規定している。(4) 又、ロンドンの中央学校に関する計画書で、12,13歳の子供が「簿記・速記・タイプライティング」などの技能の熟練へと投げ込まれることを、中等教育として容認出来ないと書いている。(5)
中央学校は、事務員や技師、仕立て屋などになることを目標とし、平均以上の能力をもっているが、中等学校の奨学金に合格しなかった者を対象に設立されたものであり、会社や工場に有能な労働者を提供することを目的としていた。(6) しかし、トーニーはそのような「職業準備」を中等教育として認めず、特定の職業に固有でない内容を中等教育として認めた。カリキュラムとして入っている教科を比較してみると、次のようになる。
中等学校は、「書・英語・歴史・地理・ラテン語・数学・仏語・ギリシャ語・ドイツ語・化学・物理・美術・音楽・作業・商業・体育」であり、女子には家庭科がある。(7)
中央学校は、「英語・歴史・地理・仏語・数学・裁縫(女)・製図・測量・理科・美術・手作業・家政・商業・音楽・体育・競技・園芸・自治」となっている。(8)
ひとまず、トーニーの言う「中等教育」とは、語学を含めた歴史・地理・自然科学などいわゆる「一般教育」であり、実科を含まないことである、と考えておこう。
さて、ここで当時の労働団体がどのような教育要求をもっていたかをみておこう。トーニーの「中等教育を全ての者に」が労働党の政策として採用されたとはいえ、労働者の要求は統一されていたわけではないからである。
労働組合評議会(T.U.C.)は1906年「中等及び技術教育は、それを利用しようと思う者全てに地方当局によって用意されなければならない」と要求し、(9) 技術教育の要求が重視された。(10)トーニーは、こうした労働者の要求に応える構想を充分には、示していない。むしろ、ハドーレポートが実科的中等学校を提起したことの中に取り込まれていった。
労働者教育協会(W.E.A.)の教育制度に対する要求は「ハイウェイ(Highway)」という言葉で言い表されている。「ハイウェイ」とは「ラダー(Ladder)」を批判して出されたもので、教育を受けることのできる者全てに対して開かれた広い道ということであって、何らかの選抜テストが行われる限り、必然的に社会的条件によって不利な者が出る、ということに対する制度的配慮である。(11)それは、大学拡張運動と継続教育の発展の中で自覚されてきた。(12)
W.E.A.は1903年に設立され、人文的教育を主とする労働者の学習組織であって、学習形態に大学のチューター制を取り入れていた。(13)カリキュラムは、第一次大戦前、経済学・産業史を基本とし、更に進む者は哲学・文学をやり、まれに生物学が行われた。数学はめったに行われなかった。(14)マンスブリッジの「古典教育 ── ラテン語・ギリシア語が人文的教育に労働者を導くものとして労働者にとっても有利である。」という言葉がその事情をよく説明している。(15)後にトーニーによってまとめられたW.E.A.の原則は、まさしく人文的発想によっている。それは、(1)特殊な能力の養成ではなく、全ての者の手に届く所にあること、(2)技術的専門的でなく、一階級の独占であってもならない、(3)自分の経験・理想に基づかなければならない、というものであった。(16)学校制度については、トーニーの構想を全面的に取り入れていた。(17)
次にプレプスリーグ(Plebs League)についてみてみよう。
プレプスリーグはW.E.A.とは対抗関係にある階級教育論にたつ学習組織だが、公的な学校制度に対する要求を機関誌で見る限り出していない。このことは、当時のイギリスのマルクス主義的自己教育運動の弱点であった。(18)
1924年、プレプスリーグは新しい憲章を決め、次のように目的を定めた。
宣伝と教育によって、賃金奴隷をなくし、労働者の階級意識を発展・増大させること(19)
これは、W.E.A.の目的が労働者の教育でなく、中間層のための教育であるという批判であった。(20)
ホレビンによれば、歴史を中心として、労働組合史・近世資本主義発達、更に経済学・経済地理・心理学などがカリキュラムとして組まれていた。労働者の教育は階級闘争に役立つことに向けられるべきであり、W.E.A.の「自由な研究」を批判するものであった。(21)しかし、初等中等教育については、国家によって行われることを是認し、内容上の批判も加えなかった。(22)ハホレビンは次のように書いている。
如何なる種類の教育が労働者にとって有利であるかという問題は起こらなかった、何となれば異なれる種類、及び価値の教育の可能性が語られなかったからである。教育はそれ自体においてよいものであった。(23)
一方、フェビアン協会では、要求の定式化はされなかったが、教育についての討論は活発に行われていた。フェビアンニュースに紹介された講義によってまとめると次のようになる。
1.大学教育の重視(24)
2.技術教育の要求(25)
3.中等学校の義務化(26)
第三の要求からみれば、フェビアン協会での議論が必ずしもエリート教育論に留まっていたのではなく、むしろ第一次大戦やフィッシャー法を経過する中で、統一学校の理念への積極的評価が出てきたことがわかる。更に16歳までの中等学校義務化・大学の拡充・成人教育の拡大によって、W.E.A.とプレプスり一グの溝を埋める努力が追求されていたことも見逃すべきではない。(27)
以上のことからわかるように、労働者の要求は、労働教育の内容をめぐっては人文教育を求めるもの、技術教育を求めるもの、階級意識の教育を求めるものにに対立していたが、それらは中等教育の内容の変革に結びついた上での対立ではなかった。中等学校の教育はあるがままの内容が当然視されていたといえよう。
トーニーに戻ろう。
卜一ニ一は20世紀に入り、民衆の教育に対する要求が高まったと認識する。その徴候は、中等教育への要求、W.E.A.にみられる成人教育の活動の増大、教育政策の遅滞に対する抗議(フィッシャー法のこと)、そして労働運動での教育綱領の制定にみられる。(28)
W.E.A.は経済学・社会科学が1920年代を通じてカリキュラムの中心であったが、生物・文学・美術なども次第に加わった。トーニー自身によれば、心理学・哲学・音楽なども加えられてはいるが、こうした多彩なクラスができることを彼は歓迎した。(29)中等教育をトーニーは「完成教育」として位置付けていること、W.E.A.で学んでいる労働者は初等教育を受けただけの肉体労働者が多いことから、(30)次のトーニーの言葉は中等教育の内容上の原則を表現しているとみることができるだろう。
我々の第一の使命は ── 教育上の特権を受けられない多数者に向けられたものである。これらの人々は15歳頃に学校教育を終えるが、彼等自身の幸福のためにも彼等が生きている社会を改造する助けとしても、人文教育を必要としているのである。(31)
こうした人文教育を中心とするトーニーの考えは、彼自身の教育概念によっているのである。
多くの文明において、教育と労働は互いに織りなしていた。あるいは同一の過程であった。しかし、工業社会においては、個人の能力を発達させることと、経済の一線がひかれる。(32)
この教育認識が、職業準備教育を否定し、ひいては「労働と教育の結合」の軽視へと到らしめたのである。
<註>
- "What is a secondary school?" T.E.S.1919.10.16
- トーニー前掲 p115 R.H.Tawney op.cit p107
- 同上 p119
- 同上 p113 ibid. p106
- 同上 p116
- Haden Guest "The New Education ── A Critical Presentation of the Education scheme of the London Education Authority" 1920 p97
- Kandel op.cit. p661
- ibid. p392
- 堀尾輝久『現代教育の思想と構造』 p96-97
- 10しかし、このことを過大評価することはできない。1918年の要求では技術教育については触れられていない。B.C.Reports "The Trade Union Congress 1868-1921" 1958 p390-391 富沢賢治『労働と国家』1980 p113
- 'Higyway or Obstacle Road' in "Higyway" 1922.12 p35
- Albert Mansbrige "An Adeventure in Working-Class Education ── Being the story of the Worker's Educational Association 1903-1915" 1920 p31
- 'Economy and the Education Act 1918 Manifest bye the W.E.A."
- Mansbridge op.cit p42
- 'The future of the classic ── Deputation to Mr.Fisher' T.E.S.1917.5.10
- R.H.Tawney 'The Future of the Workers' Educational Association' in "Highway" 1928-29 p3-4
- Arther Greenwood 'Secondary Education for all' in "Highway" 1924 p61-63
- E.R From 'Educating Marxist ── Study of the Early Days of the Plebs League in the North West' in "Marxims Today" 1968 p309
- "Plebs" vol.16 1924 p202
- J.P.&W.ホレビン『無産階級教育論』 p98
- 同上 p92
- 同上 p112
- 同上 p69
- "Fabian News" 1913.11 ウエッブの発言
- ibid. 1915.12, 1917.3 ティベリー(Tibbery)の発言
- ibid. 1920.4 ティベリーの発言
- ibid. 1926.5 R.Peers の発言
- R.H.Tawney "The British Labour Movement" p120
- Harrison op.cit p285
- トーニー『一急進主義の伝統』 p109, 120
- 同上 p109-110
- R.H.Tawney "Some Thoughts of economics of public education" 1938 p7
(5)ゾレッティとザイデルの統一学校論
<ゾレッテイ>
ここでフランスの社会党の教育方面のイデオローグであり、CGTの教育担当でもあったゾレッティについて若干触れておこう。
ゾレッティはまず、「公正」を求める。偶然性や反人間的なこと、例えば帝国主義、植民地主義、軍国主義などは拒否する。(1) したがって、「特権」による獲得ではない筋道によって、文化を高めていくことがゾレッテイの改革の主眼になる。(2)
ところで教育は、社会的なことがらであると同時に、個人の権利でもある。社会の要求を認めることは、社会的生産の必要性にあわせて教育を組織することである。しかし、このことは国民共通の教育を与えつつ、国民を選別・差別することに他ならない。(3) この避けることのできない「選抜」を、ゾレッティはできるだけ遅くすべきという。(4)
11歳から14歳を指導期として、この間に十分個人の能力・適性をみて進路を決めていくということである。ゾレッティの改革構想は図のようになっている。(5)
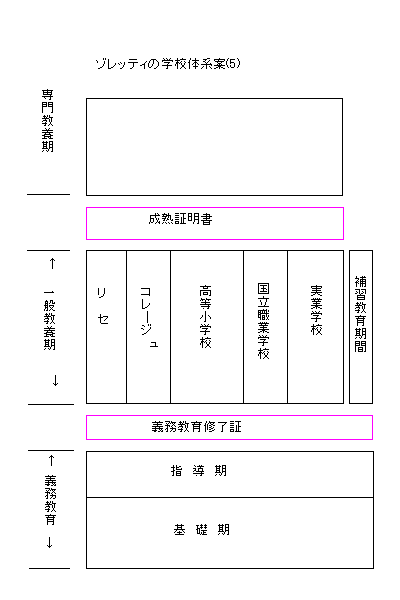
フランス社会党の特徴は、第一部でみたように、「教育の国家独占」にあった。これは徹底した「世俗教育」を求めることであったが、制度論としては「私学の自由」を認めない議論である(6)
しかし、ゾレッティはそうした「国家独占」に反対である。
社会党は階級や国家に反対しており、国家による教育独占に安住することはできない。(7)
ゾレッティは社会主義国家による独占についても、ロシア革命の例を出して批判する。めざすのは「個人の真の自由」である。(8)
しかし、まずは宗教団体から、学校が解放されなければならないため、国家による教育が承認される。そこで教えられるべき教養・文化の問題になる。
文化の階級性の問題は、大戦間の社会主義者を悩ませた、きわめて大きな問題であった。(9)
社会主義リアリズム論によるブルジョア的文化の退廃性批判という側面。
文化を創造・享受するためには、豊かな自由時間が必要であるが、実際上労働者にはそれは許されていないこと。
文化は政治や経済と異なって、必ずしも「階級的」なものではない、という意見。
様々な意見の中で、またソビエトでの積極的及び否定的現実の影響の下で、論議がなされた。ゾレッティ自身完全な解答を与えてはいない。ゾレッティが主張することは、第一に、労働者にはより多くの「自由時間・余暇」が必要だということ、(10)第二に、エリートの文化のみでは、その特権的性格による否定的影響を免れないということである。(11)エリート文化への恐れは、選抜の制度化によって労働者の優秀な者が、エリートの道を歩み、エリート文化を身につけると、人格・価値観まで労働者を捨ててしまうのではないかということであった。
<註>
- Ludovic Zoretti "L'Éducation Nationale et le Mouvement Ouvrier en France" p6 この書物は発行日が書いていないが、個別論文が書かれたのは、ほとんどが1920年代前半である。
- ibid. p12
- ibid. p12
- ibid. p36
- 夏目達也「フランス統一学校論における『進路指導期』の形成過程」名古屋大学教育学部紀要1984 p199 より
- 大坂治は、nationalisation を「国民化」と訳すことを提起し、統一学校運動が求めていたのは、「教育の国家独占」ではなく、「教育の国民化」であったとするが、しかし、monopole という語が使用されており、「私学の廃止」が要求されている限り、翻訳語がどうあれ、内容的に「教育の国家独占」であるというのが適切である。大坂治前掲プリント参照
- Zoretti ibid. p26
- ibid. p29-30
- J.ベルナール『フランス共産党と作家・知識人 1920-1930年代の政治と文学』杉村昌明訳 拓殖書房参照
- Zoretti ibid. p7
- ibid. p50
<ザイデル>
スイスの社会民主主義者ロバート・ザイデルの論理を見ておきたい。
ザイデルはSPDとも関係をもち、ドイツ革命の時にはUSPDに参加していた。先述したように、ノールによってマルクス主義の労働教育の理論家として高く評価されていた。しかし、そのマルクス主義労働教育の理解は、クルプスカヤのそれとは大いに異なっている。
ザイデルの教育学上の問題意識は二つある。
第一に、教育の目的を明らかにすること。
第二に、公民教育の位置づけを明確にすることである。教育の目的からみていく。
人間は個々の専門的能力ではなく、全体的な関連・視野を持つことが大切であり(1) それは人間性の素質と要請、人間社会の目的と必然性と調和しなければならない。(2) その要締は労働教育実践と、階級的に教育目的を区別しない統一学校である。(3)
我々は社会的に有用で、経済的に不可欠な手労働、道具の技術的な習熟性、そして職業的な労働能力の欠けることのない教育目的を必要としている。何故なら、それは労働に依存する民主的な共同体の部分(Glied)としての人間の徳性と完全性の基礎だからである。(4)
では如何なることが個々の人間に求められるのか。
ザイデルは人間の素質として以下の5点をあげる。
1.肉体的一精神的存在
2.社会的一国家的存在
3.技術的一芸術的存在
4.精神的一思考的存在
5.感覚的一倫理的存在(5)
以上の領域を無視することなく、調和して高めていくことが普遍的人間の陶冶(allgemeine-menschliche Bildung)である。つまり、ザイデルは調和的陶冶(Harmonische Bildung)を基礎概念とし、その方法として労働教育を位置づける。
では何故労働教育が調和的教育の基礎になるのか。
手の作業は精神の発達に有用であり、認識能力を高めるからである。(6) つまり単なる労働能力だけでなく、職業・芸術的能力、そして協力という道徳的な機能もある。(7)
ザイデルはこうした理念を述べながら、当然出て来る疑問、社会は階級的に構成されており、そこからの強力な教育への要請、教育そのものも階層的に構成するという要請に対して、どのように対処するかという問題には、答えていない。あくまでも教育思想史的に調和的人間の正当性を主張している。
第二の課題を検討しておこう。
ザイデルは公民教育について、繰り返し問題にしている。その問題の性格は二つある。社会民主主義者の間で批判的に扱われることの多かった公民教育を積極的に位置づけるという意識と、国家市民(Staatsbürger)としての公民と、世界市民(Weltbürger)としての公民の関係である。
国家なしの国際主義はユートピアであるから、国家市民の形成は当然であり、それは国家の部分(Glied)としての性格を身につけるのである。(8) しかし、世界市民としての教育も不可欠であり、それは反国民でも反国家でもない。(9) また世界市民としての公民教育こそ、ショーヴィニズムヘの対策となる。(10)
ではどちらが基本なのか。ザイデルは世界市民としての教育が基本であると主張する。(11)
しかし、ここでも当時のロシア革命によって引き起こされた、資本主義対社会主義の対抗という状況は、それ程考慮されてはいない。むしろスイスという地域性に依拠する論理とも言うべきものであった。
ただ後にスターリン体制の下で、必ずしも十分な検討を経ずして否定された「調和的人間像」の主張、そして世界市民を基本とする公民教育を構想しようとしたこと、手の労働の認識上の意味を考察したことは、銘記されてよいと考える。(12)
<註>
- Robert Seidel "Das Ziel der Erziehung vom Standpunkt der Sozial Pägogik" 1915 s7
- a.a.O. s10
- a.a.O. s11, 42
- a.a.O. s45
- a.a.O. s47
- R. Seidel "Die Handarbeit der Grund und Eckstein der haumonischen Bildung und Erziehung" 1911 s24
- a.a.O. s31-36
- R. Seidel "Sozialdemokratie und Staatbürgerliche Erziehung oder Staatsbürger, Weltbürger und Mensch" 1917 s31-34
- a.a.O. s157
- a.a.O. s30
- R. Seidel "Erziehung für Vaterland oder für die Menschheit?" 1919 s17
- レーニンはザイデルを社会愛国主義者として非難しているが、ここではザイデルの政治的姿勢は十分検討する材料がない。かれの教育学の著作に現れた理念を問題にした。ただザイデルの論理が「理念的」色彩が濃いことも否定しがたい。『レーニン全集23』 p255 参照
(6)試験制度について
中等学校は多様でなければならない、というトーニーの主張は、以上見たように教育内容的にみれば、形式的主張に過ぎなかった。物的教育条件を満たせば、内容は自由でなければならないという消極的規定であった。
さて多様性と平等が両立しうる、という主張からみれば、多様な中等学校が平等でありうるか否かは、その入試制度に決定的に左右される。イギリスで知能テストが公的な試験制度に取り入れられるに到ったのは、第一次大戦後の改革の一環としてであった。そして、それは「選抜機構」としての中等教育の性格をよく表しているのであって、知能テストを中心とする試験制度及びその基底になっている「能力観」をトーニーとの関連で検討することが不可欠である。
20世紀に入り、心理学が知能を問題にしはじめる。(1) ビネーから始まり、イギリスのスピアマン、アメリカのソーンダイクと広がる中で、「知能論」は学校制度、特に中等学校と密接な繋がりを持つに到った。特にイギリスでは、19世紀からの「Payment by result」及び20世紀に入ってからの無償席制度によって、テストが広く行われていた。中等教育拡大の動きの中で、1920年代、教育庁(Board of Educaition)は諮問委員会(Consultative Committee ハドー委員会)に、全国的な教育制度の中での「心理学テスト」について諮問を行ない、1924年に報告が出された。(2) トーニーはこの委員会の委員であった。
1924年レポートは、18世紀の能力心理学は形而上学的で、それが次第に科学的になってきたのは、数学的手法を取り入れた19世紀以降のことであると書いているが、(3) 特に20世紀に入ってからのドイツのシュテルンの「差異心理学(Differentielle Psychologie)」と、イギリスのスピアマンの「先天的、一般的能力(innborm general ability)」の学説を大きく取り上げ、それらを公的に確認した。
当時、イギリスにおいては、ビネーは既に障害児の発見法の開拓者としてではなく、精神発達の Scale の創始者として評価されていた。(4) レポートが承認した中心的理論は、第一に、生涯を通じて、不変の「精神的要素(Mental factor)つまり「知能(intelligence)」が存在すること。
第二に、それを教育によって獲得された能力とは区別して発見し、計測することが可能である、という二点である。(5)
そして、
1.知能テスト(一般的知能)
2.標準テスト
3.職業テスト
4.特殊精神テスト
5.体力テスト
6.性格テスト
が、公的教育制度の中で利用されるべきことが提示された。(6)
こうした心理学は、一面では能力は階級的に規定されているという支配階級の意識を打ち砕くのに有効であったといえるだろう。
トーニーは次のような「ある特別市の教育長の言葉」を引用している。
中等学校への奨学金をえようとする基礎学校からの応募者を9年間試験してきた経験の結果は、わたくしをして、候補者の40%から50%の者が疑いなく、中等学校教育の課程から充分利益を受けるだろうとの結論に到達せしめた。(7)
能力の問題は、身分・階級から離れて、個人の問題になった。1924年レポートは、経済的・社会的条件を捨象して、先天的な能力を計りうると結論した。
なるほど「先天的能力」の存在をいうことは、それ自体は決定的に重要なことではない。「遺伝」の存在は、かなり確かめられていたし、又、今日では遺伝子の存在すら確認されるに到っている。逆説的にいえば、それ故に能力が先天的に決まっているという能力観は、科学的・技術的発展の中で、支配階級の学問によっても修正されざるをえなくなるのであろう。そこでは、能力は「獲得された力量(attainment)」になる。
だから、1924年レポートの問題、階級的性格は知能が「計りうる」とされたことと、集団テストを選抜の手段として採用したことにあるのである。(8) かくて「中等学校はテストによって支配されている」と中等学校教師が批判せざるをえない状況になっていった。(9) しかも重要なことは、このレポートがスピアマンの「一般能力」を是認していたことであって、中心的なテストが「一般能力」を測定するということになったことである。(10)
ここから、各段階の「知能」の持ち主が、一定の割合で存在している、という「理論」に到達するのは、さして遠いことではない。しかも、「知能」は、精神的要素であるとされ、それを計るテストの内容は、明らかに「中産階級」以上の者に有利なものになっていた。(11)しかし、これはそもそも「知能論」が支配層を選びだす、という階級的性格・目的をもって登場した必然的帰結であるといえよう。事実、当時の mental test 論は、ビネーの下位集団重視から正規分布を前提とする上位集団の重視へと重点を移行させていた。 (12)
トーニーの「中等教育を全ての者に」は1922年であるから、当然この書物は検討の対象となっていない。彼がこのハドー委員会のメンバーであったことをもって、積極的に支持しているとは速断できないであろう。
彼は中等教育のみならず「高等教育も全ての者に」と考えていたし、W.E.A.でそれを彼なりに実践していた。つまり、彼は全ての者が一生学び続けることを前提にして、その一つの部分として「大学」を考えていたのであり、それ故、大学を一部の知的職業につく者に限定することを批判した。トーニーによれば、W.E.A.で学んでいる肉体労働者が学術論文としても通用するりっぱな論文を書くことがまれでない。それを根拠として、彼は普通の者が高等教育を受けることができると考えるのである。(13)卜一二一は能力の先天性論者ではなく、発達的視点に立っていたといえる。
<註>
- 心理学が第一次大戦後教育界に入ってきており、一定の問題状況を生んでいた。'Special Report' T.E.S.1919.1.9
- Board of Education "Report of the Consultative Committee on Psychological Tests of Educable Capacity and their possible Use in the public education system" 1924 pxi (以下 Reports on Tests と略)
- Reports on Tests p1-2
- Philip Boswood Ballard "Mental Tests" 1920 p13
- Reports on Tests p74
- ibid. p136
- トーニー『すべての者に中等教育を』 p71 R.H.Tawney "Secondary Education for all" p67
- Reports on Tests p87-93 1919年から奨学金テストに知能テストが取り入れられた。
- 'Intelligence versus Tests' T.E.S.1925.11.14
- ibid.
- Simon "Intelligence, Psychology and Education" p49
- Ballard op.cit. p90
- トーニー『急進主義の伝統』
(7)まとめ
トーニーの論は、労働党やT.U.C.が国家と癒着していく中で、基本的には同一基盤にありながら、最大限労働者の権利内容を体系化したものである。階級協調性、労働と教育の結合の軽視、入試制度の弊害への無自覚等、トーニーの理論には明確な欠点がある。しかし、資本の論理そのものである人的能力論に立つとみることはできない。
国家独占資本主義が実質的な不平等を一方で是認することで社会法を成立させるが、一方ではイデオロギーとしての「平等論」を成立させる。トーニーの平等論は、この条件的平等を究極の社会原理とする平等論ではない。自治の主体として国民を形成する視点が、教育論として構想されるか否かが一つの分岐点になる。トーニーは平等を実質化させる不可欠の条件として教育の拡大を提起した。彼が教育を「解放(矢川)」の道筋で理解しなかったとはいえ、彼の平等論は批判的に継承すべきものであろう。
では、トーニーの中等教育の多様性はどのように理解されるべきであろうか。
トーニーの主張は何よりも、民主社会は多様性を保障すべきだという原理に基づいている。更に、市民社会における私的団体の成長が、国家介入の不充分な段階に即応して「多様な自治」の成立を可能なように思わせた。したがって、地方的・階層的に様々な内容をもった教育が原理として主張されたのである。ハドーレポートが多様な中等学校 ── 特に実科的中等学校を提起したとき、その産業との結合は、地方レベルで考えられていた。トーニーとハドーレポートの両立の秘密はここにあったが、その方向は逆だったのである。しかし、フィッシャー法以降徐々に国家の介入が進み、又1920年代後半から、重化学工業からの教育への提言が強化されるに従って、この地方的自治にい依拠する構想の実現は難しくなっていく。ラスキのマルクス主義への発展に見られるように、多元的社会主義自体が批判されることになった。
しかし、国家介入がいわば極限まで達している現在、トーニーの理論がもっていた「多様性論」の意味を、新たな形態で発展させる視角は必要だと思われる。