第五章 階級協調の統一学校論
第一節 ドイツ社会民主党と統一学校運動
── H.シュルツを中心として
(1)はじめに
SPDはドイツにおける社会主義政党として、初めて社会主義の教育政策を志向した。しかもその当初から学校制度の統一性が掲げられ、統一学校運動の中心勢力のひとつであった。(1) 統一学校運動の ── 要求の底辺の広さと、あまりに多様な意見とによって成功したとは言い難かったとはいえ ── 一つのピークをなした1920年6月の全国学校会議の主催者の一人が、SPDの教育政策の中心であったH.シュルツ(Heinrich Schulz)であったことにそれは明確に現れている。しかしながら、ワイマール憲法制定時におけるSPDは、中央党(Zentrum)との妥協はもとより、SPD内部からも統一学校の原則を裏切った、として批判されてきた。(2) この批判の妥当性はワイマール憲法の制定過程や、その後の全国学校法案の動向をみる限り、疑う余地がない。
しかし、SPDの教育政策を分析する際には、とりわけ「政治と教育」「理念と現実」という問題の検討が必要であろう。SPDはとにかくも、ワイマールを支えた政党であった。しかし、その基盤は強固ではなく、単独政権であったことはない。それ故、「妥協」が常に強いられたのである。そうした中で、何を優先するのか、どのようにして原則を貫くのか、SPDはそうした問題に常に直面していた。
したがって、SPDは社会主義原則を裏切ったという側面のみで、片づけられるべきものではないだろう。P.エストライヒ(Paul Oestreich)など内部からの批判が運動として存在したこと、SPDは選挙等でみる限り、国民の支持を広く受けていること、他方KPDの統一学校政策自体もそれほど首尾一貫したものではなかったことである。
更に、「シュルツの統一学校論は、社会主義社会にならなければ実現不可能な案である。」というザウペの批判もあった。この限りでは、シュルツは」般的には原則的な社会主義者と考えられていたのである。(3)
そもそもSPDは三つの潮流に分離しており、「社会主義」とは何かについての統一的イメージ自体が、当時既に困難になっていた。
そして、一般的な意味での社会主義と教育の社会主義的性格とは、また常に意識されてトータルに考察されたわけではない。ヒルファディンクは社会化によって組織された経済を、直接に自己管理団体の支配下に置くことによって、社会主義を実現できると考えた。ヒルファデインクにとって、自己管理団体による自己管理が社会主義であった。国家を領域とみなすギルド社会主義にヒルファディンクは共鳴した。(4) しかし、「社会化」自体あいまいな概念だったことは、周知のことであり、一方で所有を中核と考える人々がいたことはいうまでもない。
だが教育政策に関しては、SPDの内部に対立があったことは事実であるが、原則についてではなく、実行の様式にあった。
<註>
- Tews "Sozialdemokratie und öffentliches Bildungswesen" 1921
- 後述する「徹底的学校改革者同盟(Der Bund entscheidener Schulreformer)」の中心人物は多くSPD党員であった。
- Saupe a.a.O. s24
- 保住敏彦『ヒルファデインクの経済理論』梓出版1984.11 p242
(2)SPDの教育政策の基本的性質
<SPD教育政策の形成>
さて、SPDの教育政策は原則として、第一次大戦前に形成されていたので、統一学校運動の前史の一部として、大戦前のSPDの教育政策を概観しておこう。
SPDが全ドイツ労働者協会(ラサール派)と社会民主労働者党(アイゼナッハ派)が合同して1875年ゴータにおいて「ドイツ社会主義労働者党(Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands)」として成立した時制定されたのは、周知のとおり「ゴータ綱領」と呼ばれるものである。
その革案は教育について次のように規定していた。
国家による一般的な平等な国民教育。全般的就学義務。無料教育。学間の自由。信教の自由(1)
これに対してマルクスは次のように批判した。
1.平等な国民教育の空想性、不明確性
2.無料教育は人民の負担による有産階級の教育になること
3.工業学校を国民学校に結びつけること
4.国家による国民教育は不適当で、逆に国民による国家の荒療治の教育が必要である。(2)
一般にゴータ綱領はラサール派との合同という政治的配慮が優先したために、理論的な掘り下げがなされておらず、エルフルト網領に至ってはじめて、行動綱領を除けば、マルクス主義の理論が取り入れられた、とされている。(3)
しかし、エルフルト綱領にしても行動綱領の一つである教育政策はほとんど前進するところがなかった。
第七項で「学校の非宗教化。公立小学校への義務就学。公立小学校における無料教育、及び学用品と食事の無料支給。学力優秀で学業継続の資格ありと認められた中等教育機関における男女学生に対する同様の措置」と規定された。(4)
これに対してエンゲルスが加えた批判は次の点である。
第一に、「万人の平等の権利のために」という表現を、「万人の平等の権利と平等の義務のために」と改めるべきであるとしていること。(5)
第二に、宗教に関する叙述をエンゲルスは次のように改めている。
教会と国家の完全な分離。いっさいの宗教団体は例外なく、国家によって私的組合として取り扱われる。宗教団体は公共資金からの補助をいっさい失い、そして公立学校に対する影響をいっさい失う。(6)
そしてエンゲルスは、かっこして、「(まさか、それらの団体が自己資金で自分の学校を設立し、そこで自分たちのたわごとを教えるのまで、禁止するわけにはいかないであろう。)」と付け加えている。(7) このことは社会主義の教育要求の中に、頻繁にでてくる「教育の国家独占」「私立学校の禁止」ということと関連して、厳密な検討が必要であろう。
これらの項目が、とりたててブルジョア民主主義政党の要求と区別されるような、社会主義的内容をもっているとは認めがたい。(8) このことはSPD指導部も感じていたので、1906年のマンハイム党大会において、教育政策を重点的に取り上げ、H.シュルツとK.ツェトキン(Clara Zektin)が報告を行った。そして、この党大会で世俗性(Weltlichkeit)、統一性(Einheitlichkeit)、無償性(Entgeldlichkeit)」という三つの原則が定式化され、ワイマール期のSPDのみならず、USPD,KPDの教育政策の土台となった。
第一次世界大戦後、ゲルリッツ綱領やハイデルベルク綱領で、階級政党から国民政党への方針転換するが、少なくとも教育政策の面では、そのような原則の転換はなされていない。(9)
<註>
- 望月清司訳『マルクスゴータ綱領批判』岩波文庫に資料として革案と成文が訳出されている。
- 『マルクス・エンゲルス全集19』大月書店 p30-31
- 安世舟『ドイツ社会民主党史序説』御茶の水書房 1973 p83-84 エンゲルスの評価も基本的に同じであるといってよい。
- 望月訳 前掲 p189 エンゲルスは草案に対する宗教団体の影響力の排除を要求しているのみである。『マルクス・エンゲルス全集22』 p244 (望月は「中等教育機関」を「高等教育機関」と訳しているが、höheren Bildungsanstalten で「中等教育機関」を示しているので、訳語を変えてある。
テウスによれば、エルフルト網領の中等教育機関に対する規定は原案にはなかったものである。Tews "Sozialdemokratie und öffentliches Bildungswesen" 1921 Pägogisches Magazin Heft9 s18
マルクス・エンゲルス全集の資料による綱領草案は次のようになっている。
5.教会及び宗教の目的のための公共資金の支出の全廃。教会団体及ぴ宗教団体は私的結社とみなされるものとする。
6.学校の非宗教性。公立国民学校への義務就学。一切の公立教育施設における無料教育と教材の無料支給。
7.全国民に対する軍事教育。常備軍にかえるに民兵をもってする。労働者保護のための施策
1 b.14歳以下の児童の商工業労働の禁止。
『マルクス・エンゲルス全集22』大月書店 p301 これはエンゲルスが批判した際の革案であり、デウスのいうように、中等学校に関する規定はない。したがって、エンゲルスのコメントはない。優秀な者が進学するということは、財産のある者が進学するより、公正であろうが、しかし、労働者にとって、必ずしも階級的利益になるものではない。進学できた個人にとっては、無条件で利益であろうが、そうして進学した者はほぼ確実に「労働者階級」から脱出するからである。この問題は社会主義政党にとって、共通の、かつ深刻な問題であった。逆に言えば、「能力による進学」は資本主義の支配にとって、最も効果的な労働者支配の方法である。
- 同上 p238
- 同上 p244
- 同上 p244
- W.ヴィトヴェルはエルフルト網領に至るまでのSPDの教育政策を、世俗性・国家性・統一性・無償性と要約し、これは実践的にはあいまいであり、そのため11月革命での矛盾した行動が生まれた、と評価している。Wolfgang W. Wittwer "Die sozaildemokratische Schulpolitik in der Weimarer Republik" 1980 s15-19
- このことは、逆に言えば、世俗性・統一性・無償性・共学というような、伝統的なSPDの政策は、党内で合意があったが、それ以外では合意が形成されにくかったということでもある。W. Wittwer a.a.O. s59
ヴィトベルによれば、SPD内部には教育政策について、三つの潮流があった。社会主義的な政策をめざすレーベンシュタイン、現実派のシュルツ、実践重視のパウルゼンなどである。a.a.O. s59-60 やはり理念の対立とはいいがたい。
<シュルツのマルクス主義受容>
周知のように、第一次大戦前のSPDは多数派(右派)、中央派、左派の三つの潮流に分離していたが、教育政策に関していえば、それに対応する三つの潮流が形成されていたわけではなく、まだ未分化な理論状況であったといってよいであろう。後年対立関係になるH.シュルツとツェトキンが ── 見解に相違があるとはいえ ── とにかく協力してマンハイム党大会への報告が準備されていったことが、それを示している。しかし、ワイマール期のSPDの教育政策の中心であった、H.シュルツの理論形成が第一次大戦まえに行われ、それがワイマール期にも維持されたことにみられるように、(1) 多数派社会民主党の教育政策というべきものが形成され始めたことも事実である。そうした政策活動の中心がH.シュルツであった。彼は第一次大戦前の社会民主党の理論機関誌「ノイエツァイト(Neue Zeit)」の教育分野の大半を執筆し、(2) SPDの教育研究所のメンバーであり、1906年のマンハイム党大会の主報告者であった。第一次大戦後についても、憲法制定会議における教育条項の担当者であり、(3) 1920年の全国学校会議を主催し、1921年の全国学校法の提案者であった。したがってH.シュルツを中心としてSPDの教育政策の論理を考察することが妥当であろう。
ワイマール期のSPDの政党としての姿勢をみる上で、第一次大戦に対して、及び11月革命に対しての基本的態度を前提として考えることは、ほぼ一致した見方となっているので、まずこの点を確認しておこう。
H.シュルツは第一次大戦について、次のように書いている。
戦争中『変化する労働要請に対する人間の完全な可動性(Disponibilität)』が完全な必然性となった。ドイツ兵は全く疎遠で不慣れな新しい課題をやりとげるために、日夜可動的でなければならなくなった。(4)
これは、マルクスの学説から学んで教育の課題を析出しようとした論文で、H.シュルツは『資本論』の大工業制下の全面的可動性を、必然性という視点で、第一次大戦に適用したのである。しかし、現実の資本制大工業から「大工場制」という媒介概念を経て、全面的可動性を導いたマルクスに対し、H.シュルツは現実の第一次大戦から導いており、それ故H.シュルツの論理は大戦そのものの擁護になっていた。H.シュルツは改革教育学の労働教育論を高く評価する一方、人間の労働が民族の資本であって、これによってフランスの植民政策に対抗しなければならない、と主張した。(5) H.シュルツの帝国主義戦争の擁護は、自覚的なものであった。
革命についてはどうだろうか。
ワイマール共和国の初代大統領でSPDの党首エ一ベルトは「私は革命を欲しません、いや私はそれを罪悪のように憎んでいます」と述べたが、(6) H.シュルツも「我々社会民主主義者は革命を欲しなかった。我々は革命という暴力なしに、ドイツ国民にとって、自由な道がつくられることを欲したのだ。」と憲法制定会議で発言している。(7) 革命によって旧い勢力が力を失い、教育改革の運動が進展したことは認めるが、むしろ改革を可能にしたのは戦争であり、革命は予期せずに起こったのだ、という認識であった。(8)
<註>
- H.シュルツの主著は "Schulreform der Sozialdemokratie" 1911 であるが、これは1919年に加筆され、再版されている。本論文で使用したのは再版の方である。
- 特に1905年から1913年のNeue Zeit誌上での活躍がめだち、その教育関係論文の半分以上はH.シュルツの執筆であると思われる。ただし教育論文の数そのものは極めて少なかった。
- K. Günter "Geschichte der Erziehung" 1966 s453
- Heinrich Schulz 'Karl Marx und die Pägogik' in "Die Glocke" Jg4 1918 s158
- Heinrich Schulz 'Förderung oder Verhinderung von Geburten' in "Die Glocke"1918 s597
- 村瀬興雄『ドイツ現代史』東大出版会 p223
- Johanes Schenk 'Zur politischen und pägogischen Position von Heinrich Schulz in der Novemberrevolution 1918' in "Jahrbuch für Erziehung und Schulgeschichte" Jg 4 1964 s142
- Heinrich Schulz "Schulreform der Sozialdemokratie" s229-239 もっともこのことは、SPDにとっては全く正しい事実であった。
<SPDと宗教教授>
このような戦争・革命観に立ってワイマール憲法制定時に中央党と妥協し、自らの統一学校の主張を裏切った、と強く批判されたのであるが、この妥協は第一に、何故いかなる理由でSPDは統一学校を主張し、第二に、何故それを「妥協」によって捨てたのか、という二重の究明課題を提起している。
まず、H.シュルツは資本主義的教育を、宗教的・倫理的教育であると規定し、資本家は教育のない(ungelehrte)労働者を好んでいるという現実認識を土台にして、資本主義教育の階級性を批判している。(1) 確かに、個々の産業においては、手腕(Tüchtigkeit)や遂行能力(Leistungsfähigkeit)が必要であろうが、大部分の労働者にとって、そのための職業教育は求められておらず、それ故婦人・児童・外国人が好まれるのである。(2) それでもアメリカやフランスでは国民教育がより良い状態にあるが、ドイツではユンカーの反動支配と結びついている。(3) したがって社会主義教育の第一の課題は階級性の除去にある。(4) H.シュルツによれば、宗教教授こそ、支配の手段として大いに利用されており、国民学校は大衆を「敬愛なる子羊(ffrommen Schäflein)」に作りあげる機能を持っている。(5) だから、教育の階級性の除去のために一切の道徳教育が廃止されなければならない。(6) しかし、H.シュルツは宗教そのもののもつ非科学性については触れるところがない。むしろ宗教自体に対してまことに寛大かつ好意的であった。
宗教的信条は本当にどうでもよいことや、軽いことなのではない。それは大人の精神的(geistigen und seelischen)素質や意志や、生活経験や性格、内的表象によるものである。宗教の前に立つことは、全ての成熟した人の神聖なる権利である。(7)
国家が支配階級の利益のために宗教を利用することを認めないし、学校の世俗性を要求するが、しかし、宗教を憎むのではない、と弁明する。(8) このように、H.シュルツの世俗性の主張は、世俗性の本質ともいうべき学校で教えられるべき教育内容の科学性という視点を全く欠落させたものであり、あくまでも反動的支配への反対という政治的視点から主張されていた。それ故ワイマール共和国でSPD自らが支配層の一翼となった時、宗派学校を認めることができた。(9)
ワイマール憲法における「学校妥協(Heinrich Schulz)」とは、SPDは中央党の主張する宗派学校を、中央党は世俗学校を容認する、という相互の妥協であったが、実際上はほとんどが宗派学校であり、世俗学校など皆無に近い状態であたから、当時既に妥協の批判者から指摘されていたように、SPDの一方的な譲歩といってよかった。それ故、SPD内部からも「国民的教育は、国立共同学校において保証されるのであり、この統一は壊されたように思われる。」と批判したザイフェルト(Seyfert)のような議員もいるが、(10)後にみるが、大方はこの妥協を積極的に位置づけていくことになる。1920年になってSPDの機関誌『平等(Gleichheit)』は次のように書いた。
今日まで、この妥協は子供の精神のための最も先鋭なる闘いをもたらした。個々の人々にとって、最も重要な宗派的な感情を公の広場に引き出すことになった。学校の世俗性と宗教の歴史的教授は、子供の中に他の思考に対する理解と判断を呼び起こすのである。(11)
しかし、SPDとしてはこうした論理の帰結としてある世俗学校を生み出す努力よりは、この論理を生み出す相対主義に傾いていくことになる。(12)そして、この相対主義による学校と宗教の問題の定式化を行ったのはラートブルフであった。
ラートブルフは国民的統一の核として、「既に色槌せた一般教養(Allgemeine Bildung)」という概念を捨て、(13)朋党関係、共同精神、労働の喜びを内容とする共同体精神を考える。(14)社会主義としては世俗学校を求めるが、国民が分裂している現実の前には、それは将来の問題であり、現在では暫定的解決として、民主主義的寛容に基づいた宗派混合学校を要求することになる。(15)11920年のカッセラー大会での宗派混合学校および統一学校の要求は、(16)価値的相対主義に立つものであり、統一学校の主張には必ずといってよい程、統一の核となる陶冶価値が含まれていたが、それを含まない特異な統一学校論となった。しかし、後年「世界観政党」を捨て、「目的政党」となることを主張したラートブルフの姿勢が既に現れている。
<註>
- Heinrich Schulz "Schulreform der Sozialdemokratie" s10,24
- a.a.O. s24
- ブタホフによれば、H.シュルツはこの時『ゴータ綱領批判jの影響によってアメリカを高く評価した。Hans Wolf Butterhof "Wissen und Macht ── Widersprüche sozialdemokratischer Bildungspolitik bei Harkort, Liebknecht, Schulz" 1978 s92
- Heinrich Schulz a.a.O. s34
- Heinrich Schulz 'Religion und Volksschule' in "Die Neue Zeit" 1905 s12-127
- Heinrich Schulz "Schulreform der Sozialdemokratie" s118
- a.a.O. s90
- a.a.O. s91
- W. Wittwer a.a.O. s98
- Max Quarck a.a.O. s63
- Clara Bohm=Schuch 'Aufgaben der Erziehung' in "Die Gleichheit" 1920.1.10 s30-32
- しかし、全体としては次のH.シュルツの言葉にみられるように、妥協を正当化したのは政治的配慮であった。W. Wittwer は次のように書いている。「ワイマールの学校妥協は全ての妥協と同様不快なものである。重要な事項に関係した者全てにとって苦悩がある。しかし、それは不可欠だっためであり、多くの批判にかかわらず同じ前提下では再び同じことがなされたに違いない。ドイツにとって今日向あらゆる方面から、多く論難されながらも、ドイツの国家的独立を保持する唯一の正当な方法である条約履行政策を可能にしているものは、ワイマールの学校問題の一致なのである。学校問題の一致は憲法の成立にとって、最後の最も困難な前提なのであった。そのような至高で最も重要な目的のためには、学校問題の不本意な解決も背負わなければならない。」W. Wittwer a.a.O. s99-100
- ラートブルフ『社会主義の文化理論』著作集第8巻 東大出版会 p32
- 同上 p11
- 同上 p41
- Hans Breitgoff, Holger Erhardt, Reate Ramb 'Theorie und Praxis der >Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Lehrer und Lehrerinnen< 1919-1920' in "Lehrerschaft, Republik und Faschismus 1918-1933" hrsg. Dietfrid Krause Vilmar 1978 s59
<シュルツと公民教育>
H.シュルツは大戦前ケルシェンシュタイナーの公民教育について原則的な批判を展開していた。
公民教育は基本的に社会民主党とプロレタリアートの運動に対する対策であり、ケルシェンシュタイナーの議論が登場した経緯は既に書いた。もちろんシュルツはその点を正確に自覚していた。(1) そうした「公民教育」に反対することは当然であった。
ケルシェンシュタイナーは人間の階級差別を何ら変えていこうとしておらず、支配する者と支配される者によって未来を構想している。支配者に進んで服従し、一方労働者として有能なものを望んでいる。(2) ケルシェンシュタイナーが重視する価値は、皇帝への恭順と犠牲的な愛国心である。(3)
そもそも国民学校自体が、信心深い労働者と敬虞なる小羊を作り上げることを目的としている。倫理・宗教・愛国心の形成に利用されているのである。(4)
すなわち支配の手段としての公民教育を拒否し、自由への方法としての青年運動をH.シュルツは対置する。しかし、H.シュルツの批判の視角は、人問の発達に対する教育的意味を含んだ批判ではなく、政治的批判を主とした。先述したように、ワイマール憲法の公民教育の条項はほとんどケルシェンシュタイナーの公民教育概念によっているが、憲法作成の中心勢力であったSPDは、この点について批判した形跡がない。H.シュルツは、SPDがKPDを弾圧する側に身を置くや、「支配の手段」というのは批判の対象ではなくなったのだと言うことができるであろう。
H.シュルツには一貫したナトルプヘの高い評価があったが、ナトルプの社会的教育学は、ケルシェンシュタイナーと対立するものではなかった。
以上のようなH.シュルツの論から、公民教育の安易な承認に至ることは自然なことであった。D.エフィクはワイマール憲法の発効によって「国家と教育」の関係が変化し、新しい共同体が出現したと賛美し、新しい公民教育の構想を示した。それによれば、第一節.ドイツ国民国家の国家法的構造、第二節.新しい文化経済政策、第三節.外交政策となっており、これによって社会主義的国民が育成されることを期待して次のように書いている。
誠実さ、献身的な労働者は新しい女性公民の形成を保証する。しかし、公民として育成された母は、社会主義共和国に対して、新しい世代の成長を保証する。その世代は、愛や労働や休息において、革命が自由に道を開いた真の社会主義を建設するのである。(5)
しかし、今日では様々な研究によって明らかにされているように、公民科や歴史等で教えられた内容は、第一次大戦までの軍国主義的性格をほとんど変えるものではなかったのである。(6)
<註>
- Heinrich Schulz a.a.O. s145
- a.a.O. s148
- a.a.O. s147
- a.a.O. s13
- D.Dlga Effig 'Staatsbürgerliche Schulung sozialstischer Frauen' in "Die Gleichhati" 1919.9.27 Jg 27
- ゾンドハイマー『ワイマール共和国の政治思想』1968 Horst Diere "Rechtssozialdemokratische Schulpolitik im Dienste des deutschen Imperialismus" は、SPD多数派は、軍国主義的・愛国的教育を実際には否定しなかったと、主張している。
(3)H.シュルツの統一学校論
<シュルツの統一学校原則>
統一学校はSPDの政策としては、ただの一度として否定されたことのない原則であり、世俗学校以上にSPDの重要な政策であったといえる。大戦前のクララ=ツェトキンのように、統一学校を過大視することを諫めた者はいたが、それもケルシェンシュタイナーのような国家有機体説的統一学校論への批判と、理想的な統一学校が資本主義社会で実現するという幻想への批判であった。
さて、マンハイム党大会では、統一学校について次のように掲げていた。
全学校制度の世俗性と統一性の基礎に立った全国学校法の制定。下級教育施設に上級教育施設が組織的に付加されること。公立学校の授業・教材・給食の無償。親の市民的権利を顧慮することなく、優秀でありながら資力のない生徒に、教育を継続するため国が援助すること(1)
これ以降、統一学校はSPDの正式の要求となったのであるが、H.シュルツはまず統一学校について次のように理解している。
社会民主主義者は、全公的教授制度の組織的統一性のために努力し、真の統一学校を欲する。
統一学校とは『一つの』学校、一種類の学校類型のことではない。つまり、統一学校は教授目的や教授方法が肉体的・精神的素質に適当であろうが、そうでなかろうが、全ての子供を強制するようなプロクルーステースの寝台ではない。
統一学校は包括的なものであって、国民の義務就学年齢の青少年を、性・年齢・性向・能力・親の関係を顧慮しないで入れる。それと同時に計画的に分岐し、各自の教育上の特殊性、子供の能力の段階的な身体・精神・情操の教育への社会の要求に適するような弾力性のあるものである。(2)
このH.シュルツの統一学校の規定は何よりも、個人の能力に適った教育に対する機会均等の原則に貫かれている。もちろん、「優秀な者に自由な道を」といスローガンで足りるとするブルジョア的統一学校論ではない。「競争の自由」ではなく、機会の平等を阻害する条件の除去を、様々に主張している。
H.シュルツはその機会均等原則を阻害するのは、まず第一に、様々な学校類型間における教育条件の格差である、としている。例えばH.シュルツは次の表をあげて格差を示している。(3) いかに平等が保証された条件で進学が決められても、進学した学校の教育条件が不平等であれば、教育に関する機会が平等に保障されたとはいえない。
この表で見る限り、初等学校と中等学校の条件の差は歴然としており、H.シュルツは第二段教育の学校までを単一の学校とすることで、その差を克服しようとするのである。
表 各種学校の教育条件
| 生徒数 | 教師数 | 教師一人当たり生徒 |
| 国民学校 | 327,551 | 5,539 | 59 |
| ギムナジウム | 4,190 | 233 | 18 |
| プロギムナジウム | 454 | 26 | 17 |
| ラテン語学校 | 1,597 | 101 | 16 |
| 実科ギムナジウム | 3,053 | 127 | 24 |
| 実科学校 | 15,435 | 535 | 29 |
| (男子中等学校計) | 24,913 | 1,034 | 24 |
| 中等学校の下級 | 20,566 | 758 | 27 |
| 予備学校 | 4,015 | 101 | 40 |
| 高等女学校 | 5,272 | 186 | 28 |
次に個人の様々な経済的格差を是正する政策である。
幼稚園から大学までの無償。(4) 義務教育である国民学校の無償は、憲法での規定であるが、中等学校・大学を無償にすることによって、機会の平等を実現できる。(5) そして教材・給食の無償である。(6)
そして貧困で能力のある児童への経済的援助である。
もし授業料・教材・給食費の無償が実現すれば、才能ある生徒への特別の援助はいらない。しかし、今日まだそれらは行われていない。(7)
第三の平等は、教育内容の平等である。シュルツがケルシェンシュタイナーのようなブルジョア的思想家ではなく、やはり社会主義者であるのは、この内容の平等を主張していることであろう。
教育内容の分裂は、階級分裂の反映であり、中等学校は支配階級にとって必要なことを教え、国民学校は資本家の利益になる限りの「中等学校のものまね」が教えられる。(8) 労働者にとって必要なのは、労働を基本とする統一的な教育プランである。言語的文化・手工・芸術・自然科学を現実の労働技術を踏まえ、肉体労働と精神労働を結合するように、教授がなされなければならない。(9)
そして歴史は、皇帝や祖国への忠誠を培うためのものになっていることを、批判し、科学的真実を教えていかなければならない。(10)
<註>
- Heinrich Schulz a.a.O. s3
- a.a.O. s47
- a.a.O. s28
- a.a.O. s71
- a.a.O. s74 ただしこの点については、マルクスのゴータ網領批判の問題が、依然残る。
- a.a.O. s76-81
- 87
- 178
- 179-191
- 194-195
くシュルツの学校体系構想>
H.シュルツの学校体系は次のような図によって示されている。
幼稚園から中間学校までが義務であり、クラスは30人以下にすることを求めている。(1)
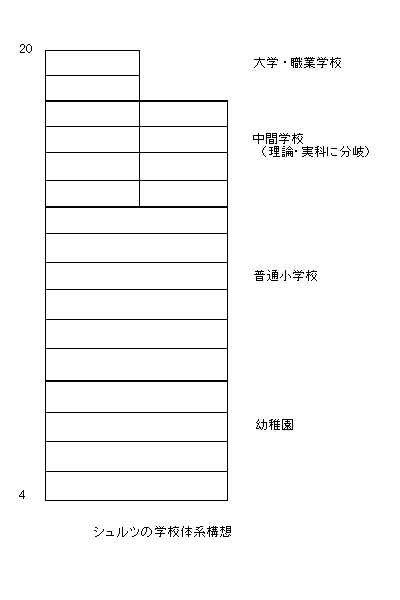 SPD内部で国民学校を、6年制にすべきか、8年制にすべきかが論争されたが、(2) 著書ではシュルツは8年制を主張するが、この図では6年制の構想になっている。(3)
SPD内部で国民学校を、6年制にすべきか、8年制にすべきかが論争されたが、(2) 著書ではシュルツは8年制を主張するが、この図では6年制の構想になっている。(3)
この体系図でみる限り、極めて単純化された単線型の学校体系をH.シュルツが考えていたことがわかる。それは特に二つの点で際立っている。
第一に、幼稚園を貧困児童の託児所ではなく、家庭と学校の二つの機能を合わせもったものとして、プロレタリア家庭の要請に適応した形で構想していること。(4)
第二に、中間学校がケルシェンシュタイナーへの批判を意識していることである。ケルシェンシュタイナーに対する批判は、ケルシェンシュタイナーの中間学校の構想は、才能のある一部の者だけが念頭におかれている、という点に向けられ、それ故H.シュルツの構想は中間学校までが、義務就学とされた。(5) 格差と結びつかない「構想」という点ではH.シュルツは確かに徹底していた。しかし、H.シュルツの構想には明確に二つの点で現実との妥協を許す論理をもっていた。
第一に、社会民主党の社会主義的要求は、社会主義社会において初めて実現するのであって、資本主義社会では実現しないのだ、という「原則」が確固としてあったことである。(6) 先にみたラートブルフの世俗学校と宗派混合学校の要求の使い分けも同様の構造をもっていた。もちろん、資本主義社会の中で社会主義の政策が実現するはずはない。KPDもしたがって、同じことを繰り返し述べている。しかし、KPDの場合、統一学校の批判として述べられていたのに対して、SPDの場合は体制的統一学校の容認になった。
ワイマール憲法制定過程において、SPDは政権党であったにも関わらず、一度としてこのH.シュルツの構想を提起した形跡はない。同時期イギリスでは、16歳から18歳までの年320時間の継続教育の義務化を定めたフィッシャー法が資本家の強い反対で延期され実現しなかった程であるから、SPDが要求を提案すれば、もっと大きな資本家の抵抗に会い、政治的争点となったことは疑いない。しかし、そのような争いは生じなかった。つまり、H.シュルツのこのラディカルな学校体系案は、実現する意志も可能性への確信もないところで、生まれたものなのであり、政治的に体制的統一学校論を支持していたのである。プロイセンの文相であったへ一ニッシェ(Konrad Haenisch)はより直裁的にそうした意識を語っている。
基礎学校法は階級学校の除去という統一学校への決定的な一歩を進めたのであり、それは統一的な国家形成の土台をつくったことを意味している。私は、統一学校は ── 階級対立の除去とはいかないにしても ── 諸階級の理解・融和に役立つものと考える。(7)
ここでへ一ニッシェは「妥協」を越えて「協調」にまで行き着いていることがわかる。
第二に、平等とされた中間学校も二つの分岐、つまり「理論的(theoretisch)」と「実科的(praktisch)」のコースをもっており、そのコース分化が格差化となることを防ぐ原理が、必ずしも明確ではなかったことである。
全ての統一学校論は、次の二つの主張を含んでいる。
1.学校制度の統一的組織
2.各個人の個性・能力を発展させる内的分化
統一学校論がエリート選抜の底辺の拡大を意図している時、初等後の分化した学校類型には社会的階層秩序が色濃く反映される。ケルシェンシュタイナーやシュプランガーはその類型間の平等を保持するための方法は、そもそも課題ではなかった。しかし、H、シュルツの「構想」にとってそれは不可欠であり、その方法原理を欠いた時、いかに「平等」を叫んでも社会階層秩序に学校もからめとられてしまうのである。
H.シュルツはそれを「労働教育」に求めた。そこで次にH.シュルツ「労働教育論」を考察しよう。
<註>
- Heinrich Schulz a.a.O. s175
- 論争については、W. Wittwer a.a.O. s57
- Heinrich Schulz a.a.O. s175
- a.a.O. s130
- a.a.O. s59-60 ここでH.シュルツは「ケルシェンシュタイナーにおいては、技術ギムナジウムはもちろん国民学校の時期を飛び越えて、より広い技術の理論の学習を行うとする意思と能力をもった特別の才能のある者のみが求められている。しかし、われわれのプランでは中間学校は全ての子供に対して義務就学である。」と批判している。
- a.a.O. s182
- K. Haenisch "Staat und Hochschule" 1920 s69
(4)H.シュルツの労働・青年・家庭教育論
<シュルツの労働教育論>
当時社会主義者が「労働教育」を論ずる時、それは三つの課題を負っていた。
第一に、労働者階級の解放を思考する際の、労働者に求められる力量を育てるという本質的課題である。したがって、この意味での「労働教育」を欠いた教育論は、社会主義教育論とはいえない。
第二に、統一学校の統一の核を示すという課題。
第三に、新教育運動(改革教育学)の中で出てきた様々な労働教育、労作教育を批判・吟味するという課題。とりわけ統一学校論の代表的イデオローグであったケルシェンシュタイナーが労働教育実践家の第一人者でもあった、という事情が第三の課題を重要なものにしていた。(1)
シュルツも労働教育は中核として位置づけている。手工とともに機械に関する知識を正しく教え、(2) それを自然科学と結び付けなければならないとしている。(3) 特に労働青年に対する継統教育を重視している。これはシュルツ自身が提示する学校体系案とは異なるが、それが実現しない時点での対案である。(4)
そうした教育の中で、労働を愛し、職業に習熟し、思考力をつける教育を目指している。(5) シュルツはこうした労働教育に関する議論をマルクス主義の理論と結び付ける。
H.シュルツがマルクス主義教育として定式化したのは、まず何よりも「全ての能力の全面的に調和した形成(Ausbildung)」であり、(6) 資本主義社会までの全ての教育が、頭と手を分裂させてきたのを克服する、という点であった。
将来の社会主義社会では、筋肉ばかり使い、能力のない、知的な指導者からは隔てられ、鞭でかりたてられる駄獣(lasttier)など存在せず、社会は生気にあふれた有機体となり、頭と手は一つに働き、頭と手の労働の格差はなく、全ての者にとって労働が喜ばしく自由であり、充分に発達した肉体的・精神的特性が最良の形で身につけられるのである。(7)
そして、その実現のための、統一的で適当に分岐した学校制度なのである。(8)
社会主義社会における労働をH.シュルツは「生産過程を見渡せること」と「可動性」という二点で把握している。
社会主義においては、社会の全体への理解が不可欠になるので、生産過程の社会的文化的意味・内的外的関係を完全に理解させるための教育がなされる。(9) そして更にH.シュルツは、マルクスが「資本論」で書いている、資本主義大工業は「大工業は、いろいろな労働の転換、したがってまた労働者のできるだけの多面性を一般的な社会的生産法則として承認し、この法則の正常な実現に諸関係を適合させることを、大工業の破局そのものをつうじて、生死の問題にする。大工業は、変転する資本の搾取欲求のために予備として保有され、自由に利用されるみじめな労働者人口という奇怪事の代わりに、変転する労働要求のための人間の絶対的な利用可能性をもってくることを、すなわち、一つの社会的細部機能の担い手でしかない部分個人の代わりに、いろいろな社会的機能を自分のいろいろな活動様式としてかわるがわる行うような全体的に発達した個人をもってくることを、一つの生死の問題にする。」(10)という規定を度々引用している。しかし、この規定の理解について、H.シュルツは先にみたように、一方では「可動性」を現実に要請したのは帝国主義戦争である、という実感において理解したこと、他方では、資本主義的工業は実際間題として技術をもった労働者を求めてはいない、という認識が土台としてあるために、現実の労働教育への誤解を生むことになった、つまり、H.シュルツはマルクスがこの規定の中にこめた意味、資本主義はその「不断の変革」の必要性によって労働者を全面的に発達させる一方、絶えず労働の単純化によってそうした教育を否定する、という矛盾したベクトルをもっていること、その中で全面発達の教育を実現するのは労働者の革命的実践である、という認識を欠いていた。したがって改革教育学への混乱した評価が生まれたのである。
H.シュルツは新教育運動の代表例であるリーツの「田園教育学舎」を、それが旧いい学校制度への鋭い批判であり、遊びと労働を教育と結合していると評価し、更にこの実践はペスタロッチ、ゲーテ、マルクス等が提起した労働と教育の結合の一例である、という規定を与えたのである。(11)これまで度々紹介したように、ケルシェンシュタイナーは常に批判の相手であったが、ナトルプは高く評価している。そして、「我々の社会的理想は『自由への教育』が相応しており、その意味で全ての職業、全ての社会的段階における労働に対して、内容を与え、全ての人に価値ある目的を与える」というナトルプの言葉を引用して、公民教育についての結論としているのである。(12)しかし、ケルシェンシュタイナーとナトルプが教育思想的にも政治的にも対立しているとはいえないし、リーツ自身統一学校案を示しているが、それはケルシェンシュタイナーのそれとほとんど変わるところはなかった。(13)したがってH.シュルツが改革教育学に対して、過度の高い評価を与えた、ということは否定しようがない。(14)これは本質的には彼等の階級的性格に帰せられることであろうが、論理的には教育の歴史的発展についての見方から帰結した。
H.シュルツはマンハイム党大会で、過去の階級教育について次のように述べた。
唯物論的考察によれば、これまでの歴史において、哲学や理論はあったにも関わらず、普遍的で平等な国民教育はみられない。これまでの社会的生産はまだそれを要求しなかったのである。まだ経済的要請(Bedürfnis)が存在しなかったのである。(15)
ツェトキンは第一次大戦前に、貴族を廃止し、軍隊を民兵に変え、累進課税を大胆に行えば、平等な国民教育は容易に実現できる、と主張したが、(16)厳密に当時の経済水準が国民教育を欲したか、可能としたかをここで問うことはできない。ただツェトキンの論がワイマールの国民学校の基礎学校が生み出された時、その妥当性を論証されたといえよう。したがって、社会民主党の論理は、不十分な学校への批判的視点を確保しえたにも関わらず、H.シュルツの論理は次のような評価に帰結したのである。
革命は全ての事項について国民の自己統治、自己管理を意味する民主的国家は、したがって全ての才能ある者に対して、より高い職業に上昇することを可能にし、全ての準備教育をし、そして、国家共同体に奉仕し、不可欠の能力の生成を可能にする統一的学校制度をつくらなければならない。(17)
1920年の基礎学校法の提案に際して出されたこの文は、ワイマール憲法及びケルシェンシュタイナーの統一学校論と完全に重なりあっている。W.べ一ムによれば、マンハイム党大会当時、H.シュルツは修正主義に対して闘った正統派に属していたというが、(18)経済的土台によって説明する先のH.シュルツの論は、史的唯物論の公式的な理解を示している。そして、資本家は教育ある労働者を欲しない、という理解が結びつく時、現実に可能な条件への究明はなされない一方、資本家の教育政策の免罪となり、ワイマールで自らの改革によって基礎学校を実現するや、前進が過度に見えることに通じていったのである。
<註>
- ワイマール憲法は第148条3項で「公民科(Staatsbürgerkunde)及び労働教育は学校の教科目である」と規定した。この点について "Geschichte der Erziehung" はケルシェンシュタイナーの理論が取り入れられた、と評価しているが妥当であろう。
- Heinrich Schulz a.a.O. s183
- a.a.O. s189
- a.a.O. s141-142
- a.a.O. s143
- a.a.O. s189
- a.a.O. s10
- a.a.O. s10
- a.a.O. s9
- マルクス『資本論』全集23 p634
- Heinrich Schulz 'Landerziehungsheim' in "Die Neue Zeit"1902-1903 s76-81
同じ見解をH.シュルツはマンハイム党大会でも発言している。Karl Christ "Sozialdemokratie und Volkserziehung ── Die Bedeutung des Mannheiner Parteitags der SPD im Hahre 1906 für die Entwicklung der Bildungspolitik und Pägogik der deutschen Arbeiterbewegung vor dem Ersten Weltkrieg" 1975
- Heinrich Schulz "Schulreform der Sozialdemokratie" s150
- H.Lietz "Die deutsche Nationalschule" 1920
- W. Wittwer は1914年以後SPDの政策は改革教育学と同質になっていた、と評価している。W. Wittwer a.a.O. s66 ナトルプの死んだ時、SPDは、ナトルプは社会主義者であったとして高く評価する論文を発表している。Karl Vorländer 'Die Lebensarbiet Paul Natorp' in "Die Gesellschaft Internationale Revue für Sozialismus und Politik" 1925 s82
- Heinrich Schulz "Schulreform der Sozialdemokratie" s17
- ツェトキン『民主教育論』五十嵐訳参照
- Hedwing Wachenheim 'Der Gesetzentwurf über die Grundschule' in "Die gleichheit" 1920.3.6 Jg 3
- Winfried Böhm 'Paul Oestreich und des Problem der Sozialistische Pägogik in der Weimarer Republik' in "Sozialisation und Bildungswesen in der Weimarer Republik" herg. von Manfred Heinemann 1976 s192
<シュルツの青年運動論>
次にH.シュルツの青年運動論についてみておこう。
H.シュルツはケルシェンシュタイナーの公民教育論に対抗する意味で、青年運動を主張した。(1) これは、ケルシェンシュタイナーの公民教育論が周知のように、義務就学を終えて兵役に就くまでの青年の教育についての懸賞論文であったことからもみられるように、(当然それはその間社会主義に触れさせないための施策が求められたのである)青年は支配層にとっても社会主義者にとっても重要な対象であった。国民教育について論じたマンハイム党大会で青年教育が論じられたのも当然のことであった。
第一次大戦前、SPD内部で青年運動について、二つの点に於て原則的な意見対立が生じていた。第一には「青年文学」をいかに考えるかという問題である。論争の中心となったのは、次のようなカウツキーのテーゼであった。
1.青年文学は政治的内容 ── 社会主義的なそれをも含めて ── から自由でなければならない。
2.青年文学は決して政治的煽動の手段であってはならない。
3.たたかうプロレタリアートは文化的には非生産的である。
4.プロレタリアートはまず、ブルジョアジーの文化的遣産から始めるべきである。(2)
1このテーゼは激しい論争を巻き起こしたが、H.シュルツは原則的に支持した。
我々は労働者の階級闘争の担い手の能力や応用性を高めることを、それ(青年運動)を通して高めたいと思う。
しかし、子供は階級闘争の担い手として使われてはならない。それ故我々は生業目的の児童労働には積極的に反対し、党の奉仕のための児童労働に反対するのである。
党において、計画的に啓蒙すべきだというのは良い。しかし、そのことによって社会主義的な意味において、子供への影響が可能だということにはならない。それは党の事柄ではなくて、個々の党員や父母の事柄なのである。(3)
KPDの論理と異なるのは、後述するが、個々の党員や父母の意思という形態をツェトキンは批判することである。ツェトキンにとっては、個々の意思ではなく、「組織された階級の意思」なのである。
第二に、迫りくる軍国主義に対抗する目的で青年運動を組織するのか否かという問題である。20世紀に入り、植民地を舞台とする帝国主義的な侵略戦争が多発していたが、植民地問題や、迫り来るヨーロッパの戦争に対して、青年を組織して反対することをK.リープクネヒトが提案していた。(3)
マンハイム党大会はこの提案を否定したのであるが、(5) テーゼやH.シュルツの主張は、ともかく、帝国主義戦争に帰結した当時の軍国主義的傾向に、大人(党)が責任をもって闘い、子供には将来に向けて幅広い学習を保証する、という反対ではなく、党自身が闘いを次第に放棄する姿勢の現れであった。そして、H.シュルツの青年運動論は、子供を階級闘争の担い手としないところに留まらず、政治的成長という見地を欠いたものであった。
戦後SPDの青年運動は、KPDとはかなり異なった原則で進むことになる。SPD関係の青年組織は、「社会主義労働者青年(Sozialistische Arbeiterjungend)」と「青年社会主義者(Jungsozialisten)」があった。青年は独自の運動を好むものであるが、SPDの場合は党指導部が、党の指導性を放棄していた。(6)
その見解の中心はシュルツであった。
H.シュルツの青年運動の基本は、青年自身の手によって運動を組織する、という自治原則であった。(7) しかし、青年運動を広く国民教育の一環として捉える場合、教育指導を欠く自治は運動を自然発生性に任せることになろう。(8) そして、青年運動の内容として期待したのは、市民的青年運動が重視していたホーム(Heim)や、スポーツ、遊戯であった。(9) H.シュルツはこれらの市民的青年運動を否定するのは誤りである、と明白に述べており、したがってH.シュルツの論理からは青年が社会民主主義的人間像に育つ道筋は具体的に浮かびあがってこない。
もっともSPDの青年運動に関する方針が、完全に青年の自発性にまかせる、というものだったのではない。党指導部の管轄におこうとしたことは何度かある。ハイデルベルク党大会でも、シュルツは指導性を求める発言をして、喝采をあびたという。(10)しかし、青年運動は通常、SPDの方針より急進的であったので、この党の指導性は、青年を抑える意味をもっており、青年自身からは支持されなかった。1925年の青年社会主義者の大会では、階級対立を覆い隠す平等な選挙権に満足することなく、国際的な階級闘争を反映させていくことを決議している。(11)
<註>
- Heinrich Schulz "Schulreform der Sozialdemokratie" s150
- K. Christ a.a.O. s105
- a.a.O. s115
- この間の事情については、山本佐門『ドイツ社会民主党とカウツキー』北海道大学図書刊行会1981
- 安世舟、前掲 p190 Karl Heinz Janke "Geschichte der deutschen Arbeiterjugnedbewegung 1904-1945" 1973 s35 リープクネヒトは独自に青年運動を組織していくことになる。
- Martin Martityny 'Sozialdemokratie und junge Generation am Ende der Weimar Republik' in "Sozaildemokratishe Arbeiterbewegung und Weimarer Republik Materialien zur gesellschaftlichen Entwicklung 1927-1933" 2 hrsg. Wolfgang Luthardt 1978 s57
- Heinrich Schulz 'Sozialdemokratie und Jugendbewegugn' kn "Die Neue Zeit" 1910 s493
- シェンクはH.シュルツを自然発生論者と規定している。J. Schenk a.a.O. s142
- Heinrich Schulz a.a.O. s497-498
- Max Westphal 'Der Parteitag in Heidelberg und die Jugend' in "Sozialdemokratische Arberterbewegung und Weimarer Republik Materialien zur gesellschaftlichen Entwicklung 1927-1933" s67
- Entschließung der Jungsozialisiten a.a.O. sし69
<シュルツの家庭教育論>
同様のことはH.シュルツの家庭教育論についてもあてはまる。H.シュルツは家庭の教育機能を重視し、資本主義社会においては、父は工場で労働し、母も四分の一は働いているから(1907年当時)充分教育者としての役割を果たすことはできないが、なお子供の第一の教育は家庭教育にある、としている。(1) 家庭の教育機能として他に代えることができないもの、すなわち家庭教育の中心は父母の愛(Liebe)である。(2) そして、家庭教育こそ、母の仕事であるとH.シュルツは考える。(3) つまりH.シュルツの家庭教育論は明確に市民的婦人論であった。(4) 結局H.シュルツに代表されるSPDの家庭教育論は、男女別学が殆どで、しかも女子中等学校はあまりなかったにも関わらず、「グライッヒハイト」誌が、「革命は我々婦人に対して国家における平等な権利をもたらした。」(5) という主張を載せたことを許容した。(6)
このような青年教育論、家庭教育論は教育制度論として、改革教育学に陥ったと同時に「政治と教育」の関係について、H.シュルツの認識が表現されたものであった。
史的唯物論から、制度を構想するとき、H.シュルツは「正統派」であり、理想的制度を考えたが、それは常に将来の問題であった。そして、現実の改革に際しては、ワイマール連合という政治を最優先させた。その時、教育によって政治を変える、という改革教育学は、置き去りにされた教育を埋める機能をH.シュルツの論理の中で果たした。
ツェトキンが全国学校法を提案したH.シュルツを批判したとき、H.シュルツは「1904年のことを未だに考えているのは文学的感情であって、おろかな言葉だけの急進主義だ」と反論している。(7) 現実政治の中では原則は一顧だにされなかった。
<註>
- Heinrich Schulz a.a.O. s123-124
- Heinrich Schulz a.a.O. s121
- Heinrich Schulz "Mutter als Erzieherin ── kleine Beiträge zum Praxis der proretatischen Hauserziehung" s10
- 周知のように資本主義社会では労働力の再生産は究極的には、個々の家庭に、つまり私的領域に委ねられている。市民革命が意図したことは「政治社会」での平等であって、「家庭」においては父権を頂点とする上下秩序が維持される。しかし、大工場の発展、市民的婦人運動の勃興、労働者階級の運動などにより、婦人の私的・公的権利が法的に認められてくるにしたがって、家庭の上下秩序は法的には次第に崩れていく。しかし、市民的婦人論の二つ ── 一方は家庭の中の仕事に女の天職を見出す。他方は才能のある女性に職業上の平等を主張する ── も、家庭における父母の任務の相違を原則として規定することは共通しており、それが市民的婦人論の譲ることのできない一線である。後者の典型をJ・S・ミルにみることができよう。
- Lttliie Kobactovich 'Erziehung zum Sozialismus' in "Die Gleichheit" 1920.1.7
- ワイマール憲法は「同一の公民権(109条2項)」「母性の保護(119条3項)」「公務員の女子例外規定の廃止(128条2項)」を規定している。
- Heinrich Schulz 'Schulreform oder Revolution' in "Die Gleichheit" 1920.10.9
(5)「徹底的学校改革者同盟」の論理
<「徹底的学校改革者同盟」の設立>
これまで何度か言及してきた「徹底的学校改革者同盟」について触れておく必要があろう。(1)
「徹底的学校改革者同盟」はSPDの妥協を批判し、文字通り徹底的な学校改革を主張して生まれたが、その指導者はSPDの党員が多かったし、SPD系の機関誌に寄稿しているので、SPDの理論の中で扱うのが妥当である。(2)
H.シュルツは既に示したように、教育の原則を説く時には、極めて「正統的」であったが、現実政治の中ではその正統的内容を遠い将来の社会主義のこととして、政治的妥協を専ら優先させたのであるが、「徹底的学校改革者同盟」の論理は逆に専ら教育の正統的論理を優先させたのだ、といえよう。その限りで論理の枠組みは基本的に同じであった。(3)
我々は革命的であること、そのように改革することを欲する。(4)
こうエストライヒは書いている。
「徹底的学校改革者同盟」の結成の過程をみておこう。
結成の契機になったことは、二つあった。
第一に、中等学校教師としての彼らの、フィロローゲン連盟に対する批判意識である。
1919年3月エストライヒはフィロローゲン連盟において次のような学校制度改革案を示した。
1.組織的に上構され、ただ素質(Anlage)や才能(Begabung)によって分離された国家統一学校
2.特権制度の廃止
3.貧しい生徒への経済的な援助
4.自由選択の宗教教授
5.学校共同体(Gemeinde)の設置
6.合議制の学校運営
7.全てのフィロローゲンの政治的・宗教的自由(5)
しかし、この要求は5月11日-12日のワイロローゲン連盟の代表者会議で事実上否決される。ここで、決まったのは次のようなものであった。
1.予備学校は廃止されるべきであり、一般的4年制基礎学校が導入され、様々な分岐をもったギムナジウムが保持されるべきである。
2.宗教教授は必修として残されるべきである。
3.合議による校長の選挙は拒否される。
4.学校共同体の導入は単に厳格な条件と制限によって承認される。(6)
こうしたフィロローゲン連盟の保守的体質に耐えきれなくなり、エストライヒは1919年9月18日に、「徹底的学校改革者同盟」を結成したのである。(7)
当時主なメンバーはフィロローゲン内部でも活動を継続しようとしたが、結局お互いの非和解的性質に気づいて、完全に狭を分かっことになる。
第二の契機は、SPDの妥協に対する批判意識であった。この点については既に一章一節で触れた。
<註>
- 「徹底的学校改革者同盟」についての評価は、旧東ドイツではブルジョア改革教育学への批判とSPDの妥協に対する厳格な立場が高く評価されているが、(Lexikon der Pägogik) 旧西ドイツでは、その生産教育がキリスト教的ではないが、宗教に似た観念性をもつとして評価はさして高くなかった。(pägogische Lexikon)事実そのような傾向は存在したといってよい。1920年10月の会議でのフェゲラーの報告は、共同体での「愛」を協調する観念的なものであった。Heinrich Vögeler 'Arbeitsschule und Menschentum' in "Zur Produktionsschule" 1921 (Entscheidener Schulreform Ⅳ)日本では「徹底的学校改革者同盟」の研究は次のようなものがある。川口祐二「パウル・エストライヒの教育思想における人間形成と社会形成」『教育学研究』日本教育学会48巻3号1981、寺沢幸恭「徹底的学校改革者同盟の『生産学校(Produktionsschule)』論について」第25回教育史学会報告プリント
- エストライヒは1918年から1931年までSPDの党員であり、以降KPDに近くなったとされる。"Paul Oestreich ── Entschiedene Schulreform" H. König の序文
- SPD指導部より平和主義的傾向が強いことは異なっている。
Paul Oestreich 'Die wissenschaftlichen geistigen Zeitnotwendigkeiten und die Bildungsanstalten' in "Produkitionsschule" s11 「我々は平和主義・人格・能力を身につけなければならない」S. Kawerau 'Landtagswahl Jugend und Schule' in "Die Neue Erziehung" 1921.1 も同趣旨のことを書いている。
- Paul Oestreich 'Von Bund entschiedener Schulreformer' in "Die Deutschschule Monatsschrift" 1920 s99
- Ingrid Neuner "Der Bund entscheidener Schulreformer 1919-1933" 1980 s27
- a.a.O. s27
- a.a.O. s29
<「徹底的学校改革者同盟」の労働教育論>
「徹底的学校改革者同盟」が最もつよくSPDを批判したのは宗派学校の容認であったが、(1) より重要な意味をもっていたのは、SPDがワイマール憲法にみられるように、生産労働と切り離された改革教育学の労働教育論と妥協したことを批判した点である。
エストライヒは学校圏と生活圏が完全に分離していることを、問題にした。それは書物の上の教養に代表されるように、教養として不十分なものである。(2)
普遍的教養という概念は、陶冶財の量によってもその種類によっても、規定することはできないのであります。たえず自己の不完全さをしっかりと自覚していること、たえず考え・感じ・行動し ── 専心し整理しつつ ── 自己の周囲の世界の本質に迫りそれを「わがものとする」ように努めること、自己を精神的にも心的にも深化し拡大するように努めることと、比較的狭い範囲の事柄を完全にマスターすることを、ともに無限の世界に献身するように自己を関連づけるよう努めること、以上のような場合だけ普遍的教養をめざすということがいいうるのです。(3)
アンナ=ジーンゼンは次のように書いている。
職業と職業教育の問題は、この10年間ますます中心的な教育問題になってきた。今日の社会における人間活動の中核として職業を理解し、そこから人間を公民として、そして人格として規定しようという試みは、強力な実践的作用をもっている。しかし、教育を今日の職業から、つまり資本主義経済の偶然的に捉えられた純粋の世襲的職業から、教育を規定しようという全ての試みは、経済の変革が教育問題として、社会主義が学校や教育政策的要求として現れるという矛盾に至らざるをえない。(4)
つまり、ここには明らかにケルシェンシュタイナー的論理の必然性の認識と、しかし、その矛盾から社会主義が導かれる確信が基礎になっているのである。
カベラウは「資本論」に定式化された生産労働と教授の結合を「生産学校」として具体化したのであるが、(5) エストライヒはそれを「核になる教授(Kernunterricht)」として統一学校の核として位置づけた。このことは、H.シュルツが中等段階の学校を理論的と実践的に分けることによって、三分岐を根底的に批判することができず、それを容認したことを考えると、それを克服する一つの手がかりを与えるものであった。彼等が新しいソビエトの総合技術教育を積極的に取り入れようとしたことは、このような下地があったからである。(6)
しかし、エストライヒを例にとれば、SPDの妥協に反発はしたが、当初その考えは極めて能力主義的な統一学校論であった。1921年に行なった講演の中で、エストライヒ自身が過去の自分の案として紹介した案は、国家の学校、能力による選別、三分岐制度(英才学校・普通学校・特別学校)を提起していた。(7) エストライヒ自身こうした案を批判していく。
統一学校を社会の施設としての学校、生活学校としての学校である場合だけ現実の創造的営みと結びつくことができるのであり、又教育・発達可能性における統一と平等という原則を具体化するために何もしないならば、形式的な虚構にすぎない(8) 「精神」と物質界、頭の労働と手の労働とが、いつでも相互に浸透しあっており、職業に貴賎の別はなく、ただ様々な職業が存在するだけにすぎなくなり、上級学校への進学が最早『より高い』(より報酬のよい)地位へ導くところの(つらい!)梯子としては評価されなくなることこそが必要だ、として能力主義的な三分岐制を捨てたのである。(9)
したがって、エストライヒは中間学校や上構学校には反対である。
上構学校は、「若干のよくできる」生徒のための進学中心の学校であり、それによって農村の生徒はほとんど得るところがないし、教師にとっても自分の力量を高めるために必要なものではない。必修を減らして選択を大幅に増やせば意味がある。(10)
これがエストライヒの上構学校批判の論拠であった。
エストライヒの弾力的統一学校の原則をまとめると次のようになる。
1.単線型学校体系
2.地域の学校
3.宗派学校の廃止
4.男女共学
5.教育費の無償(11)
そして、生産労働を中核とする弾力的統一学校を構想し、「徹底的学校改革者同盟」に参加する教師は事実様々な実践を試みた。
アンナ=ジーンゼンは次のようなカリキュラム案を示している。
基礎学校では
A.観察・判断・比較
── 理科・国語・図学・作文・幾何・代数
B.表現
── 体育・舞踊・音楽・絵画・スケッチ
C.郷土科 x
となっており、上構学校(Aufbauschule)では、生産・経済・社会・公民科・文化史等である。(12)
「徹底的学校改革者同盟」の注目すべき実践として、アウグスト=ハインが、国民学校の卒業生に対して、定時制の「園芸学校(Gartenarbeitsschule)を開いたが、その費用は生徒の労働によって賄われた。(13)
E.シュバルッ(E. Schwartz)はラインやケルシェンシュタイナーが才能によって分けるという原理をもちだすだけでなく、社会主義に敵対するに至っていると批判した後で、生徒の性向(Veranlagen)によってカリキュラムを分け、教えるというのではなく、先ず正しく認識し、かつ育てることが必要だ、と書いている。(14)
このような労働教育論は、二つの側面があった。第一に、ケルシェンシュタイナー流の手工労働から抜け出て、より社会的労働に拡大されていることである。1921年の講演でエストライヒはケルシェンシュタイナーの陶冶論を絶賛していたが、後に原則的な批判を加えるに至った。
彼が一方で、教育の選択にとって個人的精神構造が決定的であると望んでも、他方、精神構造を越えて早期の決定を望み、結局閉鎖的な学校類型に帰結してしまう。(15)
ケルシェンシュタイナーの能力の先天説への批判から、選別の論の批判へと発展している。しかし、労働を社会的労働と結びつけることは、現実の労働に子供を参加させることによって、子供に過酷な労働を強いる危険を常に孕んでいた。エストライヒ自身は、子供の労働の搾取に強く反対していたが、(16)多くの教師が各地で行っていた労働教育実践の中には、工場に働きに行かせた例が少なくなかったとされる。(17)子供自身も社会的労働の一部を担うことによって社会的責任を果たすべきである、というマルクスの言葉は、子供を搾取労働に投げ込む危険が絶えずつきまとうが、「徹底的学校改革者同盟」もまたこれを実践的に解決するには至らなかった。
<註>
- Paul Oestreich 'Die Grundfrage des Schulkampfs' in "Die Neue Erziehung" 1928.2 ゲルトナーは旧い学校は形式的な宗教的観念を教えるだけの子供の荒野だと批判している。Paul Ga¨rtner 'Neues Volks? ── Neue Schule?' in "Die Neue Erziehung" 1921.1 s2 他に Arbur Jacobs 'Die Entschiedene Jugendbewegung und der Büger' in "Die Neue Erziehung" 1921.1 s39
- エストライヒ『弾力的統一学校』 p17-19
- 同上 p22
- Anna Siensen 'Beruf und Erziehung' in "Die Gesellschaft" 1924 s584
- Siegfried Kawerau 'Die Produktionsschule' a.a.O. s6
- Reichsshulkonferenz 1920 s480-481 ここでエストライヒは統一学校に成する主張の多くは、実際はそうでないと批判し、統一学校は平等学校(Gleichheitsschule)でなければならないと述べた。統一学校は平等学校ではない、というのはケルシェンシュタイナーやナトルプが保守層への弁明のために繰り返し述べた言葉であった。
- エストライヒ『弾力的統一学校』中野光他訳 p38-42 ここでいう特別学校というのは能力の劣った者のための実科的学校のこと。エストライヒの弾力的統一学校の概念は、全ての生徒のために一つの椅子を用意しながら、弾力的に変えることのできないラインやテウスヘの批判であった。
- 同上 p24
- 同上 p48
- 同上 p50 但し、次のような表現がある。「発達の遅れた子どもであっても、後になって何ら損害を蒙ることなく、ある学校系統から他の学校系統へと移ることのできる学校制度を確立することを前提として、われわれは生徒を『普通以上のもの』『普通のもの』『普通以下のもの』に選別することができる。」同上 p39 シャイベはエストライヒの「生産学校」は初め、ブロンスキー流の労働を中心とする教育と規定していたが、次第に創造的な教育という概念に変化していったという。シャイベのまとめではエストライヒの思想は次のようになる。
1.教育過程における自己活動・自立性の原理
2.目標をもった行為による手の能力の発達
3.手作業あるいは精神的意味での労働教授
4.分業による集団の協調性
5.労働世界への準備
6.職業と一般陶冶の関連性
7.職業教育を伴う義務学校としての職業学校 Scheibe a.a.O. s20-210
- エストライヒ同上 p27
- エストライヒ同上 p53-57
- Anna Siensen 'Möglichkeit der Linienführung in Grundschule und Aufbauschule' in "Zur Produktionsschule" s9-11
- Heyn 'Die Neuköllner Gartenarbeitsschule' in "Zur Produktionsschule" s18-19
- E. Schwartz 'Die Einheitsschule differenziere nicht die Schuler nach gradueller Begabung, sondern dem Uniterricht nach der Veranlagung der Schuler' in "Die Neue Erziehung" 1921 s21-24
- Paul Oestreich "Entschiedene Schulreform" s83
- a.a.O. s78
- Monumenta.Ⅸ s78-79 クルプスヵヤはペスタロッチを批判して次のように書いている。「ペスタロッチの疑う余地のない誤りは、教授と生産労働との結合にとどまらず、教授と児童の賃労働との結合をのぞんだことである。児童の賃労働は児童労働の搾取とむすびつき、児童の労力消耗とむすびついていた。」クルプスカヤ『国民教育と民主主義』五十嵐顕他訳 明治図書 p45 クルプスカヤは当時の産業の発展段階が、資本主義前期の児童労働が、極限的に搾取されていた段階であったことを強調している。問題は「生産労働」とは教育的にみて、何を言うのかである。
<エストライヒとカルゼンの対立>
さて「徹底的学校改革者同盟」の内部的対立に触れておく必要があろう。改革を徹底的に押し進めるという人々の集まりであったことも影響して、「徹底的学校改革者同盟」のメンバーは対立する場合が多かった。そのために20年代の末期にはメンバーがかなり変化していたといわれている。
そうした対立として、中心メンバーでありながら、除名されたカルゼンが重要であろう。
小峰総一郎によれば、エストライヒは学校の枠組みを重視したのに対し、カルゼンが学校の内的生命を重視したことが、基本的な対立点であった。(1)
つまり、基本的に教養観の問題であった。
カルゼンは次のように書いている。
今日労働学校思想が普及し、その種の学校が設立されるに至った真の理由は、いまや労働の場をとおして形成される教養が支配的な教養になったという点に求められよう。なかでも広範な国民大衆の学校・国民学校では労働者集団の教養が一般的なものになっている。労働の教養とは形成的・創造的な手の活動をとおして精神的なもの・了解にまで達そうとする教養のことである。労働の教養は、最終的には生活それ自身をとおしての生活教育だといえる。多様な社会的関係のなかで固有の形をとっていとなまれる、生活の必要としての労働 ── この土台のところで自覚的・自立的人格にまで導くのが生活教育である。(2)
では何故労働者階級は新しい教養を求めるのか。
労働者階級は毎日の仕事のなかでまったくもって理解しがたい自然の威力、学識によってでは、とうてい制御できない自然の威力と直接の関係を結んでいるということ。そして、第二に、この自然の威力を支配することができるかどうかに、直接彼ら自身の幸、不幸がかかっているということ。この二つの理由によるのである。したがって、大事なことは人々がいかにしてこの新しい考え方に目覚めた者となっていくかなのだ。だから社会的事業としての新しい教育は、それ自身の枠を乗り越える。古くさい教訓や「文化財」を拒否し、学問や生活のなかで相続されてきたものを拒否して、新たなる意味づけ、新たなる判断、新たなる創造のなかから未来の価値を発見しようとするのだ。(3)
カルゼンは1918年の革命を断固擁護する。
ドイツ11月革命とともに新しい時代が始まった。(4) 非人間的な戦争に対する「人間の側からの反抗、つまり、人間の創造力をこのように乱用することに対する人問性内部からの反抗だったのである。」(5)
もちろん革命は挫折し、労働者階級は後退した。しかし、かつてはブルジョアが主張しながら、本質的には根を降ろしていなかった「自由・生活協同体」という理念が労働者階級によって現実化したのである。(6)
では革命によってどのような事態が出現したのか。
カルゼンは次のようにまとめている。
1.共同社会を目指した運動
2.国家形態の転換
3.新しい精粋(7)
共同社会を目指した運動とは何か。
第一に、労働者階級はブルジョア的伝統、労働生活様式に意味を見いださないということ。
第二に、労働者は人間をやめない、生活にあふれた生き方を望んでいるということである。(8)
これはブルジョア的文化とは質的に異なる労働者の文化様式を求める主張である。手と精神の労働の対立を克服する志向でもあった。労働は精神労働が上級なのではなく、意味があり創造的な労働であることが必要なのである。(9)そうした労働は精神労働か手の労働かを問わず人間の欲求を充足する。(10)
余暇を求め、その中で自由な享楽を得るというブルジョア的文化様式ではなく、労働そのものを人間的なものに変え、それを生み出す共同体の中で人格的価値を実現していくという立場である。(11)このことは後述するゾレッティと著しい対照をなしている。
次に国家形態の転換とは何か。
1927年の時点で、カルゼンは必ずしも革命を敗北とは見ていなかったのであろうか。共和国になった国家は、社会主義政党に率いられた労働者階級の影響の元にある人民国家になったと書いている。(12)
新しい精神とは人間を解放する労働文化とも言うべきものである。(13)労働の中で平等・連帯精神が形成されるという。(14)
しかし、この共同体という思想は不可避的に有機体説的思考をもつことになる。カルゼンは「学校は新しい有機的社会の一環であると同時に若者の生活の場となる。」と書いている。(15)
共同体思想と有機体思想との関連は社会主義者の大きな問題として残っている。
<註>
- 小峰総一郎「カルゼンの生活と教育事業」カルゼン『現代ドイツの実験学校』明治図書の解説
- カルゼン前掲 p110
- 同上 p128
- 同上 p213
- 同上 p214
- 同上 p214
- 同上 p217
- 同上 p217-218
- 同上 p228
- 同上 p219
- 同上 p220-221
- 同上 p224
- 同上 p226
- 同上 p227
- 同上 p234 なお本書解説で、小峰がカルゼンの実験学校を、初等から中等学校までの一貫教育をすることをもって、「統一学校」と呼んでいるが、そうした語の使用が皆無ではないが、「統一学校」とは本研究で明らかにしているように、国家的な学校体系の問題であるので、不適切であろう。
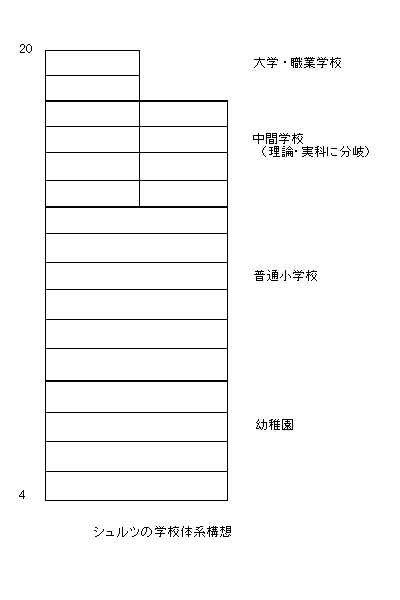 SPD内部で国民学校を、6年制にすべきか、8年制にすべきかが論争されたが、(2) 著書ではシュルツは8年制を主張するが、この図では6年制の構想になっている。(3)
SPD内部で国民学校を、6年制にすべきか、8年制にすべきかが論争されたが、(2) 著書ではシュルツは8年制を主張するが、この図では6年制の構想になっている。(3)