第四章 体制的統一学校論
第一節 ケルシェンシュタイナーの統一学校論
(1)はじめに
第一部で制度史的に統一学校の実現及び非実現過程を見たが、多くの場合議論が先行し、十分に実行されたとはいえないものであった。大戦間の学校制度改革というのは実は壮大なる改革論議であった、ということができる。その実現は第二次大戦後に多くは持ち越されたのである。だからといって、大戦間の論議が無意味だったというわけではない。むしろ、安易な実現を拒否するほどに、論議が徹底的に、ある場面では敵対的内容をもってなされたのである。
論議の下地には第一次世界大戦後の国民の分裂という事態があった。もっとも、国民の分裂は階級の発生とともに生じたのであるから、このこと自体は新しいことではない。労働者階級が明確な権利の主体として、制度的にも定着したことによって、新たにこの分裂が「認識」されたことが新しい事態であった。
これまで繰り返し述べたように、統一学校運動は現代社会の到来とともに起きた運動であり、その最も強力な基盤は帝国主義であった。第一次世界大戦によって教育を国力増強に利用しようとする利害から、体制的に支持されたのである。その立場から統一学校構想を提起したのがケルシェンシュタイナーであった。ケルシェンシュタイナーは、1854年に生まれ、シュバインブルト(Schweinfurt)とミュンヘンでギムナジウムの教師をしたあと、1895年から1920年までミュンヘンの市視学官を務めた。(1) ギムナジウムの教師時代、彼は特に自然科学の教育を重視し、人文教育が最も高い教育価値とされていた教育界に、新風を吹き込んだと評価されている。視学時代にはそこで彼は国民学校と継続学校の改革を試みた。
そして、1911年帝国議会の下院議員(自由党)となった。1918年ミュンヘン大学の員外教授(Honorarprofessor) となり、1932年1月15日に死亡した。(2) 政治家として派手な活躍をしたわけではないが、教育改革に大きな影響を与えた。
ケルシェンシュタイナーが教育改革の場面に登場するのは、「わが国の青少年は、国民学校卒業後兵役に服するまでの問、どうすれば公民社会に最も役立つように教育されるか」という1899年エルフルト王立公益科学アカデミーの懸賞論文への当選からであった。(3) これは1910年「公民教育論」として体系化される。
1890年、ウィルヘルム賖世がベルリンで会議を開き、社会主義への対抗策としての公民教育・政治教育の必要性を強調して以来「公民教育」という課題が展開してきていたが、(4) アカデミーの出題目的は、こうした事態をふまえ、義務就学期間を終えて、兵役に服するまでの数年間、犯罪者と社会主義者に陥ることのないように、国家公民として育成することにあった。つまり、1878年の社会主義鎮圧法の解除後、勢力拡大の著しかった社会民主党に対抗し、労働者のプロレタリア化を防ぐことが支配層の切実な問題だった。(5)
結局ケルシェンシュタイナーが教育界に期待されたのは、こうした政治的課題に応える「公民教育」の方法を提起したからであった。(6)
ドイツ教員組合が、1914年キールにおいて統一学校の要求を掲げたとき、統一学校について講演を行い、また1920年の全国学校会議でも、最初の問題提起者として登壇し、その後の議論は彼の提案を中心に展開した。そのような点から「統一学校運動」のもっとも有力なイデオローグはケルシェンシュタイナーであったし、その理論も、第一次大戦後の支配階層が、直面した課題に、支配的意識を前提に取り組み、その要求に応えたという意味でも、典型的な統一学校運動の理論家であった。統一学校の主張がはじめ「才能ある者に自由な道を」というスローガンから始まったことで理解されるように、当時広く理解された共通項は、あくまで才能ある生徒の進学保証ということであった。(7)
しかし、ケルシェンシュタイナーが最も中心的位置をもったのは、才能ある者だけを対象にすることなく、むしろより多くの普通の子に対する教育をひとまずは「公民教育」「労働教育」として軸に据えたからであった。
<註>
- Messer a.a.O. s107 メッサーは国民(Nationaltät)としての共同所属感情(Zusammengehörigkeitsgefühl)が崩壊したとしており、学校についてもギムナジウムは上層30%しか入学せず、事実上身分制学校になっていると批判している。統一学校はこうした国民の分裂を回避する試みとして考えられている。Messer a.a.O. s55-56
- Eike-Volkmar Kötteritz "Georg Kerschensteiner Arbeitsschule und die Arbeitslehre der Gegenwart" 1981 s55
- 藤沢法映『ケルシェンシュタイナー労働教育論』の解説 p145 高橋勝はケルシェンシュタイナーの作業教育論を、はじめは自然科学的観点から出発し、後に公民教育の視点がでてきた、とのべている。高橋勝「ケルシェンシュタイナーの『作業教育論』の形成とその特質」ケルシェンシュタイナー『作業教育の理論』解説明治図書 p40-41
- Messer a.a.O. s132
- Kötteritz a.a.O. s64-65
- Hohendorf "Die pädagogische Bewegung in de ersten Jahren der Weimar Republik" s65
- Ludolf Lehmann "Die Pädagogische Bewegung der Gegenwart ── Ihre Ursprüunge und ihr Charakter" 制度としてはマンハイムシステムがその典型であろう
(2)ケルシェンシュタイナーの公民教育論と労働教育論
<ケルシェンシュタイナーの「公民教育論」>
ワイマール憲法は、148条で公民教育について、次のように規定していた。
1.全ての学校においては、ドイツ国民性と国際協調の精神において、道徳的教養、公民としての考え方、個人的及び職業的有能さを身につけさせるように、努力しなければならない。
2.公立学校における教育にさいしては、考えを異にする者の感情が害されないように、考慮しなければならない。
3.公民科及び労働教育は、学校の教科目である。全ての生徒は就学義務を終わるにさいし、憲法の複製をうけとる。
4.国民大学をふくむ国民教育制度は、ライヒ、ラント及び市町村によって助成されるべきである。
これらの規定は正確にケルシェンシュタイナーの「公民教育」論に対応している。
ケルシェンシュタイナーの教育論は、公民教育(Staatsbürger Erziehung)と労働教育(Arbeitserziehung)を柱としており、それらが彼の統一学校の内容の中心である。しかもその二つは不可分の関係をもっている。このことは、彼の教育論は二つの現実的課題に直接取り組んでいたことを示している。
第一には、激化する階級対立・社会主義勢力の増大に対抗して、国家的一体性を保持すること。
第二に、科学・技術の発展に対して、どのように教育面で対処できるのか、ということの二点である。もちろんこのことは、帝国主義国すべての支配者が直面した課題であった。
「統一学校運動」は、第一の課題に対しては、様々な理念(ドイツ文化、キリスト教、国家的情操等々)を内面化させることで、一体性を保持し、労働者の中の特別優秀な者を支配層に取り込むことで、第二の課題に応えていこうとしたのである。
ただ注目すべきことは、ケルシェンシュタイナーの公民教育論が基本的に第一次大戦前、君主制下において形成され、受容されながら、世界で最も民主主義的といわれたワイマール憲法についても、またその下での教育の現状についても、具体的な考察がされることもなく、変更もされないままであったということである。(1) 逆に言えば、民主的ワイマール憲法が、君主制下の論理を取り入れたことになる。
1918年、11月革命により帝政が崩壊し、ワイマール共和国が成立したが、第一次大戦から、1923年頃まで、世界的に革命と反革命の闘争が続いた。(2) ドイツでは最も激しく闘われ、ついに安定することがなくナチス体制に移行するのであるが、一貫して彼はその基本的政治観を変えていない。
ケルシェンシュタイナーは戦前ドイツ帝国について、「歴史的にみれば、法治国家、文化国家への道を歩んでいる」と述べていたが、(3) 戦後は「国家権力が民衆にあるときは、民衆のあらゆる部分が国家公民的に感覚し、思惟し、行為すること」(4) が不可欠である、と主張して、共和制の擁護者として振舞っている。しかし、その認識は実は次のようなものであった。
11月革命の最中ケルシェンシュタイナーは、シュプランガーに手紙を書いている。
我々のまわりで、ボルシェビズムが勝利するとは信じていません。当分私はドイツ国民の品位のなさにづいて語り続けるでしょう。(5)
そして、アイスナー(Eisner)を幻想的ではあるが、無能だ、と決めつけ、革命への冷やかな感情をあらわにしていた。(6)
またケルシェンシュタイナーは、革命に対して純粋な民主主義よりは、制限された君主制の方がよいと明言して、社会民主党及び革命に反感を露にした。社会民主党に対する、こうした主張は一貫していた。
無思想的な勢力の持つ史的唯物論の逆らい難い圧力が、我々を納得させようとするのであるが、理想は常にその無思想な力よりも強力である。(7)
先述したように大戦前、既に最大政党になっていた社会民主党を取り込み、戦後の革命状況を緩和させるために、戦時中から形式的に平等な普通選挙の規定が考慮されていたが、そうした普通選挙法の施行によって、全ての国民が形式的に平等な「公民」として登場するという事態を迎えたことが、「公民教育」論者としてのケルシェンシュタイナーを登場させた背景でもあった。(8)
次に「公民教育」についてみていこう。ケルシェンシュタイナーは「公民教育」の課題を次のように述べる。
道徳的にも精神的にも凡庸な資質しかもちあわせていない人々が、政治に対して同じ様な関与を要求しないということ、彼らが高い価値の担い手を是認して、自由意思で彼らに随順すること、公民的教育をこのように構造化すること、このことが公民的教育の最も難しい課題なのである。(9)
共和制の実施、普通選挙によって否応なく全ての国民が政治の主体となり、その中こは「凡庸な」者も多い。彼らをいかに「従順な」状況に教化できるか、ここに明確に課題が設定されていた。言いかえれば、形式的に平等ではあるが、実質的に不平等な法的権利を受容させることである。
さて「公民」とは「国家の恩恵に対して奉仕する者」のことであって、(10)青少年を「公民」に形成していくのが「公民教育」に他ならない。
では、「公民」とはより具体的には、いかなる資質をもった者なのか。
まず第一に、国家の中で何らかの機能を果たす能力と意志をもつこと。有機体全体の中に位置づけられた一つの労働に、言いかえれば、一つの職業に従事し、それをできるだけりっぱに果たすことができること。
第二に、職業を公的任務とみなす習慣をもっていること。
第三に、労働を通じて国家に奉仕しようという性向と能力を発達させようとすること等である。(11)
国家という有機体の中で、何らかの機能を果たしていないものは、すなわち、直接にせよ間接にせよ、国家集団の目的にかなうような労働を何にもやっていないものは、だれ一人としてわれわれのいう有用な公民ではありえないことは、あまりにも明瞭である。精神的にも身体的にも健康で、国家秩序の恩恵を被っておりながら、このきわめて複雑な目的集団の中で、何らかの地位を占め、共同作業を遂行するにさいして、その能力に応じてたとえささやかな一翼にせよ、になっていないものは、単に有用な公民でないばかりか、そもそも非倫理的に行動している、とさえいわざるをえないのである。(12)
この考えは、ワイマール共和国の末期まで彼は一貫して保持していた。1933年に出版された論文の中では、彼は次のように主張していた。
全ての学校は、全段階において精神的な価値に依拠し、自由な労働共同体に分岐される中で、生徒が彼の行為によって単に倫理的な自己認識に達するだけではなく、同時に奉仕労働を通して、共同体の倫理を措定するように教育されなければならない。(13)
人間は一人で生きることはできないのであり、共同の労働によって生きることが可能となるのであるが、(14)それを組織する「国家」こそ、「最高かつ、もっとも完全な外的倫理的善」なのである。(15)
しかし、現実の国家は階級国家であり、しかも激しい階級対立が行われている。それも、ワイマール体制の成立は、同時にベルサイユ体制の成立でもあって、ドイツの労働者は、極度の生活難に苦しんでいた。だから全国民が自然に国家を最高の倫理的善と認めることなどありえない。それ故、彼は教育によってそうした認識をつくりあげようとする。しかも国家が善である、という命題自体を、彼は「前提」として提示することしかできない。(16)
つまりケルシェンシュタイナーは国家を前提として論議を演線的に志向しながら、具体的なワイマーレ憲法問題については何一つ発言しないのである。(17)ケルシェンシュタイナーの発言は次のようなものである。
正義的国家を信奉することを公言しているところの大きな政党のいずれからも殆ど躊躇なく迎え入れられるような、そういう公民的教育の典型が存在するということ。及び、この典型を追求することは、いわば、われわれが新しい国家の存続と発展という見地から、またその国家の経済的な力や文化的な力の向上という見地から、国民の教育に切に望まなければならないような事柄に通じるものなのである。(18)
すなわち国家とはあくまで「理念」に過ぎない。
もちろん彼において、共同体の最高形態が国家であることはいうまでもない。つまり、国家という有機体の中で労働(職業)を行って奉仕することを彼は要請するのであるが、労働によって人々は自己を実現する、(19)という認識を導入することによって、国家への奉仕が個人の自己実現と予定調和を作り上げる。と同時にそこに「個人的教育学」と「社会的教育学」の分裂を克服する契機を見いだすのである。(20)
<註>
- Scheibe a.a.O. s251 藤沢法膜によれば、彼は戦前はユンカーではなく、ブルジョワジーの代弁者であったが、このことの故に、戦前戦後を通じて彼の教育論は根本的変更を迫られることがなかったといえる、藤沢法膜『ケルシェンシュタイナー労働学校論』の解説論文参照
- 斉藤孝「1920年代の世界」『岩波講座世界歴史』26 p63
- Kerschensteiner "Gegriff der Arbeitsschule" s1 この論文は1911年執筆である。
- Kerschensteiner "Staatsbürger Erziehung" 1926 s3
- 1918通12月19日のシュプランガー宛手紙。"Kerschensteiner ── Spranger: Briefswechsel" 1966 s144
- a.a.O. s145
- 1918年10月18日のシュプランガー宛手紙。a.a.O. s138
- Scheibe s235 大きな流れとして国民教育制度と普通選挙の関連については堀尾氏が分析している。『現代教育の思想と構造』参照
- ケルシェンシュタイナー『公民教育の概念』 p150
- Kerschensteiner "Gegriff der Arbeitsschule" s12
- Kerschensteiner a.a.O. s12-13
- 1911年10月6日の演説 ケルシェンシュタイナー『作業学校の理論』 p113
- Kerschensteiner "Theorie der Bildungsorganisation" 1933 s50 ケルシェンシュタイナーの公民教育論と国家有機体説の関連については、堀尾前掲
- Kerschensteiner "Gegriff der Arbeitsschule" s4
- a.a.O. s2 シャイベはこういう国家認識はパウルゼン(Friedrich Paulsen)の影響であると指摘している。Scheibe a.a.O. s237
- a.a.O. s10 ケテリッツはケルシェンシュタイナーの国家認識はへ一ゲルに依拠していた、と書いている。Kötteritz a.a.O. s68
- この点はシャイベも指摘している。Scheibe a.a.O. s237
- ケルシェンシュタイナー『公民教育の概念』 p12-13
- Kerschensteiner "Gegriff der Arbeitsschule" s63 ケルシェンシュタイナーの労働教育論については、ほとんど教育学的理解、つまり、性格形成・労働能力の育成・自立性の促進等というレベルで捉え、国家公民としての面を重視しない理解もある。Wolfgang Scheibe "Die Reformpädagogische Bewegung" 1969 日本では大谷光長『ケルシェンシュタイナー教育学序説』
- しかし、このことをもって「職業教育をとおして、全人格陶冶をはかろうとしたことは、現在の職業陶冶や一般陶冶の在り方についても多くの示唆を与える」というのは、明らかに誤りであろう。つまり彼にとって労働教育・職業教育は決して一般教育なのではない。彼の労働教育論は、ほとんどが国民学校を対象としており、ギムナジウムは抽象的には同じ「労働教青論」であっても、その内容は従来の人文教育なのであった。宮本仁宏「公民教育と職業教育ケルシェンシュタイナーを中心として」中国四国教育学会編『教育学研究紀要』四巻、1958
<ケルシェンシュタイナーの労働教育論>
ケルシェンシュタイナーの「公民教育」は「労働教育」と直説的に結び付いていた。ケルシェンシュタイナーの統一学校論が、多方面に支持された理由はそこにあった。彼が体制的に受け入れられたことは、その経歴からみてごく自然であるが、社会主義者の一部にも支持されたのは、労働による陶冶を「公民教育」の土台にしたからである。例えばSPDの学校妥協を批判し、「徹底的学校改革者同盟」を組織し、一貫してその中心人物であっP.エストライヒ(Paul Oestreich)ですら、一時期ケルシェンシュタイナーを高く評価した。エストライヒは完全に自分と意見が一致すると断わった上で、次のようなケルシェンシュタイナーの文を引用している。長いが全てをここに引用しておこう。
陶冶の目的が、第一の観点からすれば、客観的価値の充溢した存在、即ち無限の人間性理念の実現をたゆみなくめざす人間にあるとするならば、第二の観点においては、それは精神的機能の完全な状態、即ち固有な諸力の一体系としての精神的有機体が最大の能力を発揮することにある。いずれの陶冶もそのねらいを子弟の心的存在、その本質的存在においている。両者は言葉の正しい意味において『一般陶冶』と言われていることに該当する。なぜなら、一般陶冶というのは、その本質の目的からいって、全ての人間に対してまったく普遍的に主張することのできることがらであるからである。
この概念の擁護者たちによれば、一般陶冶を行うということは、個人の素質を全く顧みずにまとめられた特定の教養財の体系を完全に習得させることであるという。しかし、陶冶とはいかなる場合でも、生来各人に芽生えているところのものに働きかけてなされる固有な人格形成なのである。したがって、自己を形成するためには、誰でもこの自己の特性の故に、独自の道を歩まねばならない。ところで、そのことは、個人が共同社会を離れては存在しえない以上、個人が共同社会の生活において無条件に負わなければならない課題から離れてはありえないし、また生命を維持する上で欠くことのできない物質生活そのものの課題から離れてはありえないものである。生きるための闘いは、何はともあれ有用な人間を必要とする。それは二重の意味における『職業陶冶』を必要とする。即ち自己の生計を立てるのに役立つ労働に対して訓練すること、及び共同社会を維持するために役立つ労働に対して準備すること、それ故専門陶冶と公民陶冶(目的論陶冶目的)とを必要とするのである。この『職業陶冶』に人格形成行為としての意義をもたせるとするならば、職業陶冶は生まれつきそれにたずさわるのに適しているような職業へ向けて陶冶することでなければならない。それ故、職業と心的構造とが調和しなければならないし、また、全ての陶冶は自分自身の興味からなされる自己形成でなければならない。
陶冶活動が全体として確実に行われるためには、三つに分類された陶冶概念の相互の間に統一が保たれていなければならない。つまり、人間陶冶は最高の目標を、職業陶冶は最適な道を、一般的な精神能力の育成を図る形式陶冶は最適な道をたどって最高の目標に到達するためにぜひとも必要な確実な方法を与えるものということである。(1)
ここで、エストライヒは個人の陶冶という側面からのみケルシェンシュタイナーを評価している。つまり、古い学校における固定的な教育を打破して、個性に適したより柔軟な教育原理を示した、というわけである。しかし、統一学校運動における「有能な者に道を」というスローガンが「各人をあたかも一つの物体として国家機構にはめ込んでいく公民教育という考えが、時代とともに有力になって」きたことを、批判的に指摘しながら、それこそケルシェンシュタイナーの公民教育論の本質であったことに目を塞いでいる。(2) ケルシェンシュタイナーの個性の開花という言葉は、シュプランガーの人間類型に似せながら、実は、階層的に分類された人間観に基づいていることでわかるように、決して全ての人間の平等な個性の陶冶ではなかった。
次にケルシェンシュタイナーの「労働教育」の構造をみておこう。
ケルシェンシュタイナーは、個人を「内的善」と呼び、国家を「外的善」としている。(3) つまりこの二つの「善」を発展させることが、彼の価値的立場ということになるが、全て人間は一人では生きることができない。そこで共同体が必要になるのだが、その共同体の最高の形態が国家であることは断わるまでもないであろう。そしてケルシェンシュタイナーの場合、国家は抽象的なレベルにおいて、論理としては提示されているが、しかし、現に生きている国家そのものを体制的に支持しているのである。ケルシェンシュタイナーは自分の論理に対する誤解の代表的な例を次のようにあげている。
最高の外的善の倫理的理念を実現するための教育を、現在の国家に十分な理解をもって奉仕することと解するのではなくて、教育を永久的に固定された国家有機体に盲目的に奉仕することと解する誤りである。(4)
現在の国家がケルシェンシュタイナーにおいては、第一次世界大戦前の君主制とワイマール共和制とが、無媒介的に同列におかれていることは、先に指摘した通りである。
国家に奉仕する公民を育成するのが、教育の大きな目的であるが、では学校の課題はどの様に整理されるのか。「義務教育学校」の課題として三つをあげている。
1.職業教育ないしその準備という課題
2.職業教育の倫理化という課題
3.そのなかで職業がいとなまれる共同体の倫理化という課題(5)
1が「労働教育」であり、3が「公民教育」、そして2がその媒介であることは明瞭である。
さて、ケルシェンシュタイナーの「労働」は、二重の意味をもっていた。労働共同体(=国家)の中で一員になるという情操(Gesinnung)と職業そのものとである。当然、労働教育も二重の意味をもっていたのであり、それは「公民教育」の一一部面であり、個人の陶冶という側面のみでみることはできない。
つまり、ケルシェンシュタイナーにおいては、「分業」が有機体の一環として捉えられ、「職業」意識が、全有機体の自覚につながることによって、社会的分裂が克服されるという論理的オプティミズムがあった。
ノールによれば、労働教育の源泉は二つあった。
第一に、市民革命に由来するものである。ペスタロッチから始まり、自已活動性や共同体感情の育成とともに、経済的課題に応えることが意図されていた。ケルシェンシュタイナーはこの代表である。(6)
ケルシェンシュタイナーはここに自然科学的視点を加えた。
第二は、社会主義の労働教育である。ノールによればマルクスに始まったこの思想は、ワイマーレにおいてはザイデルによって発展していた。(7)
ケルシェンシュタイナーの「労働教育」が、社会主義的労働教育の防御のためのものであることは、「公民教育」の目的から当然であるが、しかし、それにも関わらずエストライヒのような統一学校論者の共感をえたのは、「労働教育」が当時の学校の欠点をよく踏まえていたからである。
ケルシェンシュタイナーは当時の学校の在り方を次のように批判する。
われわれの今日の学校は、よそよそしい知識を伝達することによって、緩慢にしか発達しない経験的知識を、できる限り手際よく速成栽培するための国家の道具でしかない。それはまた、あらゆる文化にとって特に重要な機械的技能を、できるだけすばやく獲得させるための国家の道具である。(8)
これに対して、ケルシェンシュタイナーは自分自身の経験によって獲得する知識をより本質的なものと考え、そうした教育を育成するために生産学校を提起する。
しかし、生産学校は、国民経済学的あるいは物理的な意味で考えられてはならない。(9)
では生産的な学校とは何か。
精神の生活のより高次の統一、もしくは心の生活の外的現れとその自己実現のΦために、新しい表象や表象連合をつくりだすところの心の活動である。(10)
しかし、こうした作業には素質が必要であると念のためケルシェンシュタイナーは断っている。(11)
ケルシェンシュタイナーはこうした作業を能力の発達の構造と結び付ける。
ところで、手をはたらかす職業のために準備する教育の目的は、特定の職業の労働の過程、道具、機械及び材料について手ほどきをすることにあるわけではない。 ── そのめざすところは、職業に従事していく上に必要な器官を形成することであり、たえずより慎重により徹底的により見通しをもってするきちんとした労働方法を身につけさせることであり、正しい労働の喜びを喚起することである。(12)
そして系統的な仕事によって身につけた能力は、将来いかなる職業につくにしても、適用可能であるとする。(13)
つまり、ケルシェンシュタイナーは転移を考慮にいれて、「労働教育」の内容を構想している。したがって、その内容は、肉体労働と精神労働を結合して考えており、古い人文的教養観をその限りで乗り越えているのである。
われわれが注意すべき第一の点は、手をはたらかす活動がいかに多くの関心、熱意、努力、行為と結びついていようとも、それが教育的な意味での労働たりうるのは、精神をあらかじめはたらかすことの発露である場合だけである。(14)
そこでケルシェンシュタイナーは教養概念の検討に移る。
教養とは「文化財すなわち正当な価値にたいする人間の積極的な姿勢」がケルシェンシュタイナーの「教養」であるが、その指標として次の5点を整理している。
1.事物の有価値性、価値の意味、価値の関係に関する精神的地平の一定の広がりと多様性
2.新しい価値を理解し、その価値を実現していく際の、一定の能動性、開放性、積極性
3.こころに価値を育もうとする要求及びこの要求を、自分自身のこころという内なる存在であれ、外なる世界であれ、その形成に際してたえずはたらかすこと
4.手段と目的、原因と結果、部分と全体などの関係にある事物の価値関係を柔軟に結び合わせること
5.無条件に正当な価値にもとづいて評価する体系ができる結果、心に中心ができていくこと(15)
このような条件を満たした教養をもって、経験的・理性的に自己点検していくことが、「労働教育」の個人的な目的になるのである。(16)
これでみる限り、ケルシェンシュタイナーの「労働教育」は正当だと評価した社会主義者がいても不思議ではない。
しかし、現実にある労働は機械の奴隷のような労働である。(17)そこで彼は次のように言う。
彼等にもう一度価値ある生活を与えよ(18)
では何がそれを与えるのか。部分的には宗教・芸術・学問・パンである。しかし、それは非常に限定されたものにすぎない。より強力なものは、学校における「他の人々を世話すること」、ここに生活内容、生産的作業の源泉がある。(19)
機械のような労働に対して、社会主義的労働教育論は児童労働の保護を、不可欠の要素として主張した。そして不十分ながら、労働そのものの人聞的な形態への転換を模索した。しかし、ケルシェンシュタイナーは「教養」ある者のみが可能な形態しか提示しない。そして、多くの「機械的労働」から当面は逃れられない人々は「共同体」に対する奉仕という喜びに収斂させてしまうのである。
「労働教育」に「公民教育」が不可分の関係になっているのは、そのためである。
<註>
- エストライヒ『弾力的統一学校』1921 中野光他訳 明治図書 p13-14 カルゼンはガウディッヒと比べて、ケルシェンシュタイナーを自然科学者の観察活動がもっている価値に注目することろから出発し、作業の協同を目指した偉大な教育家として評価している。カルゼン『現代ドイツの実験学校』小峰総一郎訳 明治図書 p134 カルゼンは銘記しているわけではないが、労働学校の有名な教育家としての二人、手に頼ったザイニヒ、頭に頼ったガウディッヒに対し、この二つを統合したケルシェンシュタイナーという評価を与えているようである。
- 同上 p15
- ケルシェンシュタイナー『労働学校論』 p38-39
- 同上 p44
- 同上 p51
- ノール『ドイツの新教育運動』 p131
- 同上 p140 しかし、ノールは双方とも、生活の「仲間的」要素が強調され過ぎて、「支配的」秩序が忘れられている、と批判している。 p148
- ケルシェンシュタイナー「生産的作業とその教育的価値」1906 『作業教育の理論』 p65
- 同上 p68-69
- 同上 p73
- 同上 p74
- 同上 p58
- 同上 p58
- 同上 p62
- 同上 p75-76
- 同上 p86
- 同上 p82
- 同上 p82
- 同上 p84-85
(3)ケルシェンシュタイナーの統一学校構想
<ケルシェンシュタイナーの統一学校構想>
さて、彼の「公民教育」「労働教育」論の意義を「統一学校」構想との関係で更に検討してみよう。
ケルシェンシュタイナーは、統一学校の具体的制度として、次のように考える。
ケルシェンシュタイナーの学校構想図
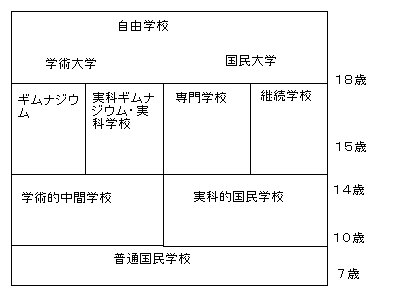 Saupe s.18
Saupe s.18
当時の学校の最大の問題は、学校の分岐が個人の才能によってではなく、親の社会的経済的地位によって行われることである。それ故、個人の才能によって進学が決められることを実現することが統一学校の目的であるとされる。(1)
19世紀末から、「工業学校(Gewerbeschule)」が衰退し、その代わり「実科学校(Realschule)」「上級実科学校(Oberrealschule)」「実科中等学校(Realgymnasium)」などが出現し、先述のように、「学校戦争」なる状況がおきたのであるが、彼はこうした状況をとらえ、それが自然科学の発達によって促進されたものと評価し、統一学校の問題を中等段階の問題を中心として考察したのである。(2)
しかし、この時代には、まだ自然科学の成果を教育に取り入れるということが、決定的に重要な要因になっていないことも事実である。「自然科学的統一学校」を主張したハインリッヒ=シャハトですら、その要求は次のようなものであった。
1.陶冶という方法によって、統一学校は、全ての階層の全国民を精神的、倫理的にまとまった全体へと結合させるべきである。
2.統一学校は、自然科学的性格を加えて、国家的な国民学校として、公民・世界市民としての教育を行なうべきである。
3.統一学校は全ての人の平等の思想を現実化するものである。(能力による進学)
4.統一学校は党派に奉仕すべきではない。(3)
つまり、自然科学の教育というより、むしろ国民の一体観や選抜の合理化の要素が重視されている。
このような状況によって、支配層も大戦中から次第に、才能ある人問に中等段階の教育を受けさせる必要があることを認識するようになっていた。1917年9月18日、内閣は「全ての才能ある者(Tüchtigen)に自由な道を」という政策を以降とると声明したことにそれが現れている。戦争の打撃がこのように決意させたのである。(4)
1920年の全国学校会議では、統一学校の支持者から同主旨の意見が多く語られた。著名な者はテウスであったが、(5) 支配層による改革の意図を大胆に語ったのは、レーベンシュタインであろう。彼は、統一学校を支持して「革命は必要である。しかし、資本主義にそった革命、つまり、増大するプロレタリアートに歴史的・経済的・文化的位置を提供するということである。」と述べた。(6)
ケルシェンシュタイナーは、こうした状況をふまえて、全ての国民が通う基礎学校をおいたのであるが、だからといって、彼は科学的な教育を全国民的なものにするため学校改革を考えたのでもなかったし、全てに平等な教育を保証しようとしたのでもなかった。教育内容について彼は、「個々人に適した教材・教育内容を」{■というスローガンを述べたが、それは能力の「先天的資質論」によって裏打ちされていたのである。彼によれば、子供の才能は量的・質的にはじめから異なっているのであるから、I出幼稚園のときから分けてもよいのである。しかし、10歳頃までは、適性は自覚されるものではなく、又、差異に対する家庭環境の作用も大きい。そして、発達の差は大体量的にのみ現れるので、4隼間の「基礎学校(Gmndschu1e)」に全ての国民が通い、lO歳から11歳に明瞭になる才能の差によって、その後で分岐する。舳しかし、彼の論理から、基礎学校に於て既に特別優れた才能を見せた者は、例外的に早く(3年で)中等学校に進学することを認めることは当然であった。(10)
<註>
- Reichsshulkonferenz 1920 s117
- a.a.O. s118 Gewerbeschule は現代語と実科を教える学校で、プロイセンに1799年に設立された Gewerbe-Institut が発展したものであり、19世紀前半に急激に増加した。二学級制で教える内容は、数学・物理・化学・ドイツ語が主要な内容であった。それが、1870年前後に規模が拡大し、実習なども重視されるようになって、カリキュラムにも地理・歴史などが加えられ、ラテン語のない Realschule や Oberrealschule になっていった。Rein "Enzyklopädisches Handbuch der Pägogik"
- Heinrich Schacht "Die Neugestaltung unseres Bildungswesens" 1920 s4-5
- Rein "Zur Neugestaltung unseres Bildungswesens" 1917 s2
- Reichsshulkonferenz 1920 s148-149
- a.a.O. s519
- a.a.O. s118
- しかし、この判定は難しい。当時からそうした批判があった。Karl Roller "Die Einheitsschule ── Ein Vorschlage zur Lösung des Problem" 1919 s20
- 子供の素質が年齢によって変わりうることが明瞭になってくると、ケルシェンシュタイナーの論理は崩れざるを得ないであろう。同様の批判として Bastian Schmidt, Max Brahn "Das neue Deutschland in Erziehung und Unterricht" 1919 s45
- a.a.O. s120 Gerd Hohendorf "Die Pägogische Bewegung in den ersten Jahren der Weimar Republik" 1954 s72
<適性と選別>
では、質的量的差はどのように現れるのか。彼は次のように人問のタイプを考える。
a.少数の理論的に優れ、知的労働に就く者
b.実際的才能の後に理論的才能を出す者
c.実際的才能を持つ者
d.芸術的・商業・社会的才能を持つ者
e.特別の才能を持たない大部分の者
である。そして、タイプと学校を次のように対応させるのである。
a.古典ギムナジウム
b.実科ギムナジウム・技術ギムナジウム(Technische Gymnasium)
c.d.中間学校(Mittelschule)
e.国民学校(Volksschule, Bürgerschule)
そしてbのために移行を可能とする措置をとるのが、ケルシェンシュタイナーの中等段階の学校構想である。一方で、彼は明確にシュプランガーの影響を受けながら、理論的志向の人間、美的志向の人間、技術・実際的志向の人間というように、人間類型論を示し、それぞれの個性を教育の課題として措定するのであるが、しかし、シュプランガーと異なって、徹底的に階層的な発想がなされている。つまり第一の理論的志向の者のためには、理論だけではなく、芸術・社会・国家・宗教の文化が導入される。第二の技術的・実際的志向の者には技術に加えて科学・芸術・社会的文化が導入される。そして、美的志向の者には、文化のみが言われている。(1) ここに見られる内容は、逆に彼の中等段階の各種学校への期待が同価値なものでは決しでないことを示しているだろう。それ故ケルシェンシュタイナーにおける「全体性原理(Totalitätsprinzip)」は、いかに教育において重要な原理だとされても、(2) それは、第一の理論的な志向・才能を持った者にしか、実際は期待されていないのである。(3)
引しかし、教育学理論である限り、それで国民全体を包括したものにはなりえないことは明白である。それ故、ケルシェンシュタイナーは次のように補完をするのである。
個々人の特殊な教育可能性の基準によって共同体の教育施設を用いて、可能な精神的な形態に達する道を満たすことは、個人の倫理的な権利(sittliche Recht der Individualität)である。(4)
即ち、階層的分化への教育が権利であるとケルシェンシュタイナーは言う。
さて、能力が先天的に規定され、それを発見して選抜していくのであるから、各々における労働教育の内容は当然異なっている。彼の「労作教育」として知られる手の労働による教育は、国民学校を主たる対象としているものであり、もっぱら知的職業に就く中等学校では労作教育は必要ないとされた。(5) ところが一方、そうした国民学校では自主的な思考は限定されてしまい、中等学校こそが真の「労働学校」となりうるのであった。(6) 彼の能力論は「大衆蔑視」と結び付いていた。
全ての文化国家にあっては、民主主義的な傾向が絶え間無く進行中である。しかしながら、その市民の多数の精神状態が貴族主義的でないならば、民主主義的な諸国家の状態は、愚民統治へと向かうことになるであろう。(7)
ケルシェンシュタイナーが既存の中等学校についての批判意識をもっていなかったことは、ギムナジウムを9年制として維持すべきであると主張していることからもわかる。(8) ギムナジウムをより大衆的なものにするために、年限の短縮が必要であるとする運動があったことを忘れるべきではない。(9)
知的能力が、個人的に差があることを前提にしている点では、ナトルプも同様である。ナトルプは、人間は知的能力については差があるから、その面に関する限り、統一学校は望ましくない、としたのである。彼の統一学校の根拠は、学校は知的教授(Unterricht)のみを行うところではなく、訓育も行うところであり、人間は道徳的には平等である、というところに求められた。(10)このことは、古典的な「教育の自由」(=徳育や学校選抜に対する親の権利)を制限することでもあり、ナトルプは、だから、「教育の自由」に対する国家介入の擁護者でもあった。(11)
さて、ここで、一つの大きな問題が生じることになる。基礎学校を全ての者が通うことにするというのも、「才能ある者(Begabtem)」を正確に選び出すためである。(12)ナトルプが「誰に天分があり、誰にないか、ということではなく、誰には何の天分があるか、ということでなければならない」と言ったところで、学校や進学数が飛躍的に増加するのでなければ、その意味するところには変わりはない。選抜の方法について、ケルシェンシュタイナーは明確に述べていない。しかし、それが「形式陶冶説」と「先天的能力説」に裏付けされていることは明らかである。彼は「転移」を承認しており、(13)また、中等学校における「労働教育」の中心を古典語の翻訳労働においているのである。(14)
彼の労働は、共同体の一員としての「自己実現」ではあったとしても、能力が先天的に決っていれば、それを発見することがまず問題となるであろう。
ビンダーが、全国学校会議で述べたように、統一学校運動のイデオローグは、ここに「教育科学の役割」を期待した。(15)
ワイマール憲法146条3項は、実はこのことの法的確認であった。貧しいが才能ある者の進学を保証する責務を公的機関に課した規定、という意味において理解されたのではなかった。より本質的な意味は「上級学校に進学する能力」があるかないかを判定することについての公的介入だったのである。V.ブレットは解釈として次のように書いている。
とにかく、国民学校教師は、決定的な内容を話す。しかし、それが親にとって不満なものであっても決して親の権利を直接侵害するものではない(16)
結局、ケルシェンシュタイナーの能力観は、能力が身分的=階級的に規定されているという能力観を個人のレベルに分解したものであって、いわば「階級的に純化」したにすぎない。しかも最小限の変更であって、古典語の修得を中心にした形式陶冶説すらうちやぶられていなかった。
このような普通基礎学校の構想は、容易に保守層と妥協せざるをえない。統一学校の消極論者だったブロックは、「才能ある者に道をひらく、ということはよいが、普通国民学校でなければそれができない、ということはない」と主張したが、「予備学校」の廃止に反対するこうした強い主張に対し、ワイマール体制は、妥協を重ねたのであった。(17)
では、ブロック的な統一学校論はどういう構造をもっていたのか。視学官のフリードリッヒ=ローメルは、国の難事を救い、学校間の移行を認めるために、統一学校を支持する。(18)ギムナジウムも、上級2学年の35%は学校を去ってしまうという危機的な状況であった。しかし、ローメルは、教育によって国民の統一性をつくることは不可能であると考え、むしろ多様性の増大こそ教育の進歩であると考える。(19)つまり教育の課題は、教養を与え、文化を促進することである。(20)そこから、基礎学校を3年で終了しうるにようにするべきだと主張することは自然であろう。(21)ローメルはナトルプやラインの主張する6年の基礎学校では、ギムナジウムを3年短縮しなければならないではないか、と批判するのである。6年制のギムナジウムでは、充分な古典語の学習ができないという理由である。つまり、ローメルにとって、技術教育の視点は、全くないのであって労働教育を重視するケルシェンシュタイナーに疑問を投げかけるのである。(22)
ケルシェンシュタイナーの素質に基づく選抜の論理は、こうした統一学校批判の論理を結局容認するのである。
<註>
- Kerschensteiner "Grundaxiom des bildungsprozesses" 1924 s42
- Kerschensteiner "Theorie der Bildungsorganisation"1933し36 この点については、ケテリッツも指摘している。Kötterlitz a.a.O. s65
- 大谷氏の全体性原理の理論はこの点を見落としている。大谷前掲参照
- Kerschensteiner a.a.O. s84
- Kerschensteiner "Gegriff der Arbeitsschule" s20
- a.a.O. s91 このような自然的素質から、不平等な選抜に結果するケルシェンシュタイナーの論理を指摘したものとして、堀尾前掲 p251
- Kerschensteiner "Grundaxiom des bildungsprozesses" s180
- Peter Petersen "Den Kampf um die Schuldauer" 1921
- P. Natorp "Die Einheitsschule" s3
- P. Natorp a.a.O. s11-12 ワイマール憲法は144条で国の監督を規定し、146条で教育権者の意志の尊重を規定した。これはワイマール憲法の「社会化」規定の暖味さを示すものといえよう。
- Kerschensteiner "Grundaxiom des bildungsprozesses" s24
- Kerschensteiner a.a.O. s101
- Binder の発言。Reichsshulkonferenz 1920 86 シュテルンは知能の定義を「知能とは思考を意図的に新しい要求に合わせる個人の一般的能力であり、生活の新しい課題や条件に対する一般的精神的適合能力である。」とし、それを内在的であると前提している。 William Stern "Die Intelligenz der Kinder und Jugentlichen" 1920 s2-11 そして、知能の分類を、特別劣った者3%、劣った者22%、普通50%、優れた者22%、特別優れた者3%、としており、これまで心理学は選抜に使用されてこなかったが、統一学校の中で使われることを勧めている。Stern a.a.O. s168,249
- Victor Bredt "Der Geist der Deutschen Reichs" 1924 s307
- Rudorf Block "Schulfragen der Gegenwart. Einheitsschule und anders" 1916 s14
- Friedrich Rommel "Einheitsschule und humanistische Bildung" 1919
- Rommel a.a.O. s11
- Rommel a.a.O. s9
- Rommel a.a.O. s17
- Rommel a.a.O. s32
(4)国家有機体説と教育の自律性の否定
<ナトルプの統一学校論>
ケルシェンシュタイナーは共同体、そして外的善としての国家へ国民を入れ込むことを、統一学校の目的としていた。しかし、現実には、ワイマール共和国は、資本家の支配する階級国家であり、激しい階級闘争に直面していた。(1) そこで階級矛盾を緩和しながら階級支配を確保するという課題に対し、彼は階級に代わって、「指導者」「披指導者」という概念を導入し、(2) その二つを結び付けるものとして、「統一学校」を主張するのである。
しかし当時、統一学校にすると「自覚したプロレタリアートによって、階級対立が激しくなる危険がある」という危倶が、統一学校の支持者にもあった。(3)
そうした意見に対して、彼は次のように答えている。
国家の中では、人間は指導者と指導される大衆とに分かれるのだから、国家という労働共同体は壊れてしまった方がいいなどという者がいるだろうか。論理的に考える者なら、誰でもこのような現実こそ、まさに学校に労働共同体を導入する根拠なのである。(4)
社会的教育学を主張したナトルプの場合、「統一学校」を国民の一体性を保持する手段とする考えは、より一層はっきりしている。(5)
ナトルプは、実際は純粋な身分学校(Reine Standesschule)が理想であるが、大戦後の当時にあってはそれが不可能であるので、統一学校を主張するのである。(6) それ故、彼は混乱した社会への現実認識と、彼の観念的理想との矛盾を克服することが、彼の理論の主要な契機となっている。
ナトルプの統一学校構想をみておこう。彼の特徴は基礎学校が5年制(乃至6年制)であること、中等学校の前期課程を分化しない共通課程として考えていることである。つまり、彼においては、統一による「一体感の酒養」という意識が強いのである。
ナトルプの前にある現実は、敗戦後の混乱と、革命をめぐる激しい政党間の争いであって、彼の国家認識はそれ故、リヴァイアサン的なものであった。(7) そこで、彼は「非政党的な判事席」が必要であると判断し、統一的な国家が求められた。(8)
一方、ナトルプによれば、社会の理想は、自由な個人の自由な社会であり、当然それは「自治」の能力を必要とする。(9) しかし、多くの大衆(=群衆)は凡庸なるものが支配している。(10)ケルシェンシュタイナーと同じく、ナトルプにも抜きがたい大衆蔑視があった。
リヴァイアサン的な国家観と自由な個人による社会という両立しがたい認識から、新たに導き出されたのが、「国家の指導者」と「全ての国民」という観念であって、その二つを共につくり出すのが、階級的教育を廃棄した統一学校であった。(11)請うまでもなく、彼の廃棄しようとしたのは階級的=身分的学校体系に他ならなかったのであるが、彼よれば、「統一学校」とは次のように定義される。
組織に関して、これから一つの共通の基礎学校、一つの豊かな節をなしていながら、であればこそ厳しく有機体的に統一された万人のための大学、すなわち真の『総合大学』という要求が帰結する。(12)
先にみたように、ナトルプは知的教授ではなく、道徳的訓育で統一を行うのであるか、ら、その内容は「宗教」でしかありえない。しかし、宗教は宗派に分かれているから、宗教教授で統一するということは、現実的にはありえないことであった。(13)
このような考え方で、徹底した人々は、全ての宗派に共通したキリスト教を教える、という考えに至るが、それも現実的ではなかった。したがって、「宗派混合学校」(宗教を正科として、宗教の時間は分かれる)の主張者は、国民の一体性確保を、共に学ぶ時間を長くするとうことで実現しようと主張したのであり、ナトルプやラインは5−6年制の基礎学校を提起したのである。(14)
こうした主張は、宗派学校の点で、そして、六年制基礎学校でも敗れることになった。
<註>
- ドイツ帝国の経済構造の規定、特にレーニンの「ユンカー的=ブルジョア的」という規定をめぐって、又ドイツ革命の性格をめぐって論争があるが、ここではそれを踏まえた規定としていっているのではない。そこまで立ち入ることはできなかった。ただ最低限、ワイマール体制でユンカー勢力が衰え、ブルジョアジーが決定的な地位を占めたことは確認できるであろう。そして、ケルシェンシュタイナーがブルジョアジーの立場に立っていたことは、前述したとおりである。
- 1926年の『公民教育の概念』において彼は国家と個人が権力と自由をめぐって二律背反関係にあることを承認せざるをえなかった。
- Binder の発言、Reichsshulkonferenz 1920 s90
- Kerschensteiner a.a.O. s67
- レーマンはナトルプの社会的教育学を「共同体の中で、共同体を通して、共同体のために」と要約している。Lehmann "Die pägogische Bewegung der Gegenwart" 1922 s53 また細谷は「共同体による教育、共同体への教育」という二側面で把握している。細谷恒夫『ディルタイ・ナトルプ』大教育家文庫 岩波書店 昭和11年10月30日 p196 レーマンはナトルプ的社会的教育学の本質的性格を「自由な意思による服従」を求めているところに見た。Lehmann a.a.O. s56
- P. Natorp a.a.O. s9
- ナトルプ『社会理想主義』 p163 この点ケルシェンシュタイナーと同様である。
- P. Natorp a.a.O. s3
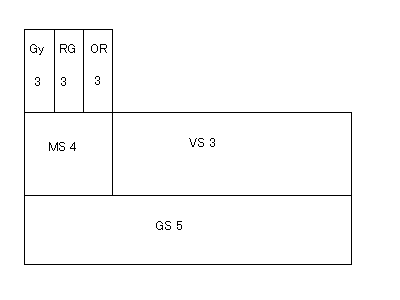 Fock s125
Fock s125
- ナトルプ前掲 p149
- 同上 p147
- Karl Vorländer 'Die Lebensarbeit Paul Natorp' in " Die Gesellschaft ── Internationale Revue für Sozialismus und Politik" 1925 s82
- ナトルプ前掲 p153,166
- 細谷はナトルプが現世的批判を重視した点に宗教教授批判の根拠を求めている。つまり、宗教はどうしても教義の強制的な注入によるドグマになるので、宗教教授の中で、「絶対性」を排除すべきだ、というのである。細谷前掲 p218-219
- 同上 p177 シャイベは代表的な教育論者は、6年から8年を主張したと書いているが、社会主義者を除いて、8年の基礎学校を主張した者はいないと思われる。Scheibe a.a.O. s263
<ケルシェンシュタイナーと宗教教授>
ケルシェンシュタイナーはこの点でナトルプと違っていたといえよう。彼の統一の軸は、労働教育とドイツ文化であった。ケルシェンシュタイナーは学校と宗教の問題については、極めて近代的であった。
国家は教会を国家的事項には混合せしめない。 ── 同様に私的社会は国家事項の中に自らを混合しえない ── 私的社会の組織体としてのみ見倣すということに、国家と教会の分離について国家は表現する。国家はそれだからといって、宗教共同体を一段低く考えるということでは決してないのであって、それはアメリカ合衆国の事例に明白にしめされている。(1)
中等学校の古典文化に執着する人々が、ラテン・ギリシア文化とドイツ文化の関連に苦悩し、また、宗教を倫理の最高形態とみる人々が、国家と宗教、統一学校における宗派の問題に悩んだのに対し、(2) ケルシェンシュタイナーはドイツ文化と労働を主軸とした公民教育を土台に据えることによってそうした「苦悩」から解放され、学校と宗教についての近代的原理、宗教の私事性を主張し得たのである。
このことの歴史的意味は、資本主義の柔軟性が、社会民主主義者のブルジョア教育理解のはるかかなたにあったということをも意味しているのである。つまり、SPDが第一次大戦前、1906年のマンハイム党大会で国民教育についての議論を行ったとき、ブルジョア教育の第一の特質として、宗教倫理に基づく教育であると規定したのであるが、(3) SPDにとっては、宗教倫理からドイツ国家精神へと重点が移行していくことが、充分に把握されていなかったのである。統一学校運動が、学校制度の帝国主義的再編の試みである限り、ドイツ文化を統一の軸とする考えは強力であった。テウスですら、ギムナジウムやリツオイムに「ドイツ」という語が冠していないことを非難して、全ての学校に「ドイツ」という語を付けることを提起した程である。(4)
結局、ナトルプのように宗教に内容的統一性を求めることは、支配層にとっても二律背反であり、一方で「ドイツ」という国家と、他方で「労働」とを提示したケルシェンシュタイナーが「統一学校」に対する支配階級の要求をよりリアルに取り込んだのである。しかし、それが容易に国家主義のイデオロギーに同化することも明らかであろう。(5)
<註>
- W. Rein も同様の発想に基づいている。彼は「国民的統一学校(nationale Einheitsschule)を次のように説明している。
1.部分が内的に捉えられ、生き生きとした関連を持つような統一的な組織。
2.親の地位や財産より、青年の才能を顧慮する。
3.そのために普遍的基礎学校(allgemeine Grundshule)をつくる。
4.その上に三つの類型の学校が分岐する。
国民学校の上級 Oberstufe der Volksschule
実科学校 Realschule
高校 höhere Schule
Rein a.a.O. Reichsshulkonferenz 1920
- メッサーは宗教教授なしに、道徳教育が可能かどうかが、大きな問題になっており、フェルスターのように通常、宗教が不可欠であると考える者が多かったが、その場合必然的に宗派学校を設定することになると指摘している。Messer a.a.O. s120-121
- Kerschensteiner "Theorie der Bildungsorganisation" し126
- Karl Christ "Sozialdemokratie und Volkserziehung" 1975 s21
- テウスの発言
<国家有機体説と教育の自律性の否定>
初期ケルシェンシュタイナーには、ほとんど教育の自律性・自由論は見られない。(1) そして、後年彼の理論体系に根本的な変化発展が起こっているわけではないから、本質的には彼には「自由」の位置づけは存在しないのである。
ケルシェンシュタイナーは労作共同体の課題を次のようにまとめる。
1.共同の労働で、その分業の全ての部分を含むものである。
2.個人とその作業とを、大きな経済計画の中に組み入れる様式である。
3.共同の自治であり、利害関係の平均化への努力と、明らかにそれが道徳的理念言に反しない限りにおいてであるが、社会によって是認されている権威に対する個々人の意思による服従とである。(2)
しかし、晩年の著書に至って、「自律性・自由」について触れるようになる。ところが、それは常に「権威」の補完物としての自律性・自由であって、権威への主体的契機を孕んだ概念ではないのである。彼は自律性・自由が基礎をおく土台を次のように書いている。
陶冶共同体としての学校は、その陶冶労働の遂行のために、生徒に対してそれが異質の決定によって行為や行動に対して自己責任の意識を呼び起こし、陶冶についての倫理的な要求を換気するように、ある程度の自由と自己決定権を保証しなければならない。(3)
そしてケルシェンシュタイナーは生徒自治の前提を次のように書いている。
1.地方的形態の自由一校長・教師の自己責任
2.同胞的精神の横溢している教師集団
3.青少年への信頼をめざす教育精神
4.メンバー相互が熟知していること(4)
ケルシェンシュタイナーの手の労働についての提起も、この点に最も重要な意味があった。
われわれは、技能を身につけさせるという理由だけで、すなわち、われわれの国民同胞が実際的な作業から隔離されないために、上手にかんなをかけ、のこぎりをひき、やすりをかけ、きりで孔をあけ、縫いものをし、織物をおり、料理を作るなどのことを実際にできるようにするという理由だけで、学校に作業場を要求しているのではない。否、われわれは、何よりもまず人問を教育するために、国家集団の原理とそれによる恩恵とを根本から理解して、国家に感謝の念をこめて奉仕するような人問を形成するために、作業の場を要求しているのである。書物が文化の担い手なのではなくて、ひたすら同胞あるいは偉大な事実に奉仕する献身的な作業が文化の担い手であるからこそ、われわれは作業の場を必要としているのである。(5)
ナトルプにとっての社会は、何よりも人と人との自然な結合としての共同体(Gemeinschaft)であった。そして、共同体によって具現される理想は、人々が無限の統一を求めていく態度の中にある、とした。(6)
ここにナトルプの統一学校の意味がある。
ケルシェンシュタイナーはナトルプよりも国家主義的、つまり国家が共同体よりもア・プリオリに存在するという点で、国家主義的であった。
このように教育の自律性、ひいては人問性の自律性の否定は、彼の国家有機体説から必然的に導かれるものである。「統一学校運動」の代表であった意味も、こ.菅こに現れているといえるであろう。
ケルシェンシュタイナーとナチスの関係も当然触れておく必要があろう。
ワイマール体制に対して、心からの信頼感をもっていなかったことについては、ナチスと同じ問題意識を共有していた。中央党やSPDへの批判はよくなされた。そして、国家への従属を主張する点においても同様である。ケテリッツはワイマールの混乱がナチスを登場させた、という叙述の中で、「しかし、ケルシェンシュタイナーはもはや生存していなかった。」という表現をして、もし生存していたら、ナチスのイデオローグになった可能性をほのめかせている。(7)
ケルシェンシュタイナーにとって、国家は至高の存在であった。
確かに、互いに対立しあっている個々の団体や全体社会の分岐の精神的役割を果たしたいという要求は、その理念の部分に対して最高の全価値的及びここの分岐の善へと高めるのである。というのは、倫理的な理念としての国家は、全ての分岐によって不可避的に生成した全共同体の利害の比較の正当な手段であり、それと同時に共同体の恥ずべき作用の影響を規制する手段だからである。(8)
全ての国家機関は、倫理的国家理念の統治法体系を考慮して、倫理的国家意識の酒養を利益として、下部要素と同様、国家共同体の教育組織の形成への要求を持つのである。(9)
そして、次のように国家の権利をまとめている。
1.国家はその担い手に対して、個人の教育可能性に応じて、陶冶を含有するべく権利と義務をもつ。
2.国家は、学校組織の決定についての権利をもつ。
3.国家は各種教育施設を拡充する権利と義務をもつ。(10)
この論理構造にはナチスとの多くの共通性を感じさせる。
しかし、ナチスにおいて国家への忠誠は、ナチス党への忠誠であったが、ケルシェンシュタイナーは党が国家を代表することは強く批判した。カール・シュミットにしても、倫理的に国家=ナチス党であったわけではない。一方、カール・シュミットはワイマール体制を激しく攻撃したが、(11)11ケルシェンシュタイナーはワイマール憲法を原則的に批判したことはない。
にも関わらず、ともにワイマールからナチス体制への移行に責任をおわなければならないとすれば、彼等の本質的共通性として、「民主主義の否定」を基礎にしていたことである。国民一人一人が政治主体として成長することを前提とした民主主義が土台とならない限り、政治反動に落ち込むことを、ケルシェンシュタイナーの理論は示している。
しかし、ケルシェンシュタイナーとナチスは決定的な二つの点で異なっていた。
ケルシェンシュタイナーは反ユダヤ主義の立場をとっていなかった。ニューヨークのユダヤ人区の小学校の、ドイツに対する愛国的な教育を賞賛して、次のように書いている。「この学校ほど立派に訓練された学校をほとんど他にみたことはなかったのである。」(12)
第二に、ナチスにとって、国家は少なくとも政権獲得後、極めて小さい意味しかもたなくなったといえる。ナチスにとって中心的組織は党だった。しかし、ケルシェンシュタイナーは党を国家を支えるものとみて、絶対的なものとはみなかった。(13)
更にケルシェンシュタイナーは科学教育を部分的にせよ重視した。宗教は重要な役割を果たさないとはいえ、抑圧の対象ではなかったし、一般教養の価値は、充分に認められるところであった。
ではナチスはケルシェンシュタイナーをどのように評価していたか。
少なくとも全面的な否定ではなかった。
マクデブルクは、ケルシェンシュタイナーが国家に忠誠なる公民教育を志向したことを評価しながらも、しかし、それが、ナチズムではないこと、また職業教育を通して公民教育をするということが、本質的な職業教育を実現させないものであることによって、「ケルシェンシュタイナーはナチスではない」としている。(14)
以上、ケルシェンシュタイナーの統一学校論は、第一に、階級分裂を緩和し、国家的一体感を創出すること、そのために普通基礎学校に労働教育と公民教育のための「労働共同体」を導入すること。
第二に、科学・技術の発展と帝国主義的競争に対応して、労働者階級のうち「才能ある者」を選び出すことを「統一学校」に求めた。
第三に、それを裏付ける「能力観」は能力の「先天的規定性」と「形式陶冶」説を支持したが、これは、能力が階級的に規定されているという主張を、個人に分解したものであった。彼は能力を発達するものと考えず、具現するとのみ考えた。したがって、能力の違う者のために別の学校が用意される。ケルシェンシュタイナーの教育論は、帝国主義段階における支配階級の教育要求を理論化したものであった。
<註>
- 大谷氏の研究においても1924年以後である。大谷前掲 p199-207 7メッサーは、ケルシェンシュタイナーが「美的教育が全ての教育の基礎とは言えないが、自由に至る不可欠の教育である。」と書いていることを指摘している。Messer a.a.O. s106
- ケルシェンシュタイナー『公民教育の概念』 p57
- Kerschensteiner "Theorie der Bildungsorganisation" s63
- ケルシェンシュタイー 前掲 p115
- ケルシェンシュタイナー『作業と学校の理論』 p99 もう一つは、才能が多様だということにある。つまり、多様な個性に対応するためには、書物学校では不可能だということである。 p99
- 細谷前掲 p124
- ケテリッツ前掲 p61 国家主義的な統一の主張としての統一学校論として、他にHans Richer "Die deutsche Bildungseinheit und die höheren Schulen" 1920 J. Friedrich "Die Deutsche Volkstumpägogik ── Die NOtwendigkeit ihrer Begrundung nebst Bausteinen und Richtlinien" 1920 H.Leitz "Die Deutsche Nationalschule" 1920 (これは統一学校論そのものではないが、統一学校の一考えに従った改革案となっている)等がある。
- Kerschensteiner a.a.O. s96
- Kerschensteiner a.a.O. s98
- Kerschensteiner a.a.O. s100
- カール=シュミット『現代議会主義の精神史的地位』
- ケルシェンシュタイナー『公民教育の概念』 p136 ただし、カール・シュミットにみられるように、本来反ユダヤ主義と無縁でも、ナチス政権下において自己の立場を守るために、反ユダヤ的な主張をした人は、数多くあったことも無視できない。
- ケルンシェンシュタイナー前掲 p172
- Ernst Magdeburt 'Die Stellung und die Aufgaben der Berufserziehung' im "Die deutsche Erziehung" herg von Benze s261-265
松岡信義氏は、ケルシェンシュタイナーがナチスに弾圧されたことをもって、ナチス思想との異質性を論拠だてているが、弾圧されたことは、ただちにナチスと対立していたことの証明にはならない。ファシズムの弾圧は段階的に進むのであって、初期の弾圧、つまり共産主義者の弾圧には利用されるが、次に自由主義の弾圧に進む中で、自ら弾圧されるという存在は広範に存在した。したがって究明されるべきは、ケルシェンシュタイナーの論理的特質であって、その国家有機体説がナチスにとってより強力に押し進められたことは疑いのないところである。松岡信義「シュプランガーとケルシェンシュタイナー ドイツ教育思想研究への一視点」長尾十三二監訳『シュプランガードイツ教育史』の解説として所収
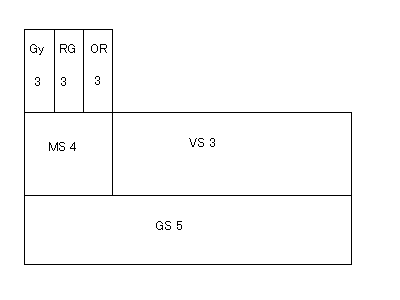 Fock s125
Fock s125
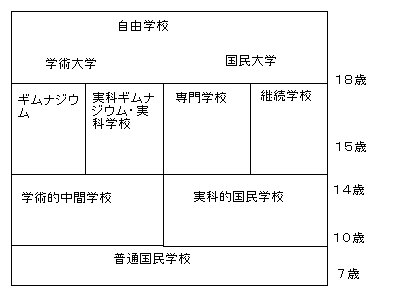 Saupe s.18
Saupe s.18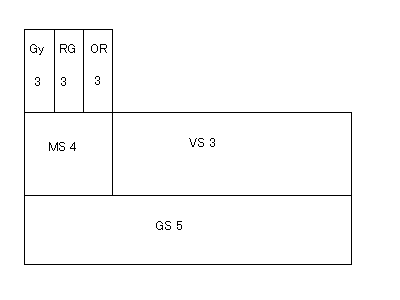 Fock s125
Fock s125