(3)フィッシャー法の制定過程
<フィッシャー法の提案と反対運動>フィッシャーが改革案を出したのは、1917年2月のことであり、「緊急提案(2日)」「一般原則(5日)」という文書によって就学年齢の引き上げ、ハーフタイムシステムの廃止、幼児学校、継続学校の充実、中等学校の改革、教師教育の充実、奨学金・補助金の増額を骨子とする提案を行った。(1) これらの内容は地方教育当局に伝えられ、いくつかの市で検討が始まった。
当時、地方の財政は極めて悪化しており、補助金の増額を柱とするこの案は、概ね好意的に受け取られたが、いくつかの反対もあった。(2) 当初より活発な論議がなされ、5月に草案の発表、8月に下院提出と進んでいく。内容は表2の通りであるが、地方教育当局と中央の教育庁の権限義務関係を具体的に規定すること、補助金を増額することが柱となっている。フィッシャーま法の提出の前後、精力的に各地、各団体をまわって、意見聴取及び事情説明を行った。
特に提出前の演説は、記録にみられる限り、教育水準を上げるために教師の質を高めなければならない、という内容に集中している。
4月19日にフィッシャーは下院で教育についての長い演説を行ったのであるが、初めに補助金を増加する説明をしたあとで1870年法、1902年法によって教育の拡大がなされた現状を指摘した。
中等学校の補助金の増加は、生徒の増加によるものであり、そして、戦時中の労働者階級の財産の増加の最も重要な直接的な結果は、中等学校入学の増加及び在学年限の延長とである。そして、給与の最低基準を定め、全体として上昇させること、初等学校教師の養成を中等学校で行うことを提案している。(4)
(略)
たとえ、初等教育の価値を疑う者があったとしても、戦争の経験によって、その疑いは消えたに違いない。しかし、それにも関わらず教育の維持にとって教師が本質的に重要である。もし、教師が悪ければ、金をかけた建物も施設も大部分は機能せず、教育制度は失敗するであろう。(3)
フィッシャーはプリマウス、ニューカッスルで行ったこの直後の演説でも、同様の趣旨を繰り返しているが、(5) 大方は好評であったとはいえ、4月19日の下院の演説に対してすぐに批判の声があがった。それは、財政補助による地方統制の危倶であった。(6) 二回の下院での討論で出された反対点は次のとおりである。
1.地方の統制、教師の統制の危倶(P. Magnus)
2.財政の増大は納税者の負担増にならないか。(F. Banbury)
3.中等教育については自己の名誉と責任で教育するべき。(O'Ponnell)
4.宗教教育は不可欠(E. Ceci)
5.機械化という時代に即応して実科教育を重視すべき。(S. Smith)(7)
こうした批判に対して、フィッシャーは提案前に反論を試みている。ニューカッスルで「国が改革に関係する、ということについてよく疑問がだされるのであるが、教師の給与について基準を定め、それを保持することは必要であり、それを議会で決めることも必要である。」(8) と述べた。
もちろん財政補助に対しては教育現場では切実な要求であり、フィッシャーの提案はそれをふまえて出されたものである。7月12日に、校長協会と中等学校協会連合協議会(Federal Council of Secondary School Association)がフィッシャーに対して、教師の物的条件は地方教育当局によって異なっているので、物的援助を増額してほしいという請願をしている。(9)
こうして8月16日法案が下院に提出されるが、周知のように地方教育当局及び綿織物業界を中心に反対を受け、暗礁にのりあげてしまう。
8月16日の演説は次のような骨子であった。
1.戦争によって明らかとなった教育の欠陥を正すことが一つの目的である。
2.宗派問題については議論をしない。
3.行政上は1902年法により徹底する、ということである。(大学、地方教育当局が管理しない中等学校・工業学校・特待生・高等師範学校等については、除外している)
4.学校医療の改善。
5.市民としての精神を養うことが、最も重要な教育的課題である。
6.具体的提案としては6つである。
(一)教育行政の改善
(二)14歳までの就学義務
(三)継続学校への就学義務
(五)小学校教育の改善
(六)私立学校との関係の改善(10)
表2フィッシャー法の概略
(法案1917.8修正案1918.1決定1918.8)
A.地方教育当局の権限及び義務
| 法案 | 修正案 | 決定 |
| 公教育に対する原則的義務 | 同 | 同 |
| 諸計画を教育に提出する義務(継続学校・教育訓練・供給) | 諸計画を教育庁に提出する権利義務(同) | 同(継続学校・職業学校・カレッジ・教員の訓練・供給) |
| 教育長により承認された場合の実行義務 | 同 | 同 親・関係者を代表するようにしなければならない |
| 義務A中央学校・学級・特別学級高等科(courses of advanced instruction) | A同 | A同 |
| capacity circumstances age に 応じる教育 | B同 | B ability, age, requirement に応じる実家教育 |
| C小学校以外への転出・進学の準備 | C同 | C同 |
| D無償の継続学校 | D同 | D同 |
| 権限A教区域における合同委員会 | A同 | A同 |
| B寄付金及び借財 | B同 | B同 |
| C小学校以外の教育への地方税制限(1902年法) | C同 | C同 |
| D休日野営・学校野営・体育施設・社会的訓練の施設・遠隔者用の宿舎・下宿施設・保育施設 | D同 | D同 |
| E教員・学生の研究補助 | E同 | E同 |
| F宗教教員以外の教員の任命 | F同 | F同 |
| G同一宗派の小学校が数校ある時の子供の分配(教育庁の許可) | G同 | G同 |
| H土地購入(教育庁の許可) | H同 | H同 |
| I会議費用(教育庁の規定) | I同 | I同 |
| J子どもに残酷な者の起訴 | J同 | J同 |
B.教育庁の権限及び義務権限
| A地方教育当局の計画を認可 | A地方教育当局の計画承認(意見の時は協議・非承認の時は理由を公表) | A同 |
| B継続学校について、通学時期・警告・証明書の規定 | B同 | B同 |
| C特別市以外の市参事会の権限を州参会に移行する | C削除 | C削除 |
| D管理上問題がある時調査委員会(教育庁の任命) | D管理上問題がある時調査委員会(一人以上教育庁が任命、当該地で聴聞会) | D同 |
| E地方教育当局への教育補助(実費の半額議会による停止は不可、地方教育当局の不正の時は減額) | E同 | |
| F地方教育当局が教育法の適用に疑問がある時は、教育庁の解釈による | F削除 | F削除 |
C.通学び雇用
| 5歳から14歳の例外のない就学義務 | 同 | 同 |
| ・地方教育当局は15歳に引き上げることができる(ただし14歳から15歳は免除) | 同 | 同 |
| ・保育学校が十分な時は、6歳まで免除可能 | 同 10人の親の公開審査 | 同 |
| ・通学しない者が効果ある教育を受けているが否かの認定は地方教育当局 | 同 | 同 ただし、教育庁及び教育当局の視察・十分な記録が必要 |
| ・非宗教的教授について、地方教育当局の権限 | 同 ただしそれにより宗回教が受けられない時の宗教の時間の保障障害児はこの規定を同除外 | 同 |
| ・学期は地方教育当局が決定 | 同 | 同 |
| ・14歳で義務就学を終わり、16歳まで就学しない者は、1年360時間の継続学校に就学義務(違反のときは本人及び保護者の罰則) | 同 | ただし地方教育当局が認める時は、280時間以上7年間実施を延期、出席については青年の同意が必要、教育内容については親の意向にそう |
| 雇用制度イ継統学校への通学時間 | イ同 | イ同 |
| ロ12歳以上14歳以下の通学時間 午前6時前・午後8時以降 | ロ同 | ロ削除 |
| ハ14歳以下 | ハ12歳以下 | ハ同 |
| 日曜日は2時間以内 雇用については地方教育当局の許可が必要 | ||
| 就学義務の実施については地方教育当局の責務 | 同 | 同 |
| 通学を妨げたり、健康を害する雇用の禁止(罰則規定) | 同 | 同 |
教員給与の増額については基準の国定ということ以外は、反対もなく実行に移されていった。フィッシャー法自体は一度廃案になり、再提出されたのであるが、教師の給与改善については、地方で実施されていくことになる。因みに1918年1月10日号から3月7日号までのタイムズ教育版の地方欄に報道された68都市の記事の中で、32の記事が教師の給与の改善に関するものであり、しかもその改善は補助金の増額によって可能になったと紹介されている。しかも一年前の同時期の記事には、フィッシャーの改革に対する批判的見解が少なくなかったが、この時期には積極的に受け入れ、フィッシャーの趣旨にそった計画づくりを進めている地方当局が出てきている。(Plymouth, Birmingham, Nottinghamshire)このようにみると、一度挫折したフィッシャー法が教育界に受け入れられていった要因は、何よりも教師の給与改善を軸とした補助金の増額であったということができる。
初等教員の給与は次の表3のように改善されていった。
1918年から1921年にかけて、地方教育当局の支出は教師の給与について著しく増加しており、教師の平均給与も増額されている。これは、法によって給与水準の改善が行われたためである。(11)
表3 初等教員の給与(単位ポンド)
| 1911年 | 1914年 | 1920年 | 1924年 | ||
| 1 校長 | |||||
| 男 | 435 | 450 | 633 | 767 | |
| 女 | 313 | 324 | 595 | 595 | |
| 2 助教授 | |||||
| 男 | 166 | 174 | 297 | 390 | |
| 女 | 120 | 126 | 212 | 308 | |
| 3 全教授 | |||||
| 男 | 200 | 208 | 332 | 424 | |
| 女 | 139 | 224 | 321 | ||
| 男 | 167 | 173 | 271 | 370 |
<註>
- Andrews op.cit. p19
- 反対が出されたと報じられたのは、4月ではバーミンガム、ゲイテスヘッド、シェフィールド等である。T.E.S.1917.4.17
- T.E.S.1917.4.17
- ibid. p
- 'Mr. Fisher at Plymouth ── The Outlook for Reform' T.E.S.1917.5.10 'Mr. Fisher at Newcastle' T.E.S.1917.6.7
- 'Mr. Fisher's proposal' T.E.S.1917.4.26
- T.E.S.1917.4.26 'The Debate on Mr.Fisher's Speech' T.E.S.1917.5.3
- T.E.S.1917.5.10
- 'The future of Secondary Schools Deputation to Mr. Fisher' T.E.S.1917.7.19
- T.E.S.1917.8.16 『英国教育改革法案』文部省
- Board of Education "Memorandum on the Board of Education Estimate 1923-1924" p3 1921-1922年の増加について、こうした分析をしている。1921年7月19日、8月25日に、給与水準の回状が出されている。Board of Education "Circular to Local Education Authorities" Circular 1220. Standard Scale of Salary for Teachers in Public Elementary Schools" 1921.7.19 同名 Curcular 1229, 1921.8.25
但し、後者によれば、7月19日の回状は、充分に地方教育当局に徹底せず、したがって基準がうまく機能していないので、再び出された、としている。7月19日の基準の改訂は次のようになっている。
1921~22に採用の基準 1922~23に採用の基準 有資格 1922.3.31に採用 有資格 1923.3.31に採用 男 女 男 女 £ S d £ S d £ S d £ S d Ⅰ既研修 164 3 4 153 6 8 168 6 8 156 13 4 Ⅰ未研修 153 6 8 142 10 0 156 136 4 145 0 0 Ⅲ既研修 167 10 0 156 13 4 175 0 0 163 6 8 Ⅲ未研修 156 13 4 145 16 8 163 6 8 151 13 4 Ⅳ既研修 137 6 8 162 10 0 186 13 4 175 0 0 Ⅳ未研修 162 10 0 151 13 4 175 0 0 163 6 8 無資格Ⅰ 101 3 4 92 6 8 102 6 8 94 0 0 無資格Ⅱ 103 3 4 94 0 0 106 6 8 98 0 0 無資格Ⅲ 106 13 4 97 6 8 113 6 8 104 13 4
- Board of Education "Memorandum on the Board of Education Estimates 1923-1924" 1923 "Memorandum on the Board of Education Estimates 1926" 1926 Simon "The Politics of Educational Reform 1920-1940" 1974 掲載の表によって再構成したもの。
テイラーはフィッシャーが教師の給与を引き上げたことは、教育制度に大きな影響を与えたとする。つまり、国家が教育に金を出すが、内容を問題にしないという体質がここではっきりした、ということである。テイラー前掲 p167
<ハーフタイムシステムをめぐって>
周知のようにイギリスでは1920年暮れから恐慌に陥り、1921年に設置された「国民支出に関する委員会(ゲッヂス委員会)」によって、経費削減が強行されるのであるが ── 事実1922年以後初等教育費は、減額されている ── 表3,4をみる限り、その中で教師の給与について大きな配慮が図られていることがみてとれる。(1)
表4 地方教育当局の初等教育支出(2)
| 初等教育費 | 教師給与 | 給与の割合 | |
| 1913-1914 | 25,608 | 16,416 | 64.1% |
| 1918-1919 | 34,763 | 24,191 | 69.6 |
| 1919-1920 | 45,294 | 31,356 | 67.0 |
| 1920-1921 | 58,420 | 39,528 | 67.7 |
| 1921-1922 | 60,695 | 41,603 | 62.1 |
| 1922-1923 | 58,424 | 42,188 | 68.5 |
| 1923-1924 | 56,736 | 41,019 | 72.3 |
| 1924-1925 | 57,529 | 41,100 | 71.4 |
したがってフィッシャーが当初公的に発言していた目的は実現していったということができる。(3)
さて、その強い反対によって法案を一時挫折させた綿織物業界の反対について検討する必要があろう。サイモンは安い労働力を欲する古くから確立した産業の要求と評価しているが、(4) 彼等はどういう理由付けの下に反対したのか。種々の発言、資料によって知ることのできる理由は次のようなものである。
1.継続学校への義務就学は非実用的であり、不可能である。16歳から18歳というのは青年にとっても有利な労働時期なのだ。(5)
2.継続学校の義務化及びハーフタイムシステムの廃止は24%の労働者に影響し、8%の労働力が消失する。これは産業にとって重大である。(6)
3.ランカシャーでは児童労働に依存しており、高い労働力に依存したら日本やイタリアに勝てない。更に児童労働の賃金を低下させる。(7)
4.教師がみつからないであろう。(8)
これに対してフィッシャーはマンチェスターに出かけて説得を試みている。彼は大要次のような演説をした。
教育については地方の努力が大切であって、特にマンチェスターは産業の中心であること同様あるいはそれ以上に教育の中心なのであるから、諸君は文化(culture)が価値あることだということを理解しているであろう。我々がやろうとしていることは大変単純なことなのである。それは、第一に、小学校の条件の改善、第二に、中等学校の拡充、第三に、14歳までの義務就学である。私はジョン・マッコーネ氏からの反対の書簡を受け取った。この三つは良いが、継続学校の義務化、ハーフタイムシステムの廃止には反対だ、ということである。しかし、それによって失う労働時間というものは大変にわずかであって、むしろ得るところの方がはるかに大きいのである。フィッシャーの考えは、綿織物業という狭い範囲では確かに不利な面は多少あるが、より全体的な視野からみれば、産業上も利益になるのだ、ということであった。それ故マンチェスターやランカシャーの業界関係者の不満は、これでは全くおさまらず、先の1.3のヒッベルトの反対が後になっても強硬になされるのである。
第一に、一般的労働への応用力
第二に、労働の習慣の形成(特に女子の場合)
第三に、労働時間の短縮が機械化の刺激になること
法の適用において私が考えているのは、労働時間・順応性における改善・青年労働の減少及び社会の健全化という三つの要素についてである。労働青年は体力において明らかに劣っており、継続学校はこうした面についても配慮することになっており、こうして社会の健全化をはかることが必要なである。どうか、狭い産業的利害のみで考えないでほしい。(9)
フィッシャー自身の言明からみれば、上記の表現は当初とは若干の相違をみせている。8月16日の下院での提案説明においては、継続学校の目標は産業にとっても利益が大きいこと(したがって教育内容は当然地方によって異なるであろう。)、第二に、週8時間の教育が理想なのではなく、より多くの教育が望ましいこと、第三に機械の付属物になっている感のある労働青年に、一定の解放を与えるものであることが主張されていた。(10)端的な変化は個別工業への木利にならないという配慮が前面にでてくることである。(11)このことはタイムズ教育版が指摘していたが、(12)事実上この変化において継続学校の義務化の挫折は既に明らかとなっていたといえる。以上みたように、フィッシャー法が当初の予定どおり進まず、かなりの修正、後退を余儀無くされたのは、この産業界の反対及びこれに呼応する労働団体の圧力であったということができる。(13)
<註>
- この点についてはサイモンも同様の指摘をしている。Simon op.cit. p32
- 前項註11,12の二つのMemorandumによって計算した。
- 三好氏によれば「ゲッジスの斧」の教育についての内容は、無償席を25%カット等によって教育費の総額を5000万ポンドから3400万ポンドに引き下げるということであるが、(三好、前掲 p186-187)これはその通り実施されたとはいいがたい。例えば無償席についていえば、1921年の34.8%から1922年31.8%に減少するが、すぐに回復して、1931まで一貫して上昇している。又教育費の総額にしても、全体としてはかえって増加しているのであり、したがって教育政策上フィッシャー法の評価について「ゲッジスの斧」を過大に評価することは誤りというべきであろう。実際の影響としては、継続学校の義務化が延期されたことがあるが、これとても法制の時点で既に7年間の猶予があったのであり、しかも8年後の1926年に出された「ハドーレポート」では、異なった方針が出されている。それ故フィッシャー法については、あくまで法そのものがもっていた論理が考察されるべきであろう。
中等学校無償席及び全教育費支出(England and Wales)
年度 生徒数 無償生 割合 補助金 地方税 合計 1914 60,453 18,310 30.3 13,772 15,555 29,327 1920 96,283 28,539 29.6 30,191 23,688 53,876 1921 95,561 33,253 34.8 38,317 32,224 70,541 1922 90,601 28,829 31.8 40,002 34,059 74,061 1923 80,754 26,116 32.3 38,681 32,209 70,890 1924 80,340 27,191 33.8 38,094 30,317 68,411 1925 84,567 32,161 38.0 38,489 31,345 69,834 1926 86,908 33,743 38.8 39,097 32,214 69,311 1927 88,946 37,056 41.7 39,088 32,846 71,934 1928 89,253 38,097 42.7 39,582 33,197 72,779 1929 84,385 37,014 43.8 41,790 35,235 77,025 1930 86,119 39,079 45.4 42,418 37,052 79,470 1931 89,682 43,823 48.8 43,778 38,485 82,263 1932 96,342 46.946 48.7 41,412 39,340 80,752 1933 92,652 43,865 47.4 38,336 39,839 78,175 1934 92,490 41,106 44.4 38,518 40,522 79,040 1935 94.540 42,304 44.8 40,288 42,414 82,702 1936 93,850 42,327 45.1 42,749 43,576 86,325 1937 97,115 45,957 47.3 43,922 44,968 88,890 1938 98,820 46,707 47.3 44,989 46,684 91,673
補助金・地方税等支出は初等・中等の合計
単位は1000ポンド Simon op.cit.p 365,377
- Simon op.cit. p16
- ランカシャー選出議員 H. Hibbert 1918年3月13日、第二読会での発言、'Parliament, The Educational Bill, second reading debates' T.E.S.1918.3.14
- Manchester Guardina に掲載された Fine Cotton Spinner's Association の副議長 John McConnell の投書。フィッシャーが演説の中で紹介しているもの。T.E.S.1917.10.4 及び Liverpool, Salford の青年雇用委員会が青年労働力の必要性から13歳以上の雇用制限を除くべきであるという意見をまとめている。Bedfodshire の教育委員会(Education Committee)は農業労働力の確保という視点から反対している。T.E.S.1917.5.3
- 1918年6月5日委員会でのヒッバードの発言。T.E.S.1918.6.13
- ibid. ただしヒッバードは、ここで14-18歳の12万人の青年に、30人に一人の教師をやとうと、一人200ポンドとして、26万ポンド必要で、そんな金はない、といっているが、筆者の計算では13万ポンド強ですむはずなので、批判のため大袈裟な数字を挙げていることになろう。
- 'Mr. Fisher's Campain, The Manchester Speec' T.E.S.1917.10.4
- T.E.S.1917.8.16
- 1918年3月18日の第二読会でのレウィスの答弁。T.E.S.1918.3.21 6月5日の委員会討議のフィッシャーの答弁。T.E.S.1918.6.13(この日激しいヤジに抗しかねて、フィッシャーは7年間の実施延期、320時間を280時間に減らす、という提案をしている。これに対し労働党が逆に反発し、実効性の保障としてスノーデン(P. Snowden)が、生計費補助の提案をするが、143対54で否決されてしまう。(採決は6月10日)労働党が積極的に対応した内容は、ほとんどこの生計費補助につきていた。
- T.E.S.1918.5.9
- 'Why educational Bill have died' T.E.S.1917.11.1 連合織物工場労働者協会(United Textile Factory Worker's Association)は4月に法反対を81,449対32,932で決めている。T.E.S.1918.4.18 但しW.E.A.は工場内継続学校に反対(T.E.S.1918.1.17)、ブリティッシュ労働者同盟(British Worker's League)は、雇用に都合のよい状態で賛成。(T.E.S.1917.11.8) それから委員会審議において、義務化を熱心に主張する者が多くいたこともいうまでもない。「児童労働は国家の問題であり、健全なる教育なくして健全なる労働者はない。」Dawby (Steam Engine Maker's Society)T.E.S.1918.3.2 又マンチェスターからの投書「今の児童労働は悲惨であり、労働時間を減らすことで、かえって失業を減らすことができる。」が紹介されている。T.E.S.1918.2.28
<地方教育当局の反対>
次に地方教育当局からの反対について考察しておこう。表2によって明瞭なように、継続学校に関する規定とともに、教育庁及び地方教育当局の関係についての規定が修正内容の大部分を占めている。しかも、修正は全て教育庁の権限の強化を是正し(弱め)地方教育当局の自主性を保障する方向でなされていて、その逆は一つもない。(1)
19世紀以来、少しずつ中央政府の権限が強化されていたとはいえ、第一次大戦前はまだ分権主義が基本であったということができよう。総力戦としての第一次大戦は教育をも全国的な統制下においた。教師の徴兵、校舎の兵舎としての利用、学童の奉仕等はそれを端的に示している。これらは、全国の教育上の人的物的条件を計画的に利用したものであり、フィッシャー法でまず初めに提案された内容は、この状況を基盤にしていたということができる。戦争はまだ終結していなかった。したがって1917年8月に提案された内容は確かに、教育庁の強い権限と地方教育当局の義務が基調となっていた。
提案の説明演説でフィッシャーは、次のように述べている。
私は全ての州及び特別市の参事会に対して、管轄区域内の教育の発達と大きな組織の実現に資する規定を設けて、計画を教育庁に提出するよう義務付けるものです。(2)具体的には1.教育庁が諸事項についての基準を設定すること、2.地方教育当局が計画を作成する義務を負い、教育庁が審査して認可する権限をもつ、という二つの内容からなっており、それを実質的に保障するものは補助金であった。この法案に分権主義的な地方教育当局が反対したのはごく自然なことであった。その理由は「統制強化」ということにつきる。ロンドン教育委員会(London Education Committee)の議長のコップ(Cyril S. Cobb)のフィッシャーあて書簡がその気分をよく表現している。
教育庁はもちろん、のろまな当局にその権限を実行し、義務を果たすように強いて行わせる権限をもっていなければなりません。行政の条項は極端な場合のみ実行可能であるようにはなっておりません。条項はあまりに一般的で幅広いという性格を持っています。地方教育当局の経験や行動力を教育庁が奪ってしまうかのような権限の集中をその条項は与えています。(3)教育庁の指導性の原則については、充分認めながら、それが無限定であること、地方の主体性を奪うことについては否定しているのである。これに対するフィッシャーの回答はどうか。長くなるがまとめておこう。
1.地方教育当局の任務を明確にすることは、むしろ自由を確認し、増すことである。
2.本質的に重要なことは計画の策定であり、その方法である。
3.真に教育について考えるならば、中央と地方とにおいて大きな認識上の食い違いが生じたときは、より豊富な経験に富み、国会に責任を負う教育庁が子供への責任をより多くもつのは当然である。
4.34条(費用支出についての基準作成)は現行法よりゆるやかであり、36条(調査委員会)は現行法にある、等々決して統制の強化を意図したものではない。
5.全国的最低基準の設定が、中央政府権限であることは諸君も認めるであろう。
6.できたら包括的な補助金を創設したい。
7.まじめな批判は大いに歓迎する。(4)
フィッシャーが主に目指していることは、教育庁と地方教育当局が同じ土台にたつ国家的計画の再生であって、それはアンドリュースが指摘したように、パートナーシップと呼ぶのがふさわしいであろう。(5) 3月12日の下院での答弁でフィッシャーは「地方教育当局が全教育についての骨格的な計画をたてることが必要である。けっして継続学校のみの計画ではないのであって、そうしてこそ国家的計画(national scheme)が可能になる。国と地方教育当局の協力によって初めて教育機会の平等が達成されるのである。」(6) と述べている。しかも、この点については、フィッシャーは自信をもっていたということができる。原案を撤回せざるをえない状況になり、「法案が死んだ」という世評になったとき、フィッシャーはタイムズ教育版に、「法は死んでいない、地方教育当局とは話し合いが進んでいる」と語っているのである。(7)
こうして、多くの反対にも関わらず、フィッシャー法は1918年8月に修正の結果成立する。継続学校の義務化は延期という形をとり、結局実質的に無効となってしまう以外は、承認されることになった。継続学校はむしろ一方において成人教育の問題として、他方において中等教育の義務化の問題として質的に発展していくことになる。
ではフィッシャー法の影響はどのように現れたのか。詳細は別の機会に譲るが、特徴的な2,3の例を紹介しておこう。ロンドンの市参事会(London county Council)は1919年から1921年にかけて次々と教育の計画を作成している。パンフレットのナンバー順にあげておくと次の通りである。
1. Backward Children
2. Promotion of Children in Elementary Schools
3. The Teaching of Science in Elementary Schools of the London County Council
4. Report to the Education Officer by the Conference or School Libraries
5. Instruction of Children over 11 years of age on Ordinary Elementary Schools
6. Development of Education on Public Elementary Schools
7. Development of Education on Public Elementary Schools
8. Times Tables of Schools
9. The Prefect System in Elementary Schools
10. The final Year at an Elementary School(8)
これらの計画は具体的に地域の教育行政官がいかなる問題に直面していたかをよく示している。ここで提起されていることを簡単に概括しておくと、
第一に、障害児のための施設の拡充
第二に、「全ての者に科学を!」が戦争の教訓であり、ステロタイプ化している科学教育を改善する。
第三に、科学教育の改善として、1.科学的な本を読むこと、2.工場見学などを取り入れる。
第四に、11歳以降で小学校に残っている者については、カリキュラム及び教師をより高い水準のものに再編すること。
第五に、更に中央学校(central school)の拡充等である。
すなわち、問題となっている最大のことは、小学校における自然科学教育を中心とする水準向上、そして、11歳以降の教育の再編(無就学の除去)である。
もう一つ、ランカシャーの教育関係者の協議による10カ年計画をみてみよう。
「教育の国家制度(A National System of Education)」と題されたこ計画は、現存する学校を承認する形でできあがっているが、特徴的なことは12歳で全ての者が、12歳までの小学校教育より一段高い教育を受けるようにすること。Aクラス(リーダー層になる者、2%)、Bクラス(給与生活者になる者)、Cクラス(熟練工になる者)、Dクラス(非熟練工になる者)という階層的な制度体系を構想していること、小学校段階においては小学校と、中等学校の予備学校との区別をなくすこと、各段階の移行は基本的には「能力」によること、ただし各クラス間の移行の制度的保証をつくること、等である。(9) このプランはドイツ統一学校運動の主流の考えに極めてよく似ていることに気付かれるであろう。そして、共通の小学校、多様な小学校後教育、能力による分化という原則は実はフィッシャー法の立法者意志の中において既に定着しているといえる。逆にいえば、フィッシャーが自ら地方教育当局との間に本質的矛盾はないといったように「パートナーシップ」が形成されつつあったということができよう。
このことを更に補助金によってより鮮明にしておこう。
補助金はフィッシャー法の重要な政策であるが、フィッシャー法の補助方式の改訂には、ケンプ委員会の補助方式によって生じた地方格差を是正しようという目的があり、これは確かに実効性をもった。表5は各都市の教育費を児童一人あたりの経費で、都市の間の格差を調べたものである。標準偏差を出すと、1921年が36.08で1922年が33.91となっており、明らかに地方格差は縮小しているのである。つまりフィッシャー法が国庫補助金によって、実質的な統制を強めたのは、こうした地方格差の是正によって国と地方の協調関係をつくりだしたことで可能になったのである。
表5 児童一人当たり経費の都市分布
| 都市数 | 都市数 | 都市数 | |
| 1921年 | 1922年 | 1923年 | |
| -150 | 3 | 2 | 1 |
| 150-155 | 1 | 3 | 2 |
| 155-160 | 4 | 3 | 1 |
| 160-165 | 8 | 3 | 5 |
| 165-170 | 9 | 12 | 7 |
| 170-175 | 14 | 16 | 13 |
| 175-180 | 13 | 15 | 18 |
| 180-185 | 17 | 15 | 14 |
| 185-190 | 24 | 19 | 22 |
| 190-195 | 16 | 28 | 26 |
| 195-200 | 16 | 16 | 14 |
| 200-205 | 17 | 21 | 13 |
| 205-210 | 26 | 25 | 30 |
| 210-215 | 18 | 9 | 17 |
| 215-220 | 8 | 16 | 14 |
| 220-225 | 16 | 15 | 9 |
| 225-230 | 12 | 10 | 19 |
| 230-235 | 7 | 14 | 8 |
| 235-240 | 19 | 12 | 11 |
| 240-245 | 7 | 9 | 17 |
| 245-250 | 8 | 20 | 10 |
| 250-255 | 8 | 5 | 6 |
| 255-260 | 6 | 5 | 4 |
| 260-265 | 5 | 4 | 3 |
| 265-270 | 5 | 5 | 7 |
| 270-275 | 5 | 5 | 7 |
| 275-280 | 5 | 2 | 4 |
| 280-285 | 0 | 2 | 4 |
| 285-290 | 3 | 1 | 1 |
| 290-295 | 3 | 3 | 1 |
| 295-300 | 1 | 2 | 2 |
| 300-305 | 3 | 1 | 1 |
| 305-310 | 2 | 0 | 1 |
| 310-315 | 1 | 0 | 1 |
| 315-320 | 2 | 0 | 0 |
| 320- | 3 | 3 | 3 |
Cost per Child, Elementary Education 1921-1922,1922,1923
(L.E.A. Actual Expenditure), and 1923-1924(L.E.A. April Extimates)
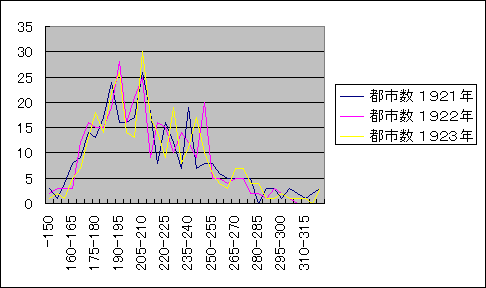
<注>
- 教育行政問題については多く「二重性」の問題として捉えられてきたが、「二重性」の内容については、「州参事会、特別市参事会」と「市参事会」の二重性(成田克矢、前掲 p232)、「学校に対する国家と教育の二重支配」(空本和助『イギリス教育制度の研究』 p56)、「公立と私立の二重性」(菅野、前掲 p186)と様々な理解がある。T.E.S.1917.8.16
- 'Mr. Fisher and his critics' T.E.S.1917.10.25
- ibid.
- Andrews op.cit
- T.E.S.1918.3.14
- T.E.S.1917.12.20
- London County Council "Development Memorandum" No.1-10 このプランはフィッシャー法の規定によるものであることが、明記されている。
- 具体的なカリキュラムを示しておくと、
小学校低学年:自然学習
小学校高学年:初歩の機械・化学・熱電気(以上週4時間)
中央学校(職業的重点をおく)
:基本的物理・植物・化学・心理・衛生・工場などがあるとよい。
ibid. - Federal council of Lancashire and Chesine Teacher's Association 'A National System of Eduation ── some Recommendations for Establishing it on England during the Decade ending Ten Years Hence' 1920
この構成団体は次のようになっている。
リバプール、マンチェスター大学(以下マンチェスター、ランカシャー地域のもの)校長協会、教頭協会(The Assistant Masters' Association)、校長女教師協会、私学協会、NUT、教頭協会(The Association of Head Teacher)、定時制参事会、技術学校教師協会、全日美術教師協会、家政教師協会、音楽家協会、全日手工教師協会
ハーフタイムシステムや継続学校問題については全く触れられていない。