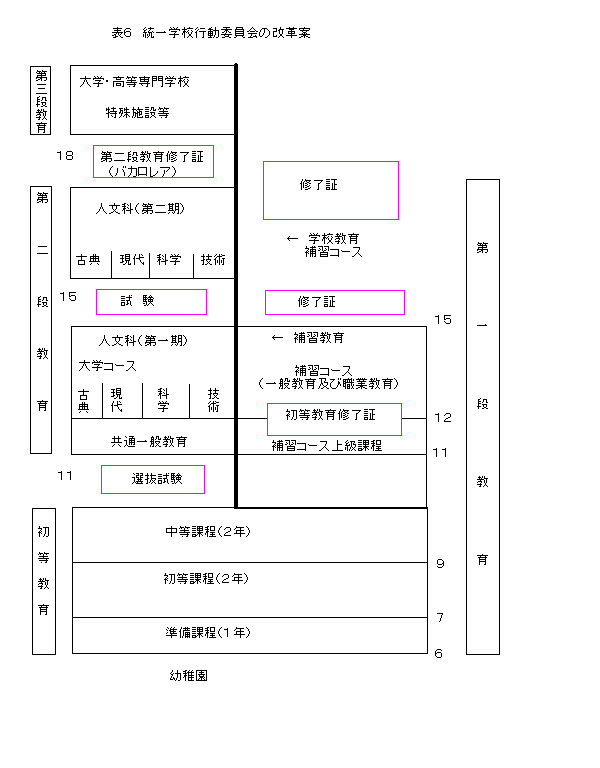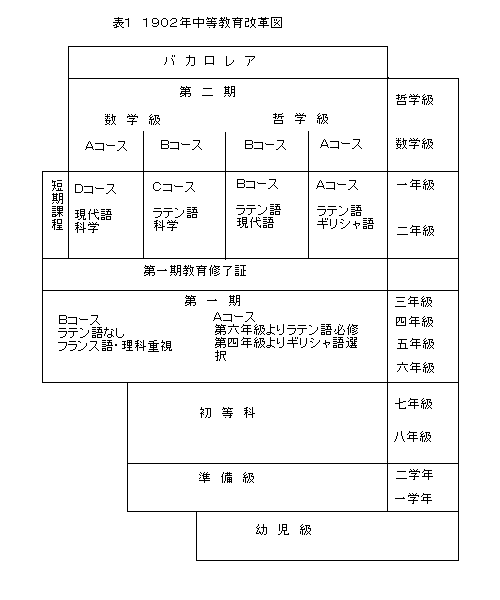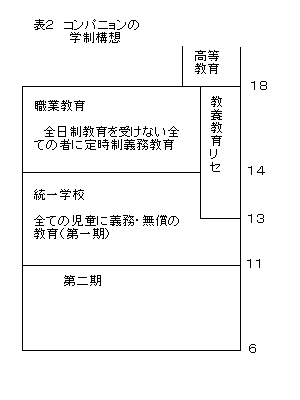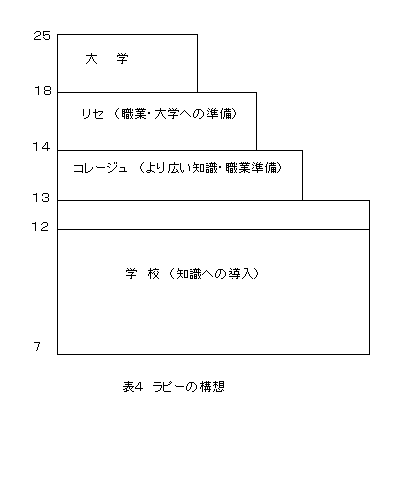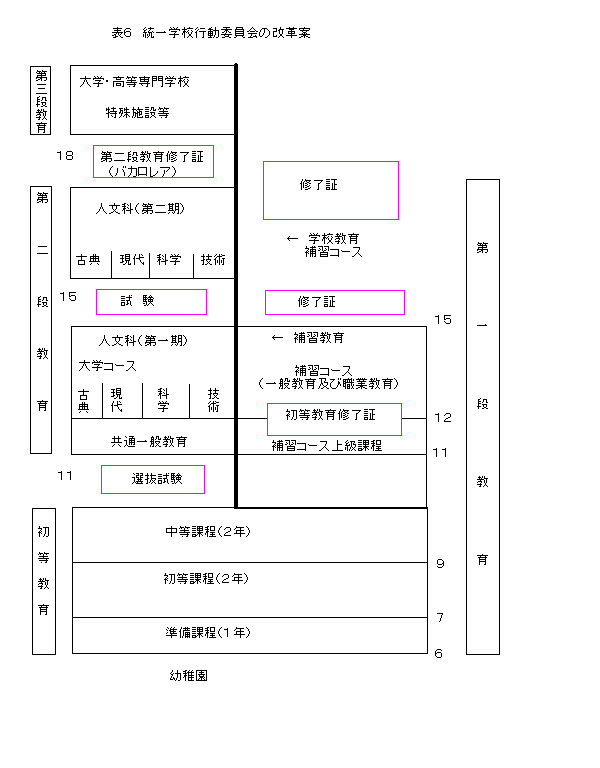第二章フランス統一学校運動の展開と帰結
第一節フランス統一学校運動の展開
(1)はじめに
フランス統一学校運動は、ドイツの運動に学んで始まったものであるが、(1) ドイツとは異なった性格を持っている。運動の契機はドイツ統一学校運動にあったにせよ、思想的にはフランス革命以来の統一学校の思想が伝統として存在していた。F.ビァール(Francisque Vial)が、コンドルセを「統一学校の父」と呼び、(2) M.ウェベール(Mauriced Weber)が、統一学校運動をフランス革命の継承と位置づけたのは、当然のことであろう。(3) 更に第三共和制の下でのJ.フェリー改革で大きな役割を果たしたF.ビュイッソンにより統一学校の主張が述べられてもいた。(4) これらは「人権宣言」の思想がほぼ共通の土台として論議された。この点、様々な議論が錯綜したドイツ統一学校運動とは異なった性格をもっていた。
第二に、戦勝国として第一次大戦の影響が決定的に異なっている。フランスは戦勝国とはいえ、その傷は大きかった。150万の死者、この中にはCGTに参加する25,000名の教師のうち7000名の死者が含まれていた。戦争がなければ生まれていたはずのやはり150万の幼児、そして170万の戦傷病者をもたらした。(5) 工業生産は半減し、農業地帯は戦場となることによって荒廃した。ロシア革命によってロシア公債を失い、利権が消滅した。国富は1914年の3020億フランに比べて、1918年には2270億フランに減っていた。(6) 戦争による被害は1300億フラン、戦時の対外負債は1440億フランにのぼった。校舎の破壊などの教育施設の損害も大きく、子ども達は農作業に駆りだされた。こうした影響は1923年頃までも残っていたといわれている。(7)
戦勝国であり、第三共和制という政治体制が連続し、ドイツヘの敵愾心を媒介とした国民の一体感が生まれたという側面もあるが、(8) 深い分裂も生じていた。
第一次大戦の開始は、フランスにおいては「神聖連合(Union Sacrèe)」の体制の下になされたのであるが、(9) それはジョレスの暗殺という犠牲をともなうものであったし、事実チンメルワルト会議以降、平和運動が存在していた。フランスの戦遂行は、クレマンソーの弾圧政策を必要としていたのである。(10)したがって、戦争末期には社会主義者の多くは、神聖連合を拒否しはじめていた。(11)このように、革命に至るような対立の激化は生じなかったにもかかわらず、戦争の傷が様々な面で深かったことによって、フランス統一学校運動にいくつかの特質が生まれた。
第一に、前記のような政治情勢が、フランス革命の思想を基礎とする急進社会党を政治の中心舞台に押しあげた。(12)ビュイッソン、エリオ(Eduard Herriot)等教育改革に深く関係した政治家が、急進党員であったことも影響して「教育による社会変革」の立場が大きな力を持つことになり、更にそれを中心に教育改革論議が集約された。
第二に、フランス革命の思想の継承が、統一学校運動を経過する中で、変化・発展したことである。フランス統一学校運動の初期では、革命の伝統とは人権宣言とコンドルセの主張のことであり、ルソーの教育論はほとんど含まれていない。1930年代になって、革命思想の再把握がなされるのであるが、このことの意味は何であったのか。
第三に、大きな政治的対立が回避されたことによって、階級対立は文化的対立としてしばしば現象し、教育においてはそれは教養をめぐる対立として現れた。したがってフランス統一学校は主に学校制度の改革が教養をめぐって論議された形態として、その諸潮流が分析される必要があろう。
<註>
- ドイツで統一学校連盟が結成されたのは1886年であるが、それはギムナジウムとレアルギムナジウムの平等を志向するもので、むしろ1914年にドイツ教員連盟が要求に掲げて以来の運動が影響を与えたと考えられる。
- Francisque Vial "Vues sur l'École unique" 1935 p35
- ウェベールは「統一学校は1789年人権宣言の当然の帰結である。」と書いている。Maurice Weber 'L'École Unique' in "Pour l'ere nouvelle" 1932.7. No79 p170
同様の評価としてJoseph Majault, "L'enseignement en France" 1973 p3
ドイツ人であるヘルマン・ノールもこの点を認めている。ノール『ドイツの新教育運動』p169
- 大坂治「F.ビュイッソンの公教育思想研究(その1)」『教育制度研究』第9号1973.12 教育制度研究会
- "Educational Yearbook 1924 International Institute of teachers College Columbia University" edited by Kandel p249-250 (以下本書を『カンデル年報』と略。井上幸治『フランス史』1968 山川出版 p480
- 中木康夫『フランス政治史上』1975 未来社 p373
- 『カンデル年報』前掲 p250
- Félix Pécaut 'École unique et Démocratisastion' in "Revue Pédagogique" 1919. p238
- 中木康夫によれば、神聖連合の左翼的基礎は、1.ジャコバン的愛国主義の伝統、2.1871年以後の対独復讐心、3.対外的帝国主義政策が国内民主化と並行していたための幻想、4.ユンカーに対する「共和政」の擁護という意識があった、等が挙げられる。中木前掲 p366
- トレーズ『人民の子』北原道彦訳 大月書店
- Michel Soulie "La vie polotique d'éucation d'Herriot" p69
- 急進社会党(以下急進党と略)については、クロード・ニコレ『フランスの急進主義』白井成雄・千葉通夫訳 クセジュ文庫 白水社
(2)フランス統一学校運動の前史
<レイグ改革>
中等学校は19世紀を通じて、変遷を重ねた。とりわけフランス革命による科学革命によって上昇した科学の位置に対して、宗教世界と人文主義を奉ずる古典語教師が同盟し、科学教育に対抗した結果、中等教育のカリキュラムは恒常的な争いの中に置かれることになったのである。(1)
そうした動きは20世紀に入ると、1902年に行われたレイク改革である種のまとまりを獲得した。統一学校運動はこのレイグ改革の内容を土台にして行われるのである。
その内容は表1のような中等学校の制度を作ったことであるが、桑原敏明によれば、次のように整理される。
1.中等教育を本来の中等教育(第一期、第二期)と初等教育(初等科以下)とに分け、中等教育に小学校から入りうる道を開いたこと。
2.コース制をとり、古典と近代の壁を取り除こうとしたこと。
3.短期課程を設けて、地方の必要に応じた中堅労働者の養成を図ったこと。
4.バカロレアが一本化され、高等教育入学資格、中等教育修了証という性格をあわせもつようになったこと。
5.教育方法としては、実用的語学、理科や歴史地理では観察が重視された。(2)
つまり、レイグ改革によって中等学校が整理され、また、制度的には初等学校と中等学校の接点が生まれたのであり、後の統一学校運動が対象とする学校制度が成立したのである。
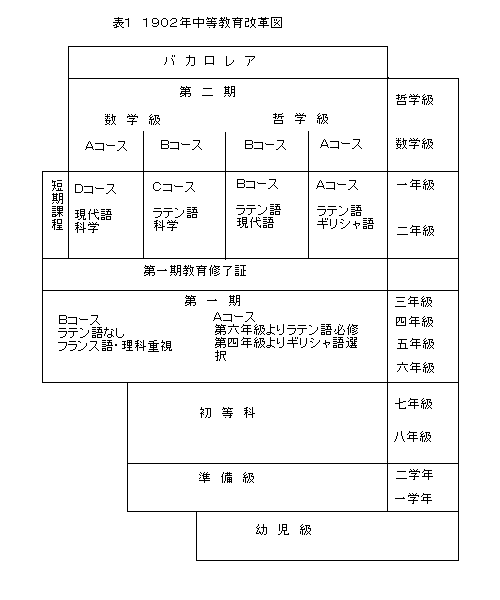
<註>
- デュルケム『フランス教育思想史』小藤藤一郎訳参照
- 桑原敏明「フランス第三共和政前期における中等教育の近代化」『世界教育史体系25中等教育史Ⅱ』所収1976 p146-147
<コンドルセの学校論>
さてこのような制度改革の時期に、どのような改革思想があったのか、ともに、教育学者でありながら、実際に文部行政に携わっていたF.ビュイッソンとF.ビアールによってみておこう。
先に述べたように、二人の理論はともにフランス人権思想、その教育における代表者としてコンドルセの理論を土台としていた。したがって統一学校思想に関わる限りで、コンドルセの理論を整理しておきたい。(1)
1.公教育が全ての人に対する社会の義務であること。(2)
全ての国民という時、障害者をも含んで言われていることは銘記すべきであろう。(3) 教育は三つの種類が考えられている。第一に、自分の能力や教育に充当出来る時間的余裕に応じて、職業や趣味のいかんを間わず、全ての人が承知していることが良いと思われる事柄を、国民の全てに教えること。第二に、一般的利益のためにそれを利用しうるように、それぞれの問題についての特質を知る手段を確保すること。第三に、将来生徒たちが従事する職業が必要とする知識を彼等に用意すること。(4)
2.これらの教育を各々子供のための教育と成人のための教育に区分し、適用されるべき原理を区別したこと。
周知のように、コンドルセの公教育論は、知育限定論で知られるが、成人教育については、必ずしもそうではない。むしろ、画一化されない形での道徳教育、原理・動機にまで及ぶ政治教育を主張している。(5)
3.普通教育を階梯として組織すること。(6)
4.国家から給与を支払われる専門職としての教職の確立。
しかし、この原則は「教師は団体を形成してはならない」いう原則と結びついていた。「これこそが、野心に変ぜず、好策に堕さない競争心を教師の間に維持する唯一の手段であり、教育を習慣的な精神から守る唯一の手段」だからである。(7)
5.普遍的有用性をもつものとしての科学教育、芸術教育。(8)
以上のようなコンドルセの主張は、その後のフランスの教育改革の長い指針となったのであるが、(9) 抽象的、理念的に演繹された構想であったといえよう。コンドルセは民衆生活の逼迫した現実についての認識は弱かった、(10)いう吉沢昇の指摘があるが、そのことはコンドルセの理論の弱点であるよりは、むしろ、「哲学の現実化」(11)としてのフランス革命の特質を典型的に表現していると考えられる。つまり、理念的思惟の徹底によってこそ100年以上後の統一学校運動の先取りをしていたといえる。
<註>
- 堀尾輝久は全ての者の教育を受ける権利、家庭教育の延長としての公教育(私教育の組織化)、知育限定論という内容で整理しているが、「統一学校の父」としてのコンドルセ思想という視点からみると、多少異なった検討が必要である。堀尾輝久『現代教育の思想と構造』岩波書店参照
- コンドルセ『公教育の原理』松島均訳 明治図書 p9-15
- Condorcet 'Troisiéme Mémoire──sur l'instruction commune pour les hommes' in "Æuvres de Condorcet" vol.12 M.F.Arago p325
- コンドルセ 前掲 p22
- Condorcet op.cit. p328
- コンドルセ 前掲 p25-27 その理由として、公職が一つの職業とならぬように国民が公職を遂行することができるようにするため、仕事や職業の区分が人民を愚味にすることがないようにするため、一般教育によって虚栄心と野望とを減少するための三つをあげている。
- 同上 p100 これは社会の義務性を純粋に表現したものと考えられる。
- Condorcet op.cit. p337
- 梅根悟『世界教育史』
- 吉沢昇「近代フランス社会と民衆教育」『欧米社会教育発達史』小堀勉編 『講座現代社会教育Ⅲ』亜紀書房1978 p364
- ハーバマス『理論と実践』細谷貞雄訳 未来社 p78
<ビュイッソンとビアール>
ビュイッソンの教育論はほぼコンドルセの忠実な継承である。もちろん、J.フェリーの改革によって、義務教育制度が既に成立しており、義務教育を否定したコンドルセに対して、ビュイッソン自身義務性を支持している点は異なっている。基礎的な教育を国民に保証することは、社会の義務であり、それは「親からの解放」、親の排他性からの解放でもあるからである。(1)
新しい科学に基礎を置く道徳を究極に望みながら、公教育において知育限定論をとったコンドルセに対して、ビュイッソンはより積極的に、世俗的道徳による教育を提起する。(2) 19世紀末、ドレフュス事件は教育界に大きな影響を与え、第三共和制を擁護することが教育の世俗性の主張と重なっていった。ビュイッソンは、それらを「平和の教育」「人権の教育」と結びつけたのである、したがって知育限定論ではすまなかった。ビュイッソンはコンドルセの精神を継承したといえる。
世俗性とともにビュイッソンがとりわけ問題にしたのは、教育の平等の問題である。現在の教育は、財産や地位による二つの階級の影響を受け、子供も二つの階級に分かれている。一方は12歳までの教育で終了する子供、他方青年期いっぱい教育を継続する子供、そしてこの不平等は社会的不平等を更に再生産している。(3) 大衆の子供は精神(esprit)がなく、教養(culture)を好むことがないというのは誤りである。(4)
そこでビュイッソンは「共通な統一学校(école unique commune)」を次の原則の下に主張する。
1.財産(fortune)ではなく、才能(talent)、可能性(capacité)、天性の能力(aptitude naturelle)、成績(mérite)等によって進学が決められるべきである。(5)
2.学校は無償でなければならないのであって、制度を年齢によって区分しなければならない。(6)
3.統一学校というのは、全ての年齢、全ての子にとって同じ唯一の学校ということではなく、全ての多様性、労働の応用、要求に答えることである。(7)
こうした原則をビュイッソンは急激な社会変革(社会主義)ではなく、合目的、合法的な方法(急進主義)で進めようとした。(8) そして、ほぼ同じ基盤に立ちながら、変革の主体を明確にしようとしたのがビアールであった。
ビアールは18世紀に調和的に考えられた自由と平等の相反性を強く意識した19世紀の中で、コンドルセ及び教育を考えている。(9)
自由は無秩序(anarchie)を生み、平等は無関心(apathie)を生む。(10)ここに民主主義の危機がある。無秩序はブルジョア学校を衰退させ、(11)堅固な一般教養(solide culture générale)をつきくずしている。(12)一方無関心は政治的特性の死を意味しており、ここにデマゴーグの入り込む余地を作っている。(13)
いずれにせよ、こうして民主主義は困難な状況にある。その打開のためにはまず、教育によって精神(esprit)と熱意(bonnes volontés)を高めなければならない。 (14)
しかし、ビアールはビュイッソンと異なって、大衆に期待しない。民主主義の主体は貴族や人民(peuple)ではなく、中産階級(classes moyennes)であり、(15)中産階級のための教育改革こそが急務であるとする。
では、中産階級を創出すべき中等学校の現状はどうか。通常の中等教育はそうした社会の要請に答えていないし、現代中等教育(L'enseignement secondaire moderne)は、その目的を充分に達していない。(16)二種類の中等教育が混乱した状態にある。そこでビアールは中等教育に二つの原理を確立して、二つの中等学校に整理することを提起する。第一に、専門職業教育に継続する有用性(utilité)の原理に基づく中等教育。第二に、知性の形成を目的とする自由の教育。(17)いうまでもなく、自由教育は伝統的な古典教育ではなく、統一的精神(un esprit unique)によって国民的統一性(unité nationale)を生み出すものと期待されていた。(18)
<註>
- Ferdinand Buisson "Un maraliste Laïque──Ferdinand Buisson" Bouglé 1933 p53 (1883年の論文。義務性については実施されていることもあり、当否はほとんど論議の対象としていない。)
- ibid. p60
- ibid. p79-82
- ibid. p83
- ibid. p84
- ibid. p85-87 ビュイッソンは教育制度の段階を第一期(11歳まで)、第二期(14歳まで)、第三期(17,8歳まで)に区分し、第二期までを全日制の義務、第三期を義務補習教育とすること、高等小学校である第二期を実質的に中等教育と相等にすることを提起している。
- ibid. p94
- ibid. p106
- F.Vial "Condorcet et l'éducation démocratique" p23
- F.Vial "L'enseignement secondaire et la démocratie" 1901 p58
- ibid. p100
- ibid. p18
- ibid. p93-94
- ibid. p99
- ibid. p64 中産階級とは、ビアールによれば、商業・工業の経営管理層・地主・公務員である。しかし、エリートではなく、ビアールはエリートはあまり限定されているので、民主主義を支える力にはなりえないと考えている。後年ビアールは統一学校運動がエリートのためのものになった、として批判している。F.Vial "Vues sur l'école unique" 1935
- F.Vial "L'enseignement secondaire et la démocratie" 1901 p202
- ibid. p167
- ibid. p167
(3)コンパニョンの主張
<コンパニョンの設立>
教育運動としての統一学校運動は、コンパニョン(Les Compagnions)という団体によって始められた。創立メンバーであるJ.カレ(Jean Marie Carré)によるとコンパニョンの創立の事情は次のようであった。
カレは大戦中に、しばしば小学校教員と話し合う機会をもったが、とくに平和の基礎となる国民教育について討論をし、アングロ・サクソンの国に試みられている統一学校(L'École Unique)を漠然と知って、それを調査することにした。
1917年、カレは大本営付を命ぜられ、そこで大学教育を受けた知識階級の一団と相会することになり、コンピエーヌの森を散歩しながら社会問題について討論した。アルベール=ジラール(Albert Girard)、リュ(H.Luc)、エドモンド=ベルメイユ(Edmond Vermeil)、ジャック=ドゥバユ(Jacques Duval)等が中心になった。その後論文をまとめ、オピニオン(Opinion)誌の1918年2月9日号に掲載した。(1) そして、その論文を次のような手紙を同封して、友人に送った。
フランスは今や新しい教育制度を要求している。それを実現するのは、我々の任務である。我々は全ての段階における教育を授ける学校の教員として、相互に何らの連絡もなく、路傍の人として無関心に、否、時としては敵意を感じつつ生きてきたのである。全てに組織的なわが国において、我々教員のみが相離れ、無力の状態に留まっていてよいものであろうか。我々を導き、戦場において結ばれ、今やその盟約を牢固として抜くことができない程になった我々の若い精神は、将来といえども我々の前途に横たわる障害物によって蹉跌するとは信じられない。(2)
オピニオン誌やこの手紙に対して、少なからぬ反響があった。雑誌としては L'Eclair (1918.6.6), La Victoire (1918.5.10), Revue des Jeunes (1918.5.10), などが紹介論文を載せ、多くは基本的な賛意を示している。個人としては、16名の手紙が、コンパニョンの著書に資料として紹介されているが、重要なものはビュイッソンとカザミアンであろう。(3)
ビュイッソンは統一学校の理念を支持し、エリートだけではなく、全ての子供のための改革に賛意を表明しているが、他方教育の国家独占に対する批判が弱いことを指摘している。(4) カザミアンは統一学校は改革の心臓であるとして原則を支持している。(5)
そして、戦後の1919年4月22日カザミアンを会長としてコンパニョン協会(L'Association des Companions)を結成した。協会の目的として規約に次のように規定された。
本協会は各学校職員間に連絡を保ち、学校と国民との間により緊密な関係を確保することによって、次の事項を遂行することを目的とする。
1.各学校の物質的・精神的状態を改良するための手段を考察し、調査し、実行すること。
2.直ちに実現の可能性のある教育上の改革を研究し、実行すること。
3.新しい教育制度を実現するために中央または地方においてなされた全ての創意あるいは努力を統一すること。
4.学制の全面的改革を実現するために世論及び議論を指導する目的をもって学校の内外において活発な宣伝をすること。(6)
こうして機関誌「ソリダリテ(SolidaitÉ)」を発行し、教育改革のための研究・実践団体としての活動を始めたのである。コンパニョンの始めた統一学校運動は、やがて教育運動の中心となり、ひろく社会的な土俵で議論が行われるようになるが、まず直接に急進党の政策の中に採り入れられるという形で大きな影響を与えることになった。急進党はビュイッソンを代議士としてかかえていたこともあり、当初から教育政策に深く関わっており、1907年の綱領は教育について次のように規定していた。
党は教育を国家の諸大権の中でも最も高貴なものの」つと考える。国家は聖職者にあらざる教師により行われる教育を自らの手で施す義務があり、またこれを施す責任を特定の者に委任する場合には、これを厳格に監督すべきである。
国民の全ての子弟はその能力に従い、完全なる教育を受ける権利を有する。公教育制度は、それ故この権利を保証すべきものでなければならない。この公教育制度はまた、職業教育の発展、並びに成人教育を可能ならしめるべきものでなければならない。(7)
この規定の意味するところは、J.フェリーの政策の徹底であり、世俗教育の擁護、教育機会の拡大であるが、1919年の綱領において「所得税、資本税、不動産税を獲得せしめるための諸便宜の提供、統一学校制度」の要求が盛り込まれた。(8) その後急進党は左右両派の対立が激化するが、1921年(リヨン)、1923年(パリ)の大会でも統一学校は要求綱領に明示された。(9)
これにはコンパニョンの趣旨に賛同し、教育に積極的に取り組んだ急進党の中心人物エリオ(Edouard Herriot)の存在によるところが大きかったといえる。(10)
<註>
- 「仏蘭西に於ける初期の統一学校論 コンパニョンの歴史とその理論」文部省教育調査部『教育制度の調査』第七輯 昭和11年 p79-82
- 同上 p83
- 16名は次のとおり。Émile Boutroux, Paul Girard, Ferdinand Buisson, Emile Goblot, Louis Cazamina, Henri Lichtenberger, C.Chabot, Desdevises du Dézert, L.Aspirant, A.L.Bittard, Victor Michel, Georges Duhamel, Lientenant, A.Sennelier, Raymond Bergougnam, A.Vulliod
- Les Compagnons "L'université nouvelle" 1 1918 p135-137 急進党は教育の国家独占を主張していた。
- ibid. p144
- 文部省教育調査部 前掲 p87-88
- クロード・ニゴレ 前掲 p68-69
- 同上 p80
- 同上 p84-85
- J.Talbott "The politics Educational Reform in France 1918-1940" p55 Michel Soulie "Le parti radical entre son passé et son avenir" p72 "La vie politique d'Eduard Herriot" p72 エリオは1919〜1936年に党首であった。(第二次大戦後も党首を務めている)タルボットによれば、エリオは「全ての子が小学校に。中等学校は才能によって進学する。統一学校は国家独占ではなく、社会和解(reconciliation)である。」と述べているが、タルボットはエリオがどこまで深くコンパニョンに学んだか疑わしい、と書いている。Talboot op.cit. p54-55
<コンパニョンの現状批判>
さて、次にコンパニョンの教育論を具体的にみてみよう。多くの点でコンドルセやビュイッソンの理論を継承しているが、いくつかの重要な変更もあった。何よりも、ビュイッソンの中心であった平和のための教育という視点はコンパニョンにはなく、むしろ明確に戦争によって疲弊した国家の再編という目的が優先していた。コンパニョンが統一学校の思想をドイツから学んだことは先述したが、それはあくまで敵国ドイツという意識の下であった。
敵が計画を立ててそれを我々に先んじて実現するのを待っているようではいけない。経済的戦争と同じように、精神的戦争においても、将来ドイツを打倒するためには、その最も良いものを奪いとる必要がある。現在の戦争の最高の目的はドイツ軍が組織を独占して、これを悪用することを防ぐことにあるのではないだろうか。(1)
そして、彼等が初めての世界大戦から得た教訓は、積極的には「国民に対してその所有する全ての物質的手段、全ての精神的資源を厳密に集中すること」「人々に共同生活をなすこと、各人の資源を共同にすること。共同社会のために身を捨てることを教えた」ということであり、(2) 消極的には「大戦は厳しい競争試験・画一的な学科・悪しき視学制度がもはや古い秩序のシンボルにすぎないことを教えてくれたことであった。」(3)
しかし、コンパニョンがケルシェンシュタイナーのように国家主義的立場に立っていたということはできない。フランスにおける戦争の惨状は生産力を著しく低下させており、生産力の復興は全国的課題であったし、ドイッヘの敵衝心も対独復讐心ではなかった。そして、コンパニョンの国家に対する理解は国家有機体説とは遠いものであった。
では、コンパニョンはフランスの教育制度のどこに批判の目を向けたのだろうか。一般的にみてフランスの教育制度が他国に比べて劣っているとはみない。むしろ初等教育・中等教育の教員の質、高等専門学校の存在、大学の質等々を誇るべきものとして讃えている。(4) しかし、「大学が大衆にはよくわからない精神的財産を享楽し、色々の流派を立てて生きてきたことも遺憾ながら事実である。ここでは頭脳を作るけれども人間をつくらなかった。」(5) つまり、それ自体として優れた内容をもっている中等教育、高等教育がそこに通う者のみが享受し、一般社会の中に、還元されていないことをまず問題にした。民衆及び実生活との隔絶である。
しかし、中等教育の内容自体に対する根本的批判がなかったことは当然であろう。中等教育が担っているとされた一般教養の質をコンパニョンは間い直していない。「新しい人文主義(Les Hunammité nouvelle)」と題された節で、フランス語、数学、自然科学を教養の土台とした後で次のように書いでいる。
この基礎的教育に加えて、ラテン語と歴史も重要である。ラテン語は今日もすぐれた知的訓練であるし、古代社会を理解することが我々の未来の指導者にとって必要である。(6)
ラテン語の問題は文化を現時点における水準において把握するかどうかの試金石であり、また中等教育の質を科学を中心として改編していくかどうかの問題であった。(7) したがってコンパニョンの批判はフランスの教育の内容にまでは充分及んでいなかったといえる。
したがってコンパニョンの指摘した問題の中心は制度問題であり、それは教育の集権主義(La centralisation universitaire)と教育の無秩序(L'anarchie universitaire)として捉えられた。
集権主義は「全てはパリから発する」(8) という点に象徴される。この弊害は具体的に次の点に現れている。
1.パリにエリートコースが集中していること。
2.コンクールジェネラル(concours général)の実施。
3.早すぎる選抜──若い体にはとても耐えられない抽象的な知識のつめこみ
4.教員の中央集権、中央志向。
5.学科内容の中央集権──視学の画一的な評価。(9)
つまり中央が地方を統制するという行政上の集権主義だけではなく、エリートコースがパリ志向であることによる競争の激化を批判するのである。
無秩序についてはどうか。「個人を束縛する中央集権が行われている一方には、個人の成功や権力だけを目的とする個人主義があって、個人主義が逆に中央集権を助長している。(10)教育界は各々の団体が連絡のない状態で孤立しており、生徒同志、生徒・父兄・教員の間の意志疎通も不充分である。その結果として大学・中等教育がとりわけ国民大衆から疎遠な存在になっている。」(11)とする。
<註>
- Les Compagnons op.cit. p16 文部省 前掲 p99 なお戦争末期からのドイツでの学校改革は、フランスに詳細に報告されていた。'Les projet de Réformes scolaires en Allemagne' in "Revue Pédagogique" 1916 p250-265 ibid. p1917 ,498-517 これはケルシェンシュタイナーやドイツ教員組合を中心とする統一学校運動の紹介である。
- Les Compagnons op.cit. p9-10 文部省 前掲 p94
- ibid. p58 同上 p128
- ibid. p6 同上 p91-92
- ibid. p7 同上 p92
- ibid. p39 同上 p116
- ただ、イギリスやドイツと違ってラテン語はフランス語の直接の源泉であるので、フランス語の理解という主張が強く残った。
- Les Compagnons op.cit. p54
- ibid. p53-58 文部省教育調査部 前掲 p125-128
- ibid. p53 同上 p124
- ibid. p58-63 同上 p125-131
<コンパニョンの改革構想>
では、こうしたフランス教育の制度的欠陥を改めるためにコンパニョンはどのような原理をたてるのか。
第一に、生産のための教育である。
広い意味での生産者を国家に提供すること、つまり「新しい教育は軍隊を養成し、幹部となりうる人々を与えねばならない。──諸君は優れた職工長、機械工、技師、工業家、事務員、政治家を必要とするにちがいない。そうならば、これらの人々を養成せよ。そのための学校を創立せよ。」(1) と要求する。戦災からの復興が第一の課題であった。
第二に、教育民主主義である。
民主主義とは、一般の利益(intérêt général)がまず考えられ、「出身のいかんを間わず、誰もがその力(forces)の及ぶ限り共同の仕事に協力することができ、功績(mérite)と有能さ(utilité)のみが唯一の階級(hiérarchie)をつくる」ことであった。(2) したがってコンパニョンの民主主義教育とは、選抜原理を示すものであって「よい生徒を形成するのは全国民の利益であり、したがって選抜を行うのが民主的教育である」という理解につながっていく。(3)
しかし、このことはコンパニョンが子供の側から教育を考察していないということを意味しない。「全ての人に対して教育が与えられると同時に、一人一人の人間のもつ全ての機能(faculté)」が呼び覚まされねばならない。全てに均衡を得た者が最もよく働くことができるのであり、それ故「身体の発達、意志の鍛練、知識の収得」を理想としたプラトンを教師とするのである。(4) そして、このように均衡を得た上で、それが職業教育に結びつくことが民主的教育である。(5)
以上の原則の適用が統一学校(école unique)であった。
統一学校制度とはコンパニョンにあっては、まず初等教育・中等教育・高等教育という体系を否定し、それを段階として再構成することである。
我々は余りに長い間、初等教育を一般教育とは別の枝と考え、閉じられた部分として考えてきた。初等教育は中等教育に先行するものであり、より高い段階に達するための段階である。(6)
そして、統一学校は全ての者──金持ちも、労働者や農夫の子もを対象とする小学校である。
しかし、そこにはいくつかの留保がつけられている。まず、校舎の統一は意味せず、授業や試験、教員の統一だけが要求され、リセの初等クラス(classes élémentaires)の廃止は改革が完全に実施された時点のこととされた。(7) 第二に、統一学校は私立学校を許容するし、国家独占を意味しない。統一されるのは学校の様式だからである。(8) 第三に、統一学校は画一学校ではないこと。したがってその具体的教育は地方の実情によって多様であってよいことになる。(9)
次に統一学校が全体の学校制度の中でどのような位置を与えられているかみておこう。小学校としての統一学校は、民主主義と指導者の選抜という二つの重要な課題を同時に解決できる形態であり、生徒を人文主義の教育と職業教育に進む者とに分ける機関である。(10)1918年のコンパニョンの著作では、このように選抜機関として位置づけられていたが、1919年の著作では統一学校はより全体的な制度概念へと発展している。そこでは、統一学校は消極的に規定すれば、小学校とリセの初等クラスの区分の廃止であり、積極的には、全ての人々の学校であるとされた。(11)そして、14歳まで義務教育を延長することによって、(12)14歳までの教育を11歳までと11歳から14歳までの教育に分割することを提起した。(13)この時点ではまだ、人文主義と職業教育という二つのコースに分岐した制度を11歳から14歳の課題として考えていたが、前期中等教育という概念への入口に立ったといえる。
更に統一学校の実現のために高等教育が改革されなければならない。(14)全ての人々に教育を開くという原理が高等教育にも適用されなければならないだけではなく、専門職としての教職の確立が急務だからである。(15)
さて、コンパニョンはフランス教育の古い欠陥(集権主義と無秩序)を克服し、統一学校制度を実現するために、新しい教育行政制度を提案している。地方分権主義(la décentralsation)と教員の組合(corporation)による教育運営がそれである。
現代社会においては、国民の向かうべき目標を定めるのは国家で、そのために実行方法を決定し、それを実行に移すのは国民の集団(corps)でなければならない。(16)
そのような集団として、現在ある公的な組織──各学校の管理評議会(conseil académique)、中央の高等審議会(Conseil Superieur)と私的な親和会(Amicales)と結合し、地方分権の原理の下に教員組合を設け、日常の管理を行なうというものである。(17)その役割は
1.地方の特質に見合った教育を実現すること。
2.国民との連係を保つこと。──例えば、商工業者の組合や団体、宗教各派の代表者、官庁や自治体などの行政機関、父母
3.国家と協力して学校を管理すること。(18)
この組合による管理は、一つには教育の政治的中立を確保するためのものであり、一つには教員の力を有効に活用するためのものでもある。そのために小学校教員の任命権を県知事から移管させること、私立学校も組合に加入させて、全教員組織とすることが求められた。(19)
では国家の任務は何か。それは強制・補助・監督に集約される。しかし、教育そのものを行う主体は教師の組合であり、国家があまりに詳細なことに立ち入ったり、画一主義、集権主義を持ち込んではならない。(20)
かくしてコンパニョンの制度原理はコンドルセからの質的転換があったことがわかる。コンドルセの科学の発展について最も高い水準での洞察と、それを教育と結びつけていこうとする精神がコンパニョンには希薄であった。このことはP.ランジュバンの活動と比べれば明瞭である。しかし、なによりも重要な変更は、コンドルセにおいては、国民は権利の主体であり、国家・社会は義務の主体である、というように純粋に相対するものとしてに把握されていたのに対し、コンパニョンにおいては、国民も国家も権利及び義務の主体と考えられていることである。もちろんこれは明確に構造化されているのではないが、この変更は第一に、組合員として教師が教育の主体となること、第二に、社会が学校を選抜機関として利用することの二点によって示されている。
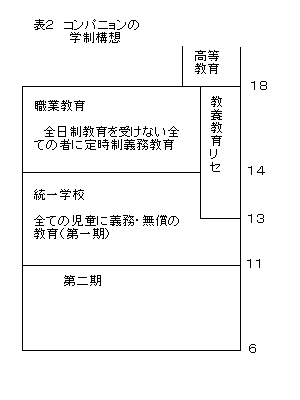
<註>
- Les Compagnons op.cit. p20 文部省教育調査部 前掲 p102 ただし、生産活動という語はマルクスの言うような物質的な意味ではないと断っている。
- ibid. p21 同上 p103
- ibid. p22 同上 p103
- ibid. p28-29 同上 p108
- ibid. p32 同上 p111
- ibid. p23 同上 p104-105
- ibid. p24 同上 p105 ドイツにおいては何よりもまず予備学校の廃止が求められたことと対照的である。
- ibid. p27 同上 p107
- ibid. p27-28 同上 p108
- ibid. p26 同上 p107
- Les Compagnons "L'iniversité nouvelle 2 ── Les applications de la deoctorine"1919 p49 (以下本書をLes Compagnons 2 と略)
- ibid. p56
- ibid. p58
- ibid. p147
- ibid. p198
- Les Compagnons 1 p65 文部省教育調査部 前掲 p133
- ibid. p80-81 同上 p145-146
- ibid. p86-87
- ibid. p68 同上 p149-150
- ibid. p68 同上 p135
- ibid. p76-77 同上 p142-143
(4)ベラール改革からアルベール改革へ
<ベラール改革>
コンパニョンの運動でにわかに教育改革の論議が高まったが、現実に改編が着手されたのは、1920年に成立した保守派の「国民連合(Bloc national)」政府によるベラール改革であった。国民連合はロシア革命への保守層の対応であったから、当然教育改革も「反改革」が主であった。
ベラール改革とは、1923年5月3日の政令による改革で、表の中等教育の系統図でわかるように、レイグ改革によって設立された第一期の現代語、自然科学を中心とし、ラテン語を必要としない、Bコースを廃止したことである。それによって中等学校の第一期から全てのコースでラテン語が必修となった。第二期においては、Cコース(ラテン語、科学)が削られた。(1) ベラール改革が一般的に復古的と言われるように、(2) 19世紀後半以降の傾向であったラテン語の負担軽減、現代科重視に挑戦したものであった。
それはどのような論理に支えられていたのだろうか。
第一に、古典語の学習こそ思考力、論理性を向上させる、という教養観である。(3) ソルボンヌ大学の総長は、ラテン語は知的訓練として必要なのであり、非民主的、という声があるが理解できない、といって、ベラール改革を支持した。(4)
第二に、中等教育はエリート教育の場であるから、水準を低下させるようなコース分化は望ましくないということである。(5) それ故ベラールは実科的な教育を中等教育に取り入れることに反対したのである。こうしたベラールの意図は、改革にあたって首相ミルラン(A. Millerand)にあてた書簡に明確に表現されている。
ラテン語、ギリシャ語をやる理由を弁護することは難しくなってきているようにみえる。その訓練の尊い目的、特別の価値は、表面的な同意やエレガンスの精神を与えるのでは決してない。それは、友愛・判断の基準を知りえることにあるのであって、人文教育こそ本質的に分析する精神・強靭さ・正確さ・理性の明証性の発達を好むからである。中等学校における古典的伝統の部分を大きくするということは、国家的利益を放棄することではないし、ましてや人間性をそこなうかつての時代遅れの鍛練に舞い戻ることではない。(6)

ベラールの改革については二つの正反対の立場から反対がなされた。一方はリセやコレージュの古典語教員で、ベラールはまだ古典語を軽視しているという批判であり、彼等は最終的には改革を容認した。(7)
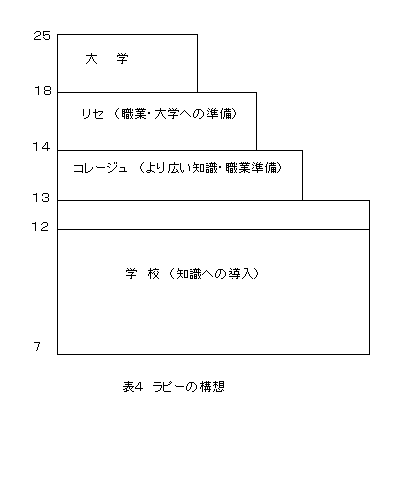
もう一方は、コンパニョンを中心とする統一学校運動からの反対である。(8) この立場から最も根底的な批判を行ったのはP.ラピー(Paul Lapie)であったといえよう。ラピーは早くも1918年の時点で実科的教育の重視、統一学校を打ち出していたが、(9) 1922年に進行しつつあるベラールによる改革に対して改革案を対置した。19世紀の中等教育の発展を概括してみると、中等学校と高等小学校、技術学校の間に厳密な区別をし、分離することはあまり意味がなくなっており、この三つの学校を包括する新しい一般教養が求められるべきである。そして、年齢と成熟度による進学を原則として表4のような制度構想を提起した。(10)ラピーの場合、一般教養の原則は必ずしも明確ではなかったが、(11)全ての者に平等な教育体系として統一学校を位置づけ、それをもってはじめてエリートが生まれるという主張は、「選抜」についてのあらたな提起であったといえる。(12)つまりベラーレにとってエリートは教育以前に存在するが、ラピーにとっては教育の結果生まれるものであった。
さて、国民連合と協調していた急進党が、1921年になって協調が崩れたために、社会党と接近し、左翼連合(Caretel des gauches)が成立し、1924年にエリオを首班とする左翼連合政府が実現した。急進党と社会党の協力については、ビュイッソンの力が大きかったといわれるが、(13)1920年の分裂以降、党としては教育政策に消極的であった社会党の姿勢も影響して、左翼連合政府においては、主に急進党によって統一学校のために取り組みが行われていった。
<註>
- Institut Pédagogique National "Réformes et la Revolution ou à nous Jour" 1962 p252-253
- I.L.Kandel "History of Secondary Education in France" 1924 p26
- I.L.Kandel "History of Secondary Education──Study of Liberal Education"1930 p213
- I.L.Kandel "History of Secondary Education in France" 1924 p16 1923年のCommission L'Academie des Sciencesでの報告
- ibid. p18
- Talbott op.cit. p85 85ラテン語の存続を強く求めた団体は、Féderation national des professeurs de lycée, Comité d'Entente Universitaire, Amicale des Priviseurs et Directrices des Lycée 等
- コンパニョンはエリートのための教育という考え自体を批判している。Kandel op.cit. p15
- Paul Lapie "Pédagogie Française" 1926 p175-180
- André Duval(ラピーのペンネーム) 'Esquiss d'une réforme générale de notre enseignement national' in "Revue Pédagogique" 1922 p81-82
- ibid. p93 フロストはラピーが教養と職業教育が調和できるとしていることを評価している。Antine Prost "L'Ensegnement en France 1800-1967" p77
ラピーの教育論は自発性を重視するものであり、とりわけビネー、モンテッソーリを高く評価していた。またピュイッソン、ラピーは世俗学校を主張しているために、後述するように、ランジュバンと同じ制度構想をもっていたが、唯物論からの宗教批判になっているのではないので、「教養論」としては異なっていた。Paul Lapie "Pédagogie Française" 'L'École laïque et le problem de la natalitÉ' in "Revue Pédagogique" 1925
- André Duval op.cit. p87
カンデルによれば、より根底的な批判は社会主義者からなされ、その趣旨は現代科こそカリキュラムの中心となるべきものでという点にあった。Kandel op.cit. p15 なおMiqueland 'Les HumanitÉs Modernes' Marcel Brauschbig 'L'Eensegnement des les Humanités Modernes' いずれも "L'Éducation" 1924-1925
- Talbott op.cit. p75
<アルベール改革>
さて、文相アルベールは公教育高等審議会においてベラール改革を批判し、積極的に改革を個別に展開していった。まず具体的に中等教育についての法令をあげておこう。
1924年3月25日省令。フランス語、ラテン語、ギリシャ語、現代外国語を必修とする。女子中等学校を6年制とする。ただし、バカロレアも可能とする。
1924年5月10日省令。初等教育修了証書(CEP)で中等学校の第6年級、第5年級に入学する資格があると認める。
ここまでは、ベラールによる改革である。以降アルベールによる改革となる。
1924年8月9日、現代コースをリセに戻す。
1925年1月9日省令。2月27日省令。中等学校、高等小学校、技術学校はテストで奨学金を与える。
1925年6月3日省令。英語またはドイツ語を必修とする。
1925年6月6日回状。中等学校は一般的形成のみならず、特殊的形成が行われなければならない。Aコース、Bコースを単に語学による分化と捉えるのでなく、両者を結合して考えなければならない。そのために共通コースが必要で、同じ方法、同じ内容、同じ教師が必要である。
1925年7月20日回状。ラテン語、ギリシャ語は精神の形成であり、英語、ドイツ語は実用である。
1925年9月12日省令。奨学金テストについての実施規定。(1)
これらの諸改革は明確に二つの方向性をもっている。第一に、奨学金等による教育機会の拡大である。この政策はベラールの時に着手されたものであって、したがって二人の改革には連続性もあった。(2) 第二に、現代科の重視である。すなわちアルベールはベラールが否定したレイグ改革を復活させたのである。
ところでベラールとアルベールとでは古典重視、現代科重視と現象的には逆であるが、一つの共通した模索があった。ベラール文政下の1924年1月の公教育高等審議会は、中等教育に関して主に女子中学校の拡充と財政問題を論議したが、あわせて混合カリキュラムの構想が提案され、10月をめどに採用することが確認された。(3) アルベールに代わった1924年の公教育高等審議会では、現代科及びフランス語の重視が決められたが、フランス語を現代科とは別の領域と考える人と、フランス語が現代科の中心であると考える人が対立した。(4) 議論そのものはもちこされたが、特に後者の側から共通カリキュラムの考えが打ち出されてくる。
1925年1月の公教育高等審議会では、「アマルガム amalgame(混合カリキュラム)」という構想を打ち出した。前年からの継続で現代科の位置づけをどうするかの論議が行われた際、現代科と古典と同じように重視することについて異論が出され、そこで妥協として「融合(fusion)」という考え方がまずとられ、そこからアマルガム構想が出てきた。
アマルガム構想とは
1.現代科学習の一般的価値の承認
2.中等教育第一期の二つの課を部分的に関連付け、融合させること
3.数学に適当な位置を与えること
である。(5) これによって中等教育第一期が他の初等後学校(高等小学校、技術学校)と部分的に同じ内容をもつ課程となり、前期中等教育という一つのまとまりを持つ前段階となった。
さて、アルベールは改革を始めるにあたって次のような趣旨の文書を公教育高等審議会に対して提出していた。
1.今回の改革は二つの原理に基づいている。第一に、中等学校の本源的精神を保持しながら、エリートを補充する。第二に、二つの中等学校、二つの教養というのではなく、あくまでもひとつの中等学校、一つの教養であり、その中での選択という形をとる。
2.現代語は単なる語学としてではなく、精神の形成として行なう。AB両コースの共通点は精神と教養の結合ということである。(6)
そして、現代科について次のように定義している。
哲学、倫理、政治、文明等については古典的教養と同じである。特徴は第一に、現代文明を中心にすること、第二に、自然科学に多くの時間をさくこと、第三に科学の実験、フランス語、歴史を詳細に行うこと。(7)
アルベール自身必ずしも伝統的な中等教育を根本的に批判していたわけではないが、現代科を重視することによって、そしてまた、「大衆リセ(lycées populeus)」という前期中等教育の発想を示したことによって、(8) 小学校とリセ、コレージュの初等クラスの中等学校と高等小学校とのカリキュラム上の接近を進めることになった。それは表5にみられるような1926年10月1日の政令に具体化された。ビアールはこの政令によって統一学校への動きが制度的に始まったと評価したように、(9) 初等・中等を通しての統一化を促進したものぞあるが、しかし依然として、二つの体系には越えがたい相違があった。
それは高等小学校のみに課せられた「公民科(Morale, Insturction civique, Droit usuel, Economie politique)」によって示されている。高等小学校は「教育ある労働者(travaillers instruits)」(10)を作りだすためのものであり、それは多くの実科に示されているが、公民の存在にも示されているのである。1920年に出され、1931年になお有効であった訓令には公民科について次のように書かれている。
第一年目には個人の単純な義務、社会関係、社会的責務等について。
第二年目には国家、国家組織、道徳的価値について。
第三年目には私的権利、政治、経済。
表5 1926年10月政令による時間数
| 第6年級 | 第5年級 | 第4年級 | 第3年級 |
|---|
| 共 | A | a | B | es | 共 | A | a | B | es | 共 | A | a | B | es | 共 | A | a | B | es |
|---|
| フランス語 | 4 | | | 3 | | 4 | | | 3 | | 4 | | | 3 | | 4 | | | 3 | |
|---|
| 現代外国語 | 4 | | | 1 | | 4 | | | 1 | | 3 | | | 4 | | 3 | | | 4 | |
|---|
| 幾何 | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
|---|
| 代数 | 2 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
|---|
| 理科 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | |
|---|
| 図画 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 15 | | | | 1 | 15 | | | | 1 | |
|---|
| 体育 | 2 | | | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | | | 2 |
|---|
| ラテン語 | | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | | | | 5 | 7 | | | | 4 | 6 | | |
|---|
| ギリシャ語 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | |
|---|
| 歴史 | | 2 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 2 | 3 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 1 | | 15 | 15 | 15 | 1 |
|---|
| 数学 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | |
|---|
| 地理 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | |
|---|
| 美術 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
|---|
| 公民 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 |
|---|
| 物理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 手工 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | 4 |
|---|
| タイプ | | | | | 2 | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
|---|
| 歌唱 | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 2 |
|---|
15は1.5のこと。esはESPのこと。
このようにごく基礎的な国民としての道徳及び政治経済的な知識に限定されており、「経済計画は公教育に適用されなければならない。民主主義は全ての子が知識をもち、共和国が要求するエリートをつくる時にのみ現実化する」(11)と規定する1926年10月1日の政令の中等教育観とは隔たりがある。
高等小学校において「公民」の占める位置は中等学校においては「精神(esprit)」であり、前者が所与の社会的価値を学びとることであるのに対し、後者は所与の社会的価値や文化を一つの素材として行う主体的な社会・文化に関わる精神諸活動のことであり、しかも「精神」の形成は中等学校の最上級に行われるアグレジェによる哲学教育という高い水準が制度的に保証されていた。
こうした社会的価値についての教授の根本的差異がある限り「共通カリキュラム」はまだ「教養の統一」になりえていない、というべきであろう。(12)
<註>
- 阿部重孝は、これらの改革が小学校と中学校を本当に接続できるか否かについて疑問を述べ、リチャールの調査を紹介している。それによると1908年に高等小学校からリセ、コレージュに行った者は、387人、それが1921年には122人になっている。奨学金の志願者は小学校で、1922年に1702人、1923年に3401人。小学校卒業生は毎年75万人で、小学校卒業試験に合格しているのは22万人のみで、小学校以上への進学者は10%に過ぎない。
このことから阿部は小学校と中等学校の溝はまだ大きいとしている。『阿部重孝著集7』 p225
- コンパニョンのベラール改革批判は直接の資料がないが、マイヤーによれば、1.外国の産業や商業に勝つために専門家が必要であり、より良い技術訓練が必要である。2.より大きな注意が大衆の教育に向けられるべきである。3.全ての段階で無償とすべきである、と批判していた。ここには現代科の重視・奨学金という不充分な機会拡大策の批判が現れている。Adolf Meyer "Development of Education in the Twentieth Century" 1949 p219
- Gerges Beaulavon 'La session du conseil superieur de l'instruction publique 22-26 Janvier 1924' in "Revue Universitaire" 1924 1 p125- 135
- Georges Beaulavon 'Conseil supeieur 2-5 Juillet' in "Revue Universitaire" 2 p124-131 後者に立つ論として M.F.Brunot 'Une Défeuse des Humanités Modernes' in "L'Éducation" 1924-25 p350-351 一方でフランス語を古典教育の一環として捉える論もあった。Henri Bernés 'Le fran&ccerdil;ais séparé du Latin et l'enseignemnet secondaire' in "Revue Universitaire" 1927 1 p406
- Georges Beajlavon 'La session du conseil superieur de l'instruction publique 19-23 Janvier 1925' in "Revue Universitaire" 1925 1 p127-133
- Fran&ccerdil;ois Arbert 'Projets d'arrêtés concernant le plan d'études et les Programmes de l'ensegnement secondaire (enseignement moderne)' in "L'Éducation" No. 6 1924-25 p319-324
- ibid. p324
- ibid. p321
- F.Vial "Vues sur l'école unique" p21
- 'Instruction Ministerielles de 30 septembre 1920' in "Plan d'études et Programmes de écoles primaire superieurs de gar&ccerdil;ons" 1931 p91
- "Horaires et Programmes de l'enseignement secondaire des Garéons" 1928 p11
- Henri Boivin 'L'École unique devant la presse' in "Revue Universitaire" 1925 2 p329 本書は「身体は同一の場で学ぶが、モラルは共にしない」といって保守派に対して統一学校を弁明する見解を紹介している。またアルベール改革の進行と同時に、兵役義務のための体育、モラル強化が教育問題として議論されていたことに注意すべきであろう。O.Gassion 'Question Militaire et Maritimes' in "La Revue de France" 1924 p188
(5)統一学校論の諸潮流
<リセ・コレージュの統一学校反対論>
アルベールは個別的な改革を進める一方、統一学校について広く論議を集約することを目的として、ビュイッソンを委員長とする「統一学校委員会(Commision pour l'école unique)」を1924年12月に発足させた。更に1925年には統一学校の実現をめざす人々が「統一学校研究行動委員会(Comité d'étude et d'action pour école)」を組織し、活動を開始した。こうした公的・私的団体の活動によって統一学校についての問題は大きな社会的問題となり、議論がかわされるようになった。また、統一学校に反対する運動も活発になった。統一学校の主張の特徴と意味を鮮明にするために、まず反対論からみてみよう。
1926年5月23日から26日に会議をもったリセ、コレージュ卒業生が次のような決議を採択した。
1.統一学校の理念は捨てるべきである。
2.初等教員の検定は尊重される。
3.バカロレアのみが高等教育に進む権利を与える。
4.奨学金の創設は考慮され、研究され実現されるべきであるが、家庭の経済負担を考慮しつつ、子供については才能(mérite)に従うべきである。
5.統一学校委員会に我々のメンバーを多く入れること。(1)
イエズス会も、統一学校はプロレタリアがブルジョアの恨みを増長させるだけだ、という理由で反対した。(2)
こうした反対の理由を明確に述べているのは、中等学校の教員であるV.ブイヨ(V.Bouiliot)である。ブイヨの最大の論拠は「親の教育の自由」である。
「実際にリセの初等クラスがなくなったとしても、初等クラスを望んでいる親は子供を小学校には入れないだろう。それを強制的に小学校にいれようとすれば、教育の国家独占が必要であるが、それは革命の伝統である『自由主義』に反するであろう。(3)
ここにはかなり強引な論理操作がある。近代原則としての「親の教育の自由」は、家庭教育の自由、私立学校の自由であったが、リセ、コレージュの初等クラスは国立・公立であり、したがってブイヨ自身の主張する「教育の自由」に妥当するものではない。しかし、後でみるよう統一学校反対論が「教育の自由」対「教育の国家独占」という対立図式を公にしたことによって賛成論者もその図式に巻き込まれることになった。
ブイヨの第二の論拠は、当時のプロレタリアートの知的水準では、教育の平等を形式的に実現したら、社会不安を引き起こす、というものである。(4) もちろんプイヨ自身はプロレタリアートの知的水準を高める対策を示すわけではない。
結局、ブイヨが守ろうとするのは中等精神(esprit secondaire)である。小学校と初等クラスは、事実上カリキュラムが同一化しているので教育内容は同じであるが、精神が違うめだ、それが何故意いのだ、という。(5) そこには公立学校の「公的性質」の無視がある。「特権者の学校という非難があるが、初等クラスを小学校化したところで、貧乏人の小学校と金持ち用の小学校つくるだけではないか」(6) と述べ、中等学校の初等クラスの無償化にも反対する。「リセの初等クラスが有料であることに対する反対があるが、それは親が望んでいることなのだ。」(7)
こうして、ブイヨは「教育の自由」を「親の学校選択の自由」におきかえ、それで「諸公立学校の選択の自由」を意味させ、その基本に経済力をおくのである。
プイヨのように表だって反対はしないが、最も消極的に賛成することによって、事実上統一学校を無意味なものにしようとする人々の意見は、次のラムレー(Lucien Lamoureux)の説明に示されている。
1.全ての子供が全段階において平等の権利をもち、能力以外によって差別されることがないこと。
2.子供の能力が明確になるまで、最大限有効に個々の能力を活用すること。(8)
統一学校支持論が常に具体的であるのに対し、消極論は原理に終始する。
ブイヨと全く正反対の政治的立場から、統一学校に反対したのはフランス共産党である。1925年5月29日のユマニテ(Humanité)は、統一学校は「だまし(duperie)」「民主的かつぎ(beteau démocratique)」と批判し、資本主義社会での統一学校など幻想だと主張した。(9) そして、1927年には次のような理由で統一学校運動を批判した。
第一に、ラピーは現行の高等教育を批判していないこと。
第二に、財政難で実施困難といっているが、金があっても、統一学校を実現する気などないのだという批判。
第三に、社会党のゾレッティやブルムは産業に有益であるという理由で統一学校に賛成しているのであって、マルクス・レーニン主義とは無縁だということ。(10)
1924年以降のフランス共産党は、中立教育の立場を完全には捨てず、ソビエトの階級教育と対立してはいたものの、(11)全体としてはボルシェビキ化の時代であり、(12)階級に帰着する批判に終始した。
<註>
- H.Boivin 'Qui en est la question des l'école unique' in "Revue Iniversitaire" 1927 2 p11-12
- Talbltt op.cit. p115 国民カトリック連盟(La Fédération nationale catholiqye)は1926年の総会で、学校に関して、1.統一学校に対する闘い、2.小学校教員組合への闘い、3.私立学校への補助金のための闘いを要求として掲げた。木下半治『フランスナショナリズム史(一)』図書刊行会1976.11.20 p230
こうしたカトリックの認識の基本は、カトリック派の集会(1925年2月10日)の「子供を自己の欲するままに養育する家父の自由」というものであった。同上 p297 ただフランスのカトリックは自らの資金で自由な教育を行うという「教育の自由」をイギリスのパブリックスクールほど徹底させていなかったことがわかる。
- V.Bouillot 'Les classes élémentaires et l'école unique' in "Revue Universitaire" 1924 p306-307
- ibid. p305
- ibid. p309
- ibid. p304
- L.Lamoureux 'L'École unique' in "Revue Univeisitaire" 1926 2 p19
- Heinri Boivin 'L'école unique devant la presse' in "Revue Universitaire" 1925 2 p333 1936年12月のトレーズの演説の中でも「左翼連合は、労働者階級の一部が階級協力を実行して資本の利益のために、ブルジョアジーのある一派の後にくっついたものである。」と述べている。トレーズ『フランス人民戦線』国民文庫 p139
- E.Chanvelon 'Un mythe réformiste l'école de classe' edi. Daniel Lindenberg 1972 p83-92
- Lindenberg op.cit. p64 増井光夫「国際教育運動の成立史(上)──教育インターナショナルの研究ノート(1)」『教育運動研究』No 12 1976.2 p81
- ibid. p49
<統一学校支持の二つの立場>
では、統一学校を支持する者はどのような議論を展開したのだろうか。
統一学校の積極的支持者は、大別すると二種類の立場があった。一方は初等・中等教育を含めて統一化を志向するものであり、他方は初等教育のみの統一を志向するものである。
前者の代表はP.ランジュバンであった。
ランジュバンは統一学校の原則を次のように整理している。
1.全段階での平等と無償
2.職業教育と一般教育の並立(Juxtaposition)
3.全段階での移行可能性(1)
この原則の特質は全段階に同じ原理を適用していることであり、この原則の下に、ランジュバンは15歳までの統一的教育内容の必要性を主張するのである。(2)
第二の立場は、いわゆる「三分岐制度」を主張するものである。この立場は原則が段階によって異なることになる。例えばベルトー(Aimé Berthod)は次のように主張している。
中等学校の本質は、高等教育の準備ということにあり、高等小学校から直接大学にいれるのは誤りである。(3)
またA.ロモンは次のように述べている。
統一学校とは、私学も含めて、国による監督・義務教育の延長・無償のことである。(4)
ロモンの主張からは、中等教育の無償は導き出されてこない。
この「三分岐」型統一学校論こそ、社会的には最も大きな力をもち、事実学校制度改革をリードしていくことになる。その意味でエリオこそこの立場の代表者であった。
エリオは、各国の教育改革について広範囲に調べており、ドイツ統一学校運動、イギリスのフィッシャー法による改革に特に注意をしていた。そして、とりわけ職業教育に関心を寄せた。それは職業教育によって生産力を復興させること、それが民主的な改革によってこそ実現するという民主主義の主張が結びついたものであった。(5)
1926年4月15日の上院の答弁で、統一学校の本質的部分は、全ての者が奨学金テストを受けられること、第二、第三共通試験(Concours common)によって三分岐に分かれること、と答えていている。(6) もっともエリオは奨学金に倭小化して統一学校を考えていたわけではなく、後の中等学校の無償化に大きな役割を果たしているが、エリオが「階級的分化を止めるべきだ」(7) というのは、分化についていえば小学校に限定されていた。
<註>
- 'L'école unique ── conference de l'école hautes étude sociale 1926.2.26' in "Revue Universitaire" 1926 1 p326 ブリュンシュビックは農村や大部分の町では沢山の学校をつくることは不可能だという理由で、統一学校に賛成している。'L'école unique ── conference de l'école hautes étude sociale 1926.2.19' in "Revue Universitaire" 1926 1 p325
- ランジュバンの統一学校論については第二部第六章参照
- 'L'école unique ── conference de l'école hautes étude sociale 1926.2.12' in "Revue Universitaire" 1926 1 p323
- 'L'école unique ── conference de l'école hautes étude sociale 1926.2.21' in "Revue Universitaire" 1926 1 p236 同様の見解としてErnst Richard 'Autour de l'école unique ── l'expérience d'autum' in "Revue Universitaire" 1927 2 ,109-110
- Edouard Herriot "Crée 2" 1925
- H.Boivin 'Qui en est la question des l'école unique' in "Revue Universitaire" 1927 2 p109-110
- Herriot op.cit. p157
<選抜の論餓>
次にいくつかの個別的な論議についてみておこう。
まず、選抜の問題である。コンパニョン以来、選抜の民主化が統一学校運動の基本的テーマであったことは既にみた。フランスにおける選抜論の特質は、試験による選抜に対する批判的評価が少なからず存在したことである。P.ブッシュ(Paul Bouchy)は「人は本来多様であり、テストによる徹底した選抜は心理学的に誤りである」と述べ、(1) 子供が特殊なことがらに興味をもつようになるには、ある程度の成熟が必要であるので、統一的な小学校の中で次第に能力に応じた指導、進学をさせるべきだ、と主張している。(2)
リセやコレージュには、親が資力をもっている場合に入れるのであるから、授業についていけない者も多かったし、また中等教育の最終目標であるバカロレアには三分の一しか合格せず、中途の脱落者も多かった。こうした現象は大戦前から指摘されており、中等学校の「貧血現象」と呼ばれていた。(3) 小学校から優秀な生徒が入るようになっても、怠け者で劣った生徒が富裕な階層から入学してくる事態に憤りをもつ中等学校教師は多かった。(4) その対策が中等学校の無償化と入学試験の実施であった。財政難からの反対は多かったが、ブイヨの如き反対論はさすがに少なく、無償と入学試験は漸次実施されていくことになる。
したがって選抜をめぐる議論は、主にその時期に限定されていたが、むしろ重要なことは選抜に関する教育的批判が提起されていたことであろう。
第一に、職業指導の立場からの批判である。
第二に、能力の多様性についての主張である。「才能は無限で多様である。遅くなって発達する者がいることを忘れるべきではない」という意見を、ボアバンは紹介している。(5) この二つは教育改革に、ただエリートの選抜を期待する者への根本的批判であり、選抜と指導という問題に引き継がれていくことになる。
選抜を異なった視角から問題にしたのは社会党であった。分裂以降、社会主義者の教育論議は停滞していたが、社会党員のゾレッティが中心となり、「第二、第三段教育のための連盟(Fédération de l(enseignement aux 2e et 3e degrés)」を組織し、1.1つの小学校、2.多様な中等学校、3.全段階での無償、4.国家独占(ブルジョア国家の国家独占ではない)という主張の下に『教育(L'Éducation)』を発行して活動した。(6) その中で「統一学校はブルジョアとプロレタリアのあいの子をつくる(Jean Guéheno)」「高い教育を受けた労働者階級の子がブルジョアの側」になっていく(Albert Thierry)」(7) ことが深刻に受け止められた。ここから、ブルジョア文化に対抗するプロレタリア文化の創造が提起されたが、社会党内では文化の「調和」という発想が主流を占め、(8) 1929年のナンシー大会でも、「統一学校・世俗性・国家化」というプロレタリア文化とは異なったスローガンが採択されたのみであった。(9) この問題は未解決のまま残されたといえる。
<註>
- Paul Bouchy 'Une opinion sur le principe de la sélection' in "Revue Universitaire" 1924 2 p31
- ibid. p32-34
- Félix Pecaut 'École unique et Démocration' in "Revue Universitaire" 1919 p245
- 『カンデル年報』1926 p107 Maurice Lacroix 'La gratuité de l'enseignement secondaire' in "Revue Universitaire" 1927 2 p312
- Henri Boivin 'L'École unique devant la presse' in "Revue Universitaire" 1925 2 p38 知能テストの創始者のビネーにしても、テストについては部分的目的に限定していたし、生徒の素質・能力については多様性を認めていた。ビネー『新しい児童観』波多野完治訳 明治図書 他にHenri Peiron 'La notion d'action d'aptitude en éducation' in "Pour l'ere nouvelle" 1929.7-8 p138 'Les origines en France, de la méthode des Tests et la signification pédagogique de l'Æuvre de Binet' in "Pour l'ere nouvelle" 1933.7
- François Bernard "Le syndicalisme dans l'enseignement ── Histoire de la Federation de l'enseignement des origine à l'unification de 1935" Tome 2 p120
- ibid. p132-134
- ibid. p124-135
- ibid. p149-151 Daniel Ligon "Histoire de Socialisme en France 1871-1961" 1962 p374
<国家独占と私学>
第二の論点は教育の国家独占の問題である。この点は既に各々の論の中に出てきている。言い換えると、教育の公的性格をめぐる問題であり、大きく三つの立場があった。
第一は、ブイヨやカトリックにみられる「教育の自由」を論拠として、私立学校をそのまま容認するものである。これは、第三共和政下の最大の教育問題の一つである世俗性(laïcité)について、宗派学校を主張する立場とも相通じていた。
第二は、社会党にみられる国家独占の主張である。しかし、社会党の国家独占の主張は必ずしも明確ではなく、次の第三の立場とも重なるものをもっていた。この立場の典型的な主張は、私立学校(ほとんどは教会設置の宗派学校であった)の廃止、あるいは補助金の廃止であった。 (1)
第三に、私立学校関係者を含めた学校管理組織をつくり、その管理下におくことによって私立学校にも公的性格を付与しようとするものであった。(2) コンパニョンの案がこの代表といえよう。
さて、1920年代後半アルベールによって開始された統一学校についての論議は、20年代末に下火になりながらもモンジー改革を生み出し、そして、一方で民間の統一学校支持者によって作られた「統一学校研究行動委員会」によって、一つの合意が形成されていった。1927年3月に出された報告は、
1.無償の中等教育、高等教育
2.能力による選抜
3.一つの国家機構によって全学校組織が管理されること
4.統一的な中等学校
5.15歳までの義務就学
等を骨子とするものであった。(3)
<註>
- この点は、ジャン=ゼイ改革の過程で主に共産党によって主張された。
- 大坂治は、全国初等教育教員組合(SN1)のブーランジェ(Boulanger)の案を紹介している。それは1. 全ての者のための義務制統一学校、2. 唯一国民のみが教育権を持つ、3. 宗教教育は学校以外で行う。4. 全ての教育機関は国民化される。したがって三者(国家・利用者・教師)のコントロールに服さない私立学校は、もはや存在しないというものであった。大坂治「大戦間フランスにおける統」学校論に関する一考察 ──『教育の国民化』問題を中心として ── 」パンフレット
- Talbott op.cit. p124